久方振りに小澤征爾さん、サイトウ・キネンのチャイコフスキーの「弦楽セレナード」を聞きました。
余談ですが、今フィリップスレーベルがなくなって、ロンドン、デッカレーベルの傘下になりましたが、フィリップスのロゴぐらい遺して欲しかったと未だに思います。
素朴な味わい、温もりがあるコリン・ディヴィスさんの演奏。これもカラヤン盤の次に親しみのあるCDです。
軽やかさと柔らかさのある温かみと明るさのある音色が特徴です。
特別聞き込んだわけではありませんが、チャイコフスキーの「弦楽セレナード」のCDでは印象に残っています。
 | チャイコフスキー:弦楽セレナード/モーツァルト:「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」他 1,683円 Amazon |
左下のデッカのロゴがどうしてもマッチしないような気がして、違和感があります。神経質でしょうか……。
さて、その「弦楽セレナード」は、意外にCDは少ないのではないかと思われますが個人の知識がないせいか左様に感じます。
幾つか個人が印象に残っているCDを紹介します。
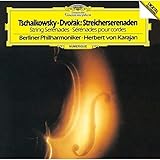 | チャイコフスキー&ドヴォルザーク:弦楽セレナード 1,683円 Amazon |
よく聞いたカラヤンの演奏。ドヴォルザークの「弦楽セレナード」も爽やかで個人は気に入っている作品ですが、カラヤンらしい力強く重低音の弦楽器の音色が特徴で馴染み深いです。
 | チャイコフスキー:交響曲 第2番 小ロシア、弦楽セレナード 2,060円 Amazon |
これは小林研一郎さんが「弦楽セレナード」を初めて録音された演奏ですが、思いの丈をぶるつける、仰反るような感じではなく円やかに仕上げたように感じられます。
2番の交響曲を含めて感情的にならずやや思惑ありげな表情を見せ、小林さんの内面を見るかのような、それは以前では感じられなかった表現、音色が耳に残りました。
このロンドン・フィルとのチャイコフスキーは5番もなかなかの名演でした。個人は全て聞いておらず、あとは1番を聞いたのみです。
エクストンレーベルならではの高音質も特筆すべきことです。
 | チャイコフスキー/ドヴォルザーク:弦楽セレナード(エソテリック SACD) 4,890円 Amazon |
どなたが1番優れているということは思いません。いずれも良かったです。
2000年前後は人材派遣会社スタッフサービスのオー人事のCMで一時期、時の曲となりました。水戸中納言が助三郎、格之進があてにならず、オー人事に頼もうか……と嘆いた姿が面白かった記憶があります。
さて、その「弦楽セレナード」はチャイコフスキー自身も良い出来栄えと思っていたようで、初演を心待ちにしていたというエピソードを百田尚樹さんの著書から知りました。
例のフォン・メック夫人に「強い内的衝動によって書かれたもので、だからこそ真の芸術的な価値を失わないものです」と手紙で報告しているくらいですから、その自信は相当なものだったのではないでしょうか。
当時1880年40歳前後で作曲家としても世間に認知され、これから期待されていた時分に作曲された「弦楽セレナード」は初演も大成功だったそうで、第2楽章のワルツがアンコールされたとウィキペディアにありました。
下は同じくウィキペディアにある第2楽章と第4楽章のイメージ絵画だそうですが、どなたの作品でしょうか。
フィナーレはすみません、個人が感受性が乏しいせいかあまりうまく説明できませんが、音楽が天に昇華されていく、空にふんわりと昇天していくイメージ……でしょうか。
久方振りに「弦楽セレナード」を聞いた所感です。

