山岡荘八歴史小説・徳川家康 第1巻 出生乱離の巻 天下統一への道まであと25!
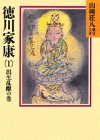
|
徳川家康〈1 出生乱離の巻〉 (山岡荘八歴史文庫) (1987/10) 山岡 荘八 商品詳細を見る |
ということで、忘れないうちに書き残しておきましょう。
徳川家康 第1巻 出生乱離の巻
こちらは冒頭での章で・・・
「暁以前」
武田信玄は二十一歳
上杉謙信は十二歳
織田信長八歳
後の平民太閤、豊臣秀吉はしなびた垢面(こうめん)の小童だった。
この年、天文十年-----
という見出しから山岡荘八氏の徳川家康が幕を開けました。
第一巻のこのときには、まだ家康は生まれていないんですよね・・・。
第1巻 出生乱離の巻では家康・・・このときは竹千代という幼名でスタート。
父、松平広忠と母、於大が出会い、そして竹千代誕生、さらに広忠と於大の離縁を描いています。
もう、凄いですよ・・・
何が凄いかっていいますと、これまで読んできた秀吉や伊達政宗なんかは、一冊300ページちょっとだったんですが、徳川家康はほとんどが一冊500ページ弱あります・・・。
読むペースが極端に遅くなりましたが、その分一冊の重みがあると感じます。
私はあまり理解できないままに一巻を読み終えたのですが・・・登場人物があまり聞きなれないものが続々と登場してきたので、正直、あまり面白いとは感じませんでしたね。
しかしながら、吉法師時代の信長が登場するなど、描写は非常に細かいものになっています。
中でも注目の登場人物は・・・
山岡荘八の豊臣秀吉にも登場していた架空の人物、「竹之内波太郎」の活躍が序盤は目立っています。
とりあえず、徳川家康はただいま3巻まで読み上げましたが、ところどころに登場しては松平家を助け、信長や、秀吉も一目おく野武士の首領で大軍学者という設定の人物。
いきなり出てきてはインパクトがあり、気がつけばまたいなくなっているという波太郎。 熊の若宮とも呼ばれている波太郎。
彼の存在が物語りを面白くしているのかもしれませんね。
といことで、この山岡荘八氏の徳川家康なんですが、全26巻という非常に長い小説の一巻のあとがきには・・・
読者からもらった投書に当時の新興勢力織田氏をソ連になぞらえ京文化に憧れを持つ今川氏をアメリカになぞらえて、作者は弱小三河を日本をして書いているのではないかというのがあったそうで、同氏はそうかもしれないと答えたそうで・・・。
いろいろとありますので、一部抜粋しただけでは誤解を招く恐れがあると思いますので御陵下さいね。
見方とすれば非常にわかり康見方なのかも知れないですね。
ただ、この徳川家康はあとがきの中に説明がされていまして、徳川家康という一人の人間を掘り下げていくことよりも、周囲の人物も取り扱っていくことだということが説明されています。
ですので、読んでいますと、時代の流れで、途中で、信長パートになったり、藤吉郎パートになったり、また家康パートになったりしているのが特徴だと思います。
ある本で読んだことがあるんですが、日本には三国志のような大河ドラマはないそうでして・・・。
戦国の歴史の物語を知る上では、織田信長や豊臣秀吉、伊達政宗といった武将、個人に注目されているものばかりなので、これを読めば戦国のことがわかるといったものがないようですね。
今まで読んできた山岡荘八氏の歴史小説も、個別に扱ってはいますが、それぞれが個人を掘り下げつつ、その武将を取り巻く人々も十分の取り扱って表現しているところがわかりやすいですね。
ですので、これだけの長編の徳川家康、彼をとりまくいろんな人物が登場し、75歳生き抜いた家康の生涯を26巻で描いていくので、これを読めば、まず戦国史のことがいろいろとわかることでしょうね・・・と信じて読んでいます・・・はい・・・。
あとがきの最後には・・・
哲学の誕生とその新しい哲学によって人間革命がなしとげらると書いてあります。
人間革命とはまた難しい哲学だと思いますが、境涯の変化とうような意味と私は受け止めております。
山岡荘八氏の描く歴史上の人物、戦国武将たちは、ただ史実に基づいてえがかれているのではなく、その生涯の中の転機により、生き方に変化が生じることをよく描いています。
豊臣秀吉では明智光秀が生きていたという説をもって、出家した光秀が陰ながら、秀吉を支えるといった境涯の変化が描かれていたりとさまざまです。
この徳川家康でもそういった人間革命という哲学が幾多も描かれています。
長くなりましたが、次は第二巻の概要とちょっとしたかんそうをば書いて見たいと思います。