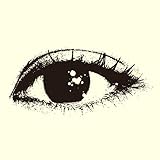- CIRCUS/栗山千明

- ¥3,059
- Amazon.co.jp
----------------------
栗山千明のシングルが布袋寅泰・浅井健一・椎名林檎とロックシンガーたちにプロデュースされ続けていることは耳にしたこともあるだろう。
今度発売のアルバムは「CIRCUS」と名付けられ、佐藤タイジにヒダカトオル、9mmといった錚々たるメンツが楽曲提供・プロデュースをしている。
私自身はまだ浅井健一プロデュースの「コールドフィンガーガール」と、椎名林檎提供の「おいしい季節」しか耳にしていない。
そしてこの二曲を聴いて感じたことは、栗山千明の“表現力”だった。
いい意味でも、(残念ながら)悪い意味でも、彼女の女優としての表現力の豊かさを感じさせられてしまったのだ。
「コールドフィンガーガール」はベンジー節が炸裂した、メロディとそのへヴィさが癖になるナンバーだと思うが、
いわゆる“ロック声”を炸裂させて唄う彼女は、たしかにベンジーの創り上げた世界にそぐわないそれだと思う。
個人的には、ベンジーの世界はベンジーの声ありきの部分があると思っているのが、それを“女”の声で再生するとこういう風になるのか、とも思ったし、それはそれで新しくてかつ快いと思った。
また「おいしい季節」では林檎さながらのスウィートな声も唸り声も披露してくれたと思う。
彼女の唄をわたしは下手だとは思わないし、
この錚々たるメンツの独自の世界観についていけるその対応力、つまり幅の広さはシンガーとしての価値があると思う。
だが残念ながら、わたしに見えるのは、この錚々たるメンツのそれぞれの楽曲を歌う彼女、という姿でしかなく、
そしてそれはシンガー・唄い手としての姿のそれではないように思えるのだ。
それはプロデューサーの世界に見事に対応し、唄の主人公になりきる、いや、もっと言ってしまえば、プロデューサー自身になりきってしまう“女優”の彼女なのである。
浅井健一にも椎名林檎にもまるでなりきれる彼女のそれを否定はしない。
そもそも、ロックシンガーによってプロデュースされる栗山千明、というコンセプチュアルのもとで生産されたアルバム「CIRCUS」なのであろうし、そのコンセプトにのっとっている限り決して間違えたことでもないと思う。
だがしかし、彼女の“才能”が、シンガーとしての活動にも関わらず“女優”のそれだと感じさせてしまうことは些か問題でもあるように思う。
なぜなら、「だったら浅井健一が、椎名林檎が唄えばいいのに」という一言がどうしても付きまとってしまうからなのだ。
彼女の才能は完璧すぎて唄い手としてあまりにアクがない。
わたしは栗山千明を通してベンジーを、椎名林檎を感じることしかできないのである。
だがしかし、これだけのメンツが名をあげるアルバムというのもなかなかあるものではない。
なによりも素直に、栗山千明自身が彼らへの憧れや思慕を以ってこのアルバムは造られたのだろうし、
それに応えたプロデューサーたちも彼女のこの表現力を以って、造りたいと思ったのであろう。
わたしはそこにある愛といったものを否定などしたくない、と強く思う。
おそらく「栗山千明」というアーティスト、を考える前に、まずはこのアルバムを聴いてみることが先決なのであろう。
「CIRCUS」、聴いてみようと思う。