選挙中はな、「ワイが当選したら戦争なんか24時間でピタッと止めたるわ!」って、めっちゃイキって言うてたくせにな。いざ自分の思い通りにいかへんかったら、「こんなんワイの戦争ちゃうし、仲介なんかせぇへんわ」って、ポイッて投げ出すんやで?そんなん、めっちゃ無責任ちゃうん?口だけ達者で、ええカッコしいやけど、ほんまに困ったときに頼りにならんタイプやん。大阪のおばちゃんでも、もっと筋通すで、ほんま!
- 前ページ
- 次ページ
2024年の読書メーター
読んだ本の数:48
読んだページ数:14832
ナイス数:427
 ツミデミックの感想
ツミデミックの感想
短編集で、どれもたいへんよく書けているのだが、どうも刺さるものがあまりない、という正直な感想です。すみません。
読了日:12月29日 著者:一穂 ミチ
 黄色い家の感想
黄色い家の感想
人はだれしも少しずつ常軌を逸しているのだから、これは誰にとってもありえたストーリーなのだろう。全員、頭おかしい。知識が決定的に欠如していれば、児童相談所も動きようがないか。
読了日:12月25日 著者:川上未映子
 「むなしさ」の味わい方 (岩波新書 新赤版 2002)の感想
「むなしさ」の味わい方 (岩波新書 新赤版 2002)の感想
むなしさは常にそこにありどうしようもない、ということだけが書いてある本だな。いろいろ学問的なことも書いてあるがほぼこじつけに感じるし、結局加藤の自死を防げなかった北山の愚痴のようにも聞こえる。まぁ、読み終わってこんなにむなしい本もなかなかない。
読了日:12月13日 著者:きたやま おさむ
 三体3 死神永生 下 (ハヤカワ文庫SF)の感想
三体3 死神永生 下 (ハヤカワ文庫SF)の感想
いやー、長い旅でございました。ちょっとIIIは惰性で読んでしまった感があるけれど、あそこまでやられたら感服するしかない。SF的アイデアは疑問がめちゃめちゃあるが、ファンタジーということでいいことにする。長い旅でした。劉先生お疲れさまでした。
読了日:12月06日 著者:劉 慈欣
 百鬼園先生言行録 (福武文庫 う 103)の感想
百鬼園先生言行録 (福武文庫 う 103)の感想
再々読くらいだろうか。随筆というべきなのか、しかし相当部分フィクションのような気もする。全体に面白いのだが、「七体百鬼園」はノリの悪かったジャズのアドリブのようでどうも未消化である。
読了日:11月30日 著者:内田 百けん
 日本教について―あるユダヤ人への手紙の感想
日本教について―あるユダヤ人への手紙の感想
再々読くらいであるが、この示唆に満ちた隅から隅まで面白い本が、古書でしか手に入らないというのは残念なことである。だれかこの本の内容をもっと新しい事案に適用しなおして書き直してくれないだろうか。令和になっても「日本教」は健在だし、ベンダサンさんのロジックは充分に通用するものだとおもうのだが。何度も読んでいると以前ピンとこなかったことがわかるようになってくる。今でも日本人は空体語を積み重ね、踏み絵で相手を判断し、「お前のお前」の関係を希求し、そして「人間」と「自然」に絶対的な価値を置いている。
読了日:10月27日 著者:山本七平,イザヤ・ベンダサン
 三体2 黒暗森林 下 (ハヤカワ文庫SF)の感想
三体2 黒暗森林 下 (ハヤカワ文庫SF)の感想
気宇壮大なすごいSFだと思うのだけれど、こちらの知識が追い付かないので、どうも落ち着かない。智子のアイデアだが、11次元を2次元に展開するというような超絶な技術があってしかも量子もつれを利用して瞬時の通信ができるという段階でどう考えても勝負あったという気がする。何らかの方法で、例ですけどね、たとえば全地球上の原子力発電所を核爆発させるとか、核ミサイルを暴発させるとか、大船団を何百年もかけて送らなくても地球文明を滅ぼすことなんか簡単にできそうだと思いますが、その辺は整合性があるのかなぁ。
読了日:10月23日 著者:劉 慈欣
 三体 (ハヤカワ文庫SF)の感想
三体 (ハヤカワ文庫SF)の感想
評判に背かぬ大作。次から次へとよくまあこんなことを思いつくものだというアイデアの奔流、イマジネーションの爆発の連続。面白かったけれど、ハードSFと呼ぶには若干のためらいがある。ハードとハチャハチャ(横田順彌)の間を行くというか…。我々の知るセンスオブワンダーとは少々異なるものだという感を禁じ得ない。
読了日:09月17日 著者:劉 慈欣
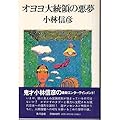 オヨヨ大統領の悪夢の感想
オヨヨ大統領の悪夢の感想
おそらく60余年の読書歴でもっとも面白く何度も読んだ本の一冊。特に「不眠戦争」のノリがよく、風化しつつある第二次世界大戦とマスコミの関係の風刺も効いている。手に入りにくいのは惜しい。
読了日:09月14日 著者:小林信彦
 御馳走帖 (中公文庫 う 9-4)の感想
御馳走帖 (中公文庫 う 9-4)の感想
昔読んで面白いと思ったが、あらためて読み返してみると、単なる偏屈爺の与太話であることが明白となってしまった。たいしたことは書いてない。ほとんど食い物の話で、大事件が起きるわけでもない。それをなんとか読ませてしまうのが百閒先生の文豪たる所以でもあろう。
読了日:09月14日 著者:内田 百けん
 土神ときつねの感想
土神ときつねの感想
樺の木と土神ときつねの三角関係なのだが、それぞれに事情があるところがミソである。土神の方にシンパシーを感じるが、きつねにはきつねの事情があるであろう。樺の木も三角関係をまとめるには経験不足であった。
読了日:09月08日 著者:宮沢 賢治
 あの子とQの感想
あの子とQの感想
ファンタジーだから理屈に合わないことがあってもかまわない。かまわないのだが、その世界観の中でなんとか筋が通るというかルールに従っていて納得感がないとファンタジーは成り立たない。この小説に関しては前半と後半が複雑骨折を起こしており、結末も本当に無理矢理だと感じる。あまり好きになれない。
読了日:09月07日 著者:万城目 学
 深夜特急1 ー 香港・マカオ〈文字拡大増補新版〉 (新潮文庫)の感想
深夜特急1 ー 香港・マカオ〈文字拡大増補新版〉 (新潮文庫)の感想
題名との関連がよくわからないが、要は香港の話ですな。ただの旅行記・紀行文に見せかけて実はタネもネタもありありの小説になっているあたりがミソですね。名作。懐かしい香港・マカオが彷彿とします。
読了日:09月04日 著者:沢木 耕太郎
 存在のすべてをの感想
存在のすべてをの感想
キンドルのサンプル部分が面白かったので購入したのだが、少し進んだところで全体の構図は明らかになってしまう。美術ひいては芸術の話や、親子の関係性の話に持っていきたいのだろうが、実に都合のいい協力者が次々現れるとか、ご都合過ぎませんか。本来サスペンスじゃないんだろうな。ちょっと損しました。
読了日:08月31日 著者:塩田 武士
 猫を抱いて象と泳ぐ (文春文庫 お 17-3)の感想
猫を抱いて象と泳ぐ (文春文庫 お 17-3)の感想
受け取り方はひとそれぞれだろうが、私には後味の悪い小説だった。
読了日:08月27日 著者:小川 洋子
 無理難題が多すぎる (文春文庫 つ 11-23)の感想
無理難題が多すぎる (文春文庫 つ 11-23)の感想
哲学者にしか書けない本である。読みながら池田晶子さんの著作を思い出した。月とスッポンではあるが(もちろん土屋氏の本の方がスッポンである)思わず爆笑してしまったところもあるが、あまり役に立つという本ではない。もちろん読書に「役に立つ」ことは求めていないが。
読了日:08月24日 著者:土屋 賢二
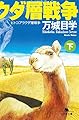 ヒトコブラクダ層戦争(下) (幻冬舎文庫)の感想
ヒトコブラクダ層戦争(下) (幻冬舎文庫)の感想
面白いのは面白いのだが、文章がくどい。何度も同じことを読まされる(連載だったのかな)。伊坂幸太郎さんの流れるようなアクションシーンにならされているといかにもぎくしゃくする。Audibleで聴いたので一層そう感じたのかもしれんないが、もう少し流麗に描いていただきたい。
読了日:08月20日 著者:万城目学
 プラスティック (講談社文庫 い 72-4)の感想
プラスティック (講談社文庫 い 72-4)の感想
以前、図書館で借りて読んだのだが、本屋大賞の発掘本に選ばれていたので再読した。仕掛けはわかっているのだが、それでも面白い。作者が、アイデアに忠実に小ぶりではあるが堅牢な構造物を作ろうと丹精しているのがわかる。フロッピーディスクが主人公(?)であるあたり時代を感じさせるが、それは全く気にならない。不朽の名作と言ってよい。
読了日:08月19日 著者:井上 夢人
 プロジェクト・ヘイル・メアリー 下の感想
プロジェクト・ヘイル・メアリー 下の感想
物理の得意な人には面白いだろうと思われるかなりのハードSFである。小説としては工夫は凝らされているとは思うが、だいたい読者の予想の範囲内でストーリーは展開していく。もっとも、手に汗握るハラハラドキドキなんてぇのは若い人の特権かもしれない。よくできたハードSFというところ。常識を覆すような奇想に満ちているという小説ではない。
読了日:08月15日 著者:アンディ・ウィアー
 数学ガール/ゲーデルの不完全性定理の感想
数学ガール/ゲーデルの不完全性定理の感想
わからなかった、というか、わかろうとする気力が途中で萎えた。でも面白かった。不完全性定理の「薫り」くらいは感じることができた。46の定義の解説お疲れ様でした>結城先生
読了日:08月04日 著者:結城 浩
 新 もういちど読む 山川世界史の感想
新 もういちど読む 山川世界史の感想
この辺で第二次大戦で終わってしまうのではないもう少し先まである世界史を読みたくなって購入。歴史の概観としてはいいのだが、もう少し「なぜそうなったか」についてところどころでも解説が欲しい。なぜ日本は対英米開戦したのかとか。ないものねだりかもしれないが。一応プーチンが大統領の2期目をやってるとか9.11とかトランプの名前は出てくる。残念ながらウクライナ戦争、ハマス/イスラエルには触れられていない。
読了日:08月02日 著者:
 AX アックス (角川文庫)の感想
AX アックス (角川文庫)の感想
Audibleにて。これは再読だと思う。だいたいストーリーは覚えていた。恐妻家の殺し屋という設定で全編もたせるという力業。面白かったし身につまされる。
読了日:07月18日 著者:伊坂 幸太郎
 マリアビートル (角川文庫)の感想
マリアビートル (角川文庫)の感想
Audibleにて。殺伐とした話でありながら、ところどころで笑いを誘うのが伊坂さんのストーリーテリング。それぞれのキャラクターが立っているのがすごい。
読了日:07月18日 著者:伊坂 幸太郎
 時間のパラドックス―哲学と科学の間 (中公新書 (575))の感想
時間のパラドックス―哲学と科学の間 (中公新書 (575))の感想
30年前にもわけのわからない本だと思ったが、再読してもわからないことは変わらなかった。内容のうち半分は自明のことだと思うし、残り半分は全く理解できない。ゼノンの矢は的まで飛ぶし、アキレスは亀に追いつく。
読了日:07月05日 著者:中村 秀吉
 猫を処方いたします。 (PHP文芸文庫)の感想
猫を処方いたします。 (PHP文芸文庫)の感想
Audibleで読んだ(聞いた)のだが、なんとも不思議なほんわかした世界である。実はその根源には目をそむけたくなる事態が伏在しているのだが…
読了日:06月26日 著者:石田 祥
 成瀬は天下を取りにいく 「成瀬」シリーズの感想
成瀬は天下を取りにいく 「成瀬」シリーズの感想
「成瀬」のキャラクターがすごい。何も超自然なことも起きないし、複雑な謎があるわけではないのだが、ついつい物語に引き込まれていく。本屋大賞おそるべし。オーディブルで聴いたのだが、朗読の域を超えた「演技」にも賞賛を送りたい。
読了日:06月10日 著者:宮島未奈
 ぼくの大好きな青髭 (中公文庫)の感想
ぼくの大好きな青髭 (中公文庫)の感想
1969年、アポロ11号の年。このシリーズの中ではもっともメタファーだらけで、まるで村上春樹を読むようだが、この時代の熱気、若者たちの行き場のないエネルギーと新宿の空気を思い出させる。実は、赤、白、黒までは読んでいたのだが、どういうわけか完結編であるこの青髭を読んでおらず、この度1977年から50年近い年月を経てやっと読み終えました。
読了日:06月03日 著者:庄司薫
 日本の仏教 (岩波新書 青版 299)の感想
日本の仏教 (岩波新書 青版 299)の感想
30年前に読んだ本を再読。こんな過激な本だったっけという印象。法然、親鸞、日蓮、3人まとめて「口先だけ」とバッサリ。天台宗にしても「無智と誤解の上に成り立っている」とこれもバッサリ。要するに実践の伴わない仏教は仏教にあらずという立場で、相当過激な論を展開していて、大変面白かった。
読了日:06月02日 著者:渡辺 照宏
 ビブリア古書堂の事件手帖IV ~扉子たちと継がれる道~ (メディアワークス文庫)の感想
ビブリア古書堂の事件手帖IV ~扉子たちと継がれる道~ (メディアワークス文庫)の感想
ああややこしい。もちろん、こちらの頭も老化しているからその分もあるだろうが、同じようなキャラクターが3代おりその配偶者がおり、同様に3代続く登場人物が複数おり、頭の中がこんがらかるのである。一応の区切りはついたようだが、三上先生、まだ書くのだろうな。
読了日:05月28日 著者:三上 延
 ビブリア古書堂の事件手帖III ~扉子と虚ろな夢~ ビブリア古書堂の事件手帖 ~扉子と不思議な客人たち~ (メディアワークス文庫)の感想
ビブリア古書堂の事件手帖III ~扉子と虚ろな夢~ ビブリア古書堂の事件手帖 ~扉子と不思議な客人たち~ (メディアワークス文庫)の感想
登場人物の行動が回りくどい。語り口もまわりくどい。推理小説は、手掛かりを淡々と追っていって、最後に「そこで探偵さてといい」でいいのだ。くどい。まぁ、ここまでつきあったから最終巻も読むけど。とにかくまわりくどいんだよ。
読了日:05月17日 著者:三上 延
 ビブリア古書堂の事件手帖II ~扉子と空白の時~ (メディアワークス文庫)の感想
ビブリア古書堂の事件手帖II ~扉子と空白の時~ (メディアワークス文庫)の感想
横溝正史ってあまり好きではないんですよ。筋立てが無理矢理…俳句どおりに殺人とか…ないわー。この本は面白かったけれど。
読了日:05月11日 著者:三上 延
 ビブリア古書堂の事件手帖 ~扉子と不思議な客人たち~ (メディアワークス文庫)の感想
ビブリア古書堂の事件手帖 ~扉子と不思議な客人たち~ (メディアワークス文庫)の感想
このシリーズは面白いのだけれど、混乱するからはっきり通しで番号を振るとか、シリーズ名を変えるとかしてほしい。掌編4つのうち、最後の一編が一番面白かった。
読了日:05月08日 著者:三上 延
 ビブリア古書堂の事件手帖7 ~栞子さんと果てない舞台~ (メディアワークス文庫)の感想
ビブリア古書堂の事件手帖7 ~栞子さんと果てない舞台~ (メディアワークス文庫)の感想
やれやれやっと完結しましたな。最後はそれほど驚くほどの大展開はなく終わりましたな。作品としてはシリーズ前半の方がノリがよかったような印象があります。
読了日:05月04日 著者:三上 延
 ビブリア古書堂の事件手帖6 ~栞子さんと巡るさだめ~ (メディアワークス文庫)の感想
ビブリア古書堂の事件手帖6 ~栞子さんと巡るさだめ~ (メディアワークス文庫)の感想
なんだか人間関係がごたごたと複雑になってきましたね。一度、関係図を示してもらわないと、老人にはきついです。まぁ、7巻も読みますけどね。
読了日:04月27日 著者:三上 延
 噺歌集II (文春文庫)の感想
噺歌集II (文春文庫)の感想
基本的には噺歌集と同じ情報が多いかな。二度も読む本じゃないね(読んだけど)あとがきで、ご本人が「おれは暗くない」と叫んでおられる。いいのにね、そんなこと気にしなくても。いや、気にしないと書いておられるのだが、その実相当気にしているね、これは(笑)
読了日:04月20日 著者:さだ まさし
 文章読本 改版 (中公文庫 み 9-7)の感想
文章読本 改版 (中公文庫 み 9-7)の感想
私にはやや難しいのだが、それでも面白く読んだ。書籍は偉大である。すぐそこに三島自身が立って文学を語ってくれるのだから。確かに鴎外の「澁江抽斎」の系図を読み下すような退屈な部分に挟まれた逸話は実に生き生きとしているし、鏡花の筆の力はすさまじいものがある。三島が漱石と露伴をどう評価していたのかが知りたいところである。
読了日:04月17日 著者:三島 由紀夫
 ビブリア古書堂の事件手帖5 ~栞子さんと繋がりの時~ (メディアワークス文庫)の感想
ビブリア古書堂の事件手帖5 ~栞子さんと繋がりの時~ (メディアワークス文庫)の感想
参考文献リストを見て戦慄する。これだけ調べて書いていて、失礼な話だがもとはとれるのだろうか。人気シリーズだから大丈夫なんだろうな。改めて読んでその蘊蓄のすごさに圧倒される。寺山修司はよくわからないのだけど…
読了日:04月15日 著者:三上 延
 福家警部補の考察 (創元クライム・クラブ)の感想
福家警部補の考察 (創元クライム・クラブ)の感想
殺人をしようというのだから、何かしらのっぴきならない理由があるのだ。ただ、それが自業自得の事情ではなく、犯人側にもそれなりの理由があり、尊敬すべき面も備えているというのが、本歌取りの本家にも通ずる特徴であろう。特に最後の一話は、その設定が実によくできている。恐れ入りました。
読了日:03月27日 著者:大倉 崇裕
 福家警部補の追及 (創元推理文庫)の感想
福家警部補の追及 (創元推理文庫)の感想
福家警部補はいいキャラクターだったのだけれど、運動全般オールマイティーってのはちょっとやりすぎじゃないかなぁ。もう少し、弱みがあった方がキャラクターとして好感が持てるんですけど。
読了日:03月20日 著者:大倉 崇裕
 福家警部補の報告 (創元推理文庫)の感想
福家警部補の報告 (創元推理文庫)の感想
3編収録されているが、「少女の沈黙」は特に傑作。ヤクザの描写が秀逸だと思う。大変面白く読んだ。
読了日:03月12日 著者:大倉 崇裕
 にっぽんの商人の感想
にっぽんの商人の感想
「日本人は虚構を虚構として尊重する」「日本が世界に誇れるのは『商事』だけ。軍事も政治も思想もなく、国会は麻痺している」1978年の主張は今でも通用するが、『商事』=経済力にも陰りが出ること久しく、日本は本当に沈没してしまった。各章の結論部分がどれもあっさりしていて、理解するのに少々骨が折れるが、一冊を通しての主張は明快で、江戸時代以来、日本は本当に変わらないということを証明している。読み継がれるべき本だと思うのだが、もう古書でしか手に入らないようだ。
読了日:03月09日 著者:山本七平,イザヤ・ベンダサン
 福家警部補の再訪 (創元推理文庫)の感想
福家警部補の再訪 (創元推理文庫)の感想
ベースに「刑事コロンボ」という大発明があるとはいえ、福家警部補の人物造形は秀逸だと思う。紺色の野暮ったいスーツを着たフチなしメガネの小柄な若い女性の警部補が出てくるだけでうれしくなる。どうしても見つからなくなる警察手帳をついに首から下げることになってしまったのもおかしい。
読了日:03月07日 著者:大倉 崇裕
 ぬいぐるみ警部の帰還 (創元推理文庫)の感想
ぬいぐるみ警部の帰還 (創元推理文庫)の感想
今一つのり切れないのは、主人公の造形がそれほど「のっぴきならない」ところまで煮詰められていないからかなぁ。
読了日:02月16日 著者:西澤 保彦
 パッとしない子 (Kindle Single)の感想
パッとしない子 (Kindle Single)の感想
つかこうへいじゃないけど「傷つくことだけ上手になって」。逆恨みによる、権力をかさに着た言葉の暴力以外の何物でもないですよ。
読了日:02月10日 著者:辻村 深月
 怪しい店 (角川文庫)の感想
怪しい店 (角川文庫)の感想
軽い推理小説を5編。楽しく読ませていただきました。「潮騒理髪店」がよかった。
読了日:02月08日 著者:有栖川 有栖
 文芸の哲学的基礎の感想
文芸の哲学的基礎の感想
読了しました。流石漱石、読んで(おそらくは聞いても)面白い文章になっています。いろいろの例示を添えているのがわかりやすくなっている所以かと思います。 まずは「意識は連続を欲す」という哲学的考察から説き起こして、結論としては「文芸は理想をもたざれば意味なし」ということなのかと思います。
読了日:02月08日 著者:夏目漱石
 日本世間噺大系 (新潮文庫)の感想
日本世間噺大系 (新潮文庫)の感想
これも読むのは3回目くらいかな。時代は変わったけれども面白いのは変わらない。何かのテレビ番組でみたけれど、伊丹さんはインタヴューのテープを大量に録りためてあったらしいですな。その中からこれは面白いというものを選んで文章に起こしたのだろうから面白いのは当然といえば当然かもしれない。
読了日:01月18日 著者:伊丹 十三
 噺歌集 (文春文庫)の感想
噺歌集 (文春文庫)の感想
読むのは二度目くらいだと思うが、この時代とさだまさしさんの古い価値観が感じられて面白い。私が就職して住むことになった、大阪の会社の寮の近くの本屋さんのカバーがまだついており、それを亡父に貸したらしく、父の筆跡でカバーの背に書名が書いてあるという珍品である。昭和57年4月の単行本を文庫(昭和61年)になってから買ったようだ。
読了日:01月10日 著者:さだ まさし
読書メーター
ラジオからの文字起こしです。
===========
(森本毅郎)
皆さんのメールを紹介しますが、今日は34年前の前回のバブル景気を経験したことありますか。今と何が違うんでしょうか、と伺いましたところ、バブルを経験したよっていう方のメールが来ましたが、改めてすごいなと思いますね。
江戸川区、62歳の男性、34年前のバブル景気の時29歳でした大いに満喫しました。
当時貿易の仕事をしていました。都内で仕事をしていた時は普段行くことのできないようなクラブで接待され、国内出張ではドンチャンさわぎ、海外赴任では毎日のように日本から出張者が来て接待、本社からはいくらお金使ってもいいと言われお酒は浴びるほど飲みました。その時の羽目を外した生活がたたって、今はお酒の飲めない体になってしまいました。
34年前は給料はいいつまでも右肩上がりが続くと思っていましたが、今の給料はいつまでも上がり続けることとは思えず夢も持てなくなりました。
中央区、69歳の女性。経験しましたよ。35歳、仕事も遊びも全力投球という時代でした。私、部長秘書と部内庶務をしていましたけれども男性社員が会社に要求するとタクシー券をほとんど何も言わずに出していました。(こういういう時代だったね)
庶務室で出す備品請求も大体通りました。当時私が所属している部は、ある大きな賞を受賞しまして受賞記念のパーティーはパレスホテルで来賓へのお土産は2万円のお仕立券つきワイシャツ、来賓一人に1台のハイヤーを手配。それを秘書室は全部認めてくれました。次の年バブルがはじけました。次の年同じ賞を受賞した隣の部の受賞記念パーティーの会場は役員食堂になりました。女子社員は接待費は使えなかったけれどもおこぼれのあったそんなバブルの時代でした。(遠藤:すごい落差)
横浜市81歳の男性。34年前のバブル時代、会社で海外担当をしておりました。たっぷり恩恵を受けましたね。当時50歳前後でしたが、日本の評判は高く、欧米や東南アジアなどの地球規模で出張しました。特に欧米の業界の会議がある時などは保養地に日本の顧客を案内しながら食事会や名所めぐりなどを楽しみ親密な関係を築きました。
もちろん日本からの移動はビジネスクラスでした。
また、国内でも給与が毎年2、3割上がってボーナスもそれなりに増えたので住宅ローンの繰り上げ返済をして定年時にはローンがほとんどなかったのでその後の生活は助かりました。(すごいよな)(遠藤:夢のよう)
埼玉県越谷市の36歳の男性。父が当時旅行代理店から電気メーカーへ転職しました。
都内の事務所に務め出してからすぐにパリの事務所へ転勤になって、私たち家族も5年以上暮らしました。しかし帰国後の2000年代に入ってからはリストラされその後転々と職場を変えた父は旅行代理店時代は良かったなと嘆いていました。
(うーん、だからねぇ、バブル前とね、その後との落差が激しいんだよな)
埼玉県春日部市60歳の男性。バブル時代は証券会社の店頭に株価ボードがあって人が集まっていました。当時クリスマスイブになると多くの人がプレゼントの入った紙袋を持っていましたよ。今のクリスマスイブ、そんな姿ほとんど見られません。駅前にはクリスマスケーキを売る臨時の店がいくつかありました。いくつもありましたが、今は全く見かけなくなりました。
埼玉県本庄市47歳の男性。今にして思えば父親のつとめていた会社の社員旅行や忘年会に家族全員が招かれていたのはバブルの高景気の恩恵だったんですね。宿泊したホテルも豪華でロビーにメリーゴーランドがあるような、すごいところだったのを幼心に覚えています。
国立市58歳の男性。34年前金融機関につとめていました。朝7時出勤、帰り23時すぎのセブン―イレブン生活でした。また週休2日ではありませんでしたが、隔週の土曜日が休みから、週休2日になった思い出があります。お金たくさんもらいましたが、使うヒマもありませんでした。
大田区59歳の男性。まだ22歳で若造とか坊やとか呼ばれてこまづかいでしたけれども、おこぼれだけで十分ご飯をいただけました。夜の街で1万円札をビラビラさせてタクシーを掴まえ、上司から貰ったお礼のチップが1万円。年3回あった定期昇給、ボーナスの社員旅行は韓国やフィリピンでした。
長野県66歳の男性。当時丸の内勤務で32歳。毎日昼休みに日興証券のボードを見ていました。あの大暴落の日も唖然として口を開けてみていた姿が当日のニュースに流れ、翌日上司からお前何を見に行ったんだと揶揄われたことを思い出します。今回の株高は円安による割安感と中国市場から日本市場への資金の流れによるのが主要要因で日本の実態経済はよくないと思いますよ。
八王子市72歳の男性。当時30代後半でバブル真っただ中でした。一部上場の会社に勤務していました。私の部署は残業で23時を超えたら一人1台、ハイヤーでの帰宅が普通でした。30人ほどの部署で1ヶ月のハイヤー代は約1千万円と聞いていました。途中バーに立ち寄ってハイヤーを外に待たせていたこともあります。おそらく現在は遅くなっても電車で帰宅でしょう30代で銀座に繰り出すなんて不可能ですよね。(もう聞いてるひといたら頭来ちゃうよね)
神奈川県55歳の男性。バブル時代に学生生活を送り就職活動が超売り手市場でした。地方出身者は今日は実家から来ましたというと企業は実家がどこであろうと往復の交通費を出してくれました。面接もセミナーという名のイベントでホテルの立食パーティーで結構な賞品があたるビンゴ大会もあったりしました。そして解禁日にとてもラジオでは言えないような接待を受けた友人もいました。私が就職した会社は内定日と解禁日に簡単なパーティーがあったくらいでしたが、それでも面接の度にテレカや会社のノベルティーをもらった記憶があります。
新宿区65歳の男性。今65歳の私ですがTBSラジオとは1970年の遠藤泰子さんのパックインミュージックからのお付き合いです。そんな中信じられないリスナープレゼントになったのがバブル期、テレビ・レコーダーはあたり前海外旅行もホンダの乗用車もありましたよ。ぜひこの番組でも豪華なリスナープレゼントをお願いいたします。
(ってとても無理だよ。何言ってんだ)
(なんだか、バブルの頃が羨ましいような気分になってきちゃって良くないね。良くないよ。)
埼玉県56歳の男性。就職したてでしたけれども預貯金の金利がまったく違う感じでしたよ。当時4%以上あったと思いますよ。仕事しないで利息で食ってるって話よく聞きました。
親から貯金しておくようにとよく言われたものです。
(そういう時代でしたけどね、もうこれは二度とこないんじゃないかな?こんな時代はね。何か妙に現実感のない思い出話になってしまいましたね。)
(また来週。)
2023年の読書メーター
読んだ本の数:56
読んだページ数:18016
ナイス数:358
 現代詩の鑑賞 (下) (新潮文庫)の感想
現代詩の鑑賞 (下) (新潮文庫)の感想
古い本なのだけれど、読み返すと味わいが。扱われている詩人は、賢治、喜八、光晴、達治、重治、心平、冬彦、中也、道造、順三郎。この中では、北川冬彦をもう一度読んでみたいと思う。検温器と花とか。長生きされたのでまだ青空文庫には収録なし。
読了日:12月10日 著者:伊藤 信吉
 日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのかの感想
日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのかの感想
再読だが、日本の三権<天皇<米国(米軍)という図式を明確に記述した良書だと思う。一つだけ意見が違うのは、現行憲法は確かに天皇制の部分など手直しが必要だと思う(できれば廃止すべき)が、作り手が誰だったかは関係なく、その骨組みはきちんと守るべきだと思う点である。
読了日:12月09日 著者:矢部 宏治
 さだのはなし ~さだまさしステージトーク集~の感想
さだのはなし ~さだまさしステージトーク集~の感想
軽い話は面白いのだが、どうも説教臭いのはいけないね。それと、「女は家庭を守るもの」という信条が抜きがたくありますな、この人は。
読了日:11月01日 著者:さだ まさし
 ストレイヤーズ・クロニクル ACT-1 (集英社文庫)の感想
ストレイヤーズ・クロニクル ACT-1 (集英社文庫)の感想
ほかならぬ本多さんで、道具立てもいいと思うのになぜ面白くないのか。登場人物が多すぎてこちらの頭がついていかないのだな。三井というキャラクターはちょっと面白かった。
読了日:10月12日 著者:本多 孝好
 煤煙 (岩波文庫)の感想
煤煙 (岩波文庫)の感想
漱石の「それから」に「門野は茶の間で、胡坐をかいて新聞を読んでいたが、髪を濡らして湯殿から帰って来る代助を見るや否や、急に坐三昧を直して、新聞を畳んで坐蒲団の傍へ押し遣りながら、「どうも『煤烟』は大変な事になりましたな」と大きな声で云った。」という」というくだりがあり、一度読んでみたいと思っていた。心中事件といいながら男女とも大変観念的で、到底同情できない。むしろ同事件を平塚明(はる、らいてう)側から描いたものを読んでみたい。
読了日:10月08日 著者:森田 草平
 MEMORY (集英社文庫)の感想
MEMORY (集英社文庫)の感想
MOMENT、WILLの二作の間を埋めるように、落穂拾いのように、短編を紡いでいく。丁寧な仕事だと思う。面白かった。
読了日:10月02日 著者:本多 孝好
 WILL (集英社文庫)の感想
WILL (集英社文庫)の感想
主人公(クールな29歳の女性なのだが)を映像化するのに誰がいいか、迷う(迷ったってしょうがないのだが)相手役は高橋一生かなぁ。
読了日:09月18日 著者:本多 孝好
 MOMENT (集英社文庫)の感想
MOMENT (集英社文庫)の感想
面白い連作短編集だが、最後の話は少々弱くないかい?
読了日:09月18日 著者:本多 孝好
 MISSING (角川文庫)の感想
MISSING (角川文庫)の感想
これは当たりだった。特に「瑠璃」がよかった。誤解を招く言い方かもしれないが、絶好調のムラカミハルキみたいな調子で実に快調である。
読了日:09月11日 著者:本多 孝好
 dele3 (角川文庫)の感想
dele3 (角川文庫)の感想
deleのおかげで小説を読む楽しみが帰ってきました。ここのところ、昔読んだものを読み返す程度で、ほとんどフィクションにはご無沙汰しておりました。話はややとっちらかった感があるけれど、堂本ナナミというキャラクターが魅力的です。タマさんもだけど。
読了日:09月06日 著者:本多 孝好
 星条旗と青春と―対談:ぼくらの個人史 (角川文庫 (5931))の感想
星条旗と青春と―対談:ぼくらの個人史 (角川文庫 (5931))の感想
1940年代から1970年代までの日本を俯瞰する、小林信彦さんと片岡義男さんの対談集である。私がものごころついたのは速くて昭和37年(1962年)くらいなので、それまでの、特に敗戦後の出来事のクロノロジカルな回想は大変興味深い。確かに、われわれは米国文化にambivalentな感情を抱いている。それはいまも変わらないと思われる。
読了日:09月02日 著者:小林 信彦,片岡 義男
 dele2 (角川文庫)の感想
dele2 (角川文庫)の感想
deleはテレビドラマでみて大変面白かったので、小説も読んでみた。テレビドラマの印象が強いのでどうしても役者さんのイメージが浮かんでしまうが、小説としても大変よくできており面白い。
読了日:09月01日 著者:本多 孝好
 ラブカは静かに弓を持つの感想
ラブカは静かに弓を持つの感想
JASRAC VS ヤマハ音楽教室の実際の訴訟を題材にした「スパイ小説」弟子がスパイかどうかという切り口と、実際の師弟関係というのは次元の違うことのような気もする。主人公はそんなに悪いことをしたのか。
読了日:08月18日 著者:安壇 美緒
 白夜行 (集英社文庫)の感想
白夜行 (集英社文庫)の感想
再読。前回と同じく、背景の時代性を描き出すという意味ではあまり成功しているとは言えないが、前回より(結末を知っていても)味わって読めたかもしれない。
読了日:08月16日 著者:東野 圭吾
 ダイイング・アイ (光文社文庫 ひ 6-11)の感想
ダイイング・アイ (光文社文庫 ひ 6-11)の感想
東野作品にしては少々ストーリーに無理があるかなぁ。サービスに走りすぎた感がある。
読了日:08月07日 著者:東野 圭吾
 流星の絆 (講談社文庫)の感想
流星の絆 (講談社文庫)の感想
登場人物たちの主な連絡手段は携帯というあたりに時代を感じる。手練れの東野作品だけに、最初に重い話を置いても、あとは軽快に飛ばしていき、最後にすべての伏線がきれいに回収されるのは読んでいて爽快感がある。エンターテインメントとして大変よくできていると思います。
読了日:08月01日 著者:東野 圭吾
 木挽町のあだ討ちの感想
木挽町のあだ討ちの感想
なんかメジャーなものを詠んでしまった。時代物というのは背景事情を理解するのに手間取るし、時代に溶け込めないので苦手なのだが、この小説に限ってはそのあたりの処理がとてもうまく、すんなり読み進めることができた。面白かった。
読了日:07月24日 著者:永井 紗耶子
 現代詩の鑑賞 上 (新潮文庫 い 8-1)の感想
現代詩の鑑賞 上 (新潮文庫 い 8-1)の感想
昭和27年の本だから71年前ということになる。はるかに現代詩とは呼べないものを扱っているが、今読んでも面白かった。取り上げられているのは藤村・有明・白秋・露風・啄木・光太郎・暮鳥・犀星・朔太郎・元麿・春夫の11人。
読了日:07月16日 著者:伊藤 信吉
 半七捕物帳〈1〉 (光文社時代小説文庫)の感想
半七捕物帳〈1〉 (光文社時代小説文庫)の感想
青空文庫にいっぱいあるのでたまにちょっとずつ読んでいる。他愛ない話も多いのだが、ちょっとひねった面白いものもある。
読了日:07月12日 著者:岡本 綺堂
 定本 バブリング創世記 (徳間文庫)の感想
定本 バブリング創世記 (徳間文庫)の感想
久しぶりに筒井康隆さんを読んだ。表題作はさすがに途中で読み飛ばしてしまったが、所謂ドタバタSF「ヒノマル酒場」が面白かったし、「三人娘」は長年中間管理職をやった経験を踏まえて読むとこれは身につまされるものがある。盛り上げていく手法がすごいのだが、これは巧んでそうしたというより、天性のものなのだろうな。舞台は昭和、それも表計算ソフト以前だろうが、非常にリアルに感じた。1978年(昭和53年)作品だから45年前だが、古くなってない。
読了日:07月08日 著者:筒井康隆
 吾輩は猫である (角川文庫)の感想
吾輩は猫である (角川文庫)の感想
何度読んだかわからない。何度読んでも面白い。漱石はまるで明治時代から令和の世の中を見通していたようにすら感じる。
読了日:07月06日 著者:夏目 漱石
 漾虚集・夢十夜 (漱石作品論集成)の感想
漾虚集・夢十夜 (漱石作品論集成)の感想
倫敦塔・カーライル博物館・幻影の盾・琴のそら音・一夜 ・薤露行・趣味の遺伝のうち、青空文庫で読めない幻影の盾を除いたものを読んだ。但し、薤露行については文語文に抵抗があって読めていない。漱石の創作の原点におけるあれやこれやの試行錯誤を見るようで大変興味深い。
読了日:06月19日 著者:
 九十八歳。戦いやまず日は暮れずの感想
九十八歳。戦いやまず日は暮れずの感想
98歳で、これだけの文章が綴れるということにまず驚く。論旨明解、首尾一貫、笑いまでとりにくる。分量に比して価格が高い気はするが、98歳じゃあしょうがないかと納得する。「寂寥」の二字が胸に迫る。
読了日:06月11日 著者:佐藤 愛子
 増補版 九十歳。何がめでたい (小学館文庫 さ 38-1)の感想
増補版 九十歳。何がめでたい (小学館文庫 さ 38-1)の感想
この本がすでに7年前。エッセイを頼まれるというのは、いいことですね。おそらくそれで書いている間は老いは影をひそめているのでしょう。私もこれに同感することが多い歳になったということか。
読了日:06月03日 著者:佐藤 愛子
 うわさ帖 (集英社文庫)の感想
うわさ帖 (集英社文庫)の感想
同じ新聞連載の「女帖」と違って、こちらはとりとめのない話が多いのだけれど、そこは文豪半村良、つぎつぎ読まされてしまう。復員してきた人がどこからかグローブとミットを手に入れて子どもにキャッチボールの相手をさせるなんて、いい話だな。戦後、野球はルールがきちんと決まっていて爽快だったというのもいい。それが例の騒動でジャイアンツがジャイアンツでなくなっちゃったというのもさみしい話だ。
読了日:05月28日 著者:半村良
 吉野葛の感想
吉野葛の感想
短いながらも谷崎の筆が冴える。昔の人は地図もなしに山道を行き、どうしようもないと案内人を雇ったのですね。
読了日:05月26日 著者:谷崎 潤一郎
 雨物語 (講談社文庫)の感想
雨物語 (講談社文庫)の感想
平成元年の雨の日の物語。あれから30年以上経ってるのだなぁ。おそらく昭和のバーというのは居心地のいい場所だったのだろうなぁと思わせる酒場がらみの作品のひとつ。
読了日:05月18日 著者:半村良
 忘れ傘 (集英社文庫)の感想
忘れ傘 (集英社文庫)の感想
例によって半村さんの酒場譚なのだが…結論は、結局女はわからない、ということでいいのだろうか?
読了日:05月16日 著者:半村良
 たそがれ酒場の感想
たそがれ酒場の感想
還暦になった、シリーズ主人公仙田の周辺を描いている。この時代、還暦は結構なトシということなのだろうな。新しい生きのいい登場人物を加えて楽しい読み物になっている。ところで京子はどこへ行ったんだ?
読了日:05月09日 著者:半村 良
 再び女たちよ! (新潮文庫)の感想
再び女たちよ! (新潮文庫)の感想
手元にあるのは1980年第9刷とある文春文庫版である。おそらくこれを私は20代前半に読んだのであろう。若い頃に読んだものというのは覚えているものですな。各章の最初を読んだだけでどんな話だったか思い出せる。それに引き換え、中年になってから読んだものはすっかり忘れているのだ。時代がたってあまりポリティカリーにはコレクトでないかもしれないけれど、面白いエッセイ集です。
読了日:05月07日 著者:伊丹 十三
 パノラマ島綺譚 江戸川乱歩ベストセレクション (6) (角川ホラー文庫)の感想
パノラマ島綺譚 江戸川乱歩ベストセレクション (6) (角川ホラー文庫)の感想
乱歩はすごいなぁ。イマジネーションとそれを書き込むエネルギー。しかし、破調である。整っていない。勢いはすごいのだけれど、結果主人公同様表現が破綻しているように思う。
読了日:04月25日 著者:江戸川 乱歩
 新宿馬鹿物語の感想
新宿馬鹿物語の感想
新宿馬鹿物語完結編。ハッピーエンドでよかったよかった。雑誌初出が昭和51年。確かにこの年は三の酉が11月29日であったことを確認。すぐ翌年に映画化されているのだが、主人公の仙田が愛川欽也さんでは私のイメージとはずいぶん違う。いや、映画を見ないで書いているのでわかりませんが。
読了日:04月12日 著者:半村良
 北村薫のミステリー館 (新潮文庫)の感想
北村薫のミステリー館 (新潮文庫)の感想
どうもピンとこない話が多いのだ。ぺダンティックで高踏的なのだ。「盗作の裏側」は面白かったが。あと、翻訳というのは読みにくいものだと改めて思った。最後の村上春樹訳はさすがに小説家だけあって読みやすいが、話がきらいだ。というか私は血に弱いのだ。奥泉光はこの作家にしては重すぎて到底最後まで読み通せない。
読了日:04月09日 著者:
 ながめせしまにの感想
ながめせしまにの感想
これをキンドルで読むことになろうとは思わなかった。全編、これ昭和の風景である。特に、なんということもない酔客2名を描いた「ふたり飲兵衛」が印象に残る。表題作をはじめ性描写がかなり濃厚で、これらと比べると「雨やどり」「おんな舞台」などのあっさりした表現の方に軍配を上げたい。
読了日:04月05日 著者:半村 良
 女帖の感想
女帖の感想
エッセイという形も、最初のうちはともかく、すぐ呼吸を掴んでしまう半村先生、いつもの見事な芸を見せてくれる。女たちの、いや人間のすぐれた52葉のスケッチブックである。
読了日:03月31日 著者:半村 良
 リセット (新潮文庫)の感想
リセット (新潮文庫)の感想
「スキップ」「ターン」と読んでいて息苦しくなるような作品のあとに「リセット」は悲劇的な背景があったとしても平常心で読める作品である。第一部は戦中、第二部は戦後を描く。第一部の「真澄」がほぼ母と同年代(学徒動員で飛行機工場に行ったりしている)、第二部の語り手である「村上君」は団塊の世代、私の6-7才上の設定で、物語中に描かれる世情に共感するものが多い。戦中のことは直接しらないが、「真澄」のような上流の人間にとっては戦争とは遠くで行われる心逸る出来事であったのだろうと感じさせてくれる。次は気をつけなければね。
読了日:03月20日 著者:北村 薫
 ターン (新潮文庫)の感想
ターン (新潮文庫)の感想
二人称で始まる珍しい形式でそれが物語の伏線にもなっている周到さ。「スキップ」にしてもそうだが、主人公は設定された異常事態にあまりに気丈に対峙するのが不自然に思えてしかたない。こういう人はいるんだろうか。私なら絶対精神に異常をきたしてしまうと思う。なお、文庫版の「付記」にある矛盾点については私も気になっていた。これをSFとみるのであれば、看過できない瑕といっていい。柿崎の生きている時間には「昨日の」午後3時15分からの5分間は含まれていないのだから、主人公が「戻ってくる」のを待ち伏せすることは不可能である。
読了日:03月17日 著者:北村 薫
 スキップ (新潮文庫)の感想
スキップ (新潮文庫)の感想
再読。設定が読んでいてもつらい。息苦しい。こんな事態になったら、精神に異常をきたしてもまったくおかしくないと思うのに、主人公は気丈である。気丈すぎるところに、むしろリアリティを感じられなかったり。昭和40年代と平成を描いてあますところがなく、ちりばめられるサブストーリーも見事なのは重々わかるが、読後感としてはしんどい。
読了日:03月13日 著者:北村 薫
 雨やどり (集英社文庫)の感想
雨やどり (集英社文庫)の感想
文春文庫で再読した。何度読んでもうならされる見事な芸だ。人情噺をしているようで、最初の話はなんとSFである。文春文庫はカバーが滝田ゆうさんの洒脱な絵である。主人公の仙田が半村さんの分身かと思っていると最終話では作家になった駒井が登場し、全体はひっくりかえってしまう。久保田万太郎が登場する「あとがき」まで含めて完全な舞台といっていい。
読了日:03月08日 著者:半村 良
 鷺と雪 (文春文庫)の感想
鷺と雪 (文春文庫)の感想
再読。この一冊に限らず、「街の灯」「玻璃の天」を含めた「ベッキーさんとわたし(花村英子)」のシリーズは傑作である。これも「円紫さんとわたし」のシリーズ同様、ヒロインのビルドゥングス・ロマンになっており、かつ五・一五事件から二・二六事件に至る昭和の決定的な一時期を見事に描いている。
読了日:03月06日 著者:北村 薫
 玻璃の天 (文春文庫)の感想
玻璃の天 (文春文庫)の感想
再読であるが、あらためて見事なものだと思った。昭和初期を背景にとり、貴族のお嬢様をヒロインにした本格推理小説でありながら、時代を描くことにあますところがない。
読了日:02月26日 著者:北村 薫
 覆面作家の夢の家 新装版 (角川文庫)の感想
覆面作家の夢の家 新装版 (角川文庫)の感想
3種類のそれぞれ違った趣向の謎解きを提示する本格推理であるが、とにかくこのヒロインを設定したのが作者のお手柄だと思う。なんで2編目が「目白を呼ぶ」なのかがいまだにわからない。
読了日:02月22日 著者:北村 薫
 覆面作家の愛の歌 新装版 (角川文庫)の感想
覆面作家の愛の歌 新装版 (角川文庫)の感想
ああややこしい。表題作の「愛の歌」のトリックは大変手が込んでいる。正直なところ3回読んで、自分で図を書いてみてやっとわかった(ような気がする)。
読了日:02月21日 著者:北村 薫
 おんな舞台の感想
おんな舞台の感想
見事な芸としかいいようがない。全く知らない世界が展開されるのだが、語り口のよさにつられて、昭和の女たちの世界を遊覧させてもらってしまう。解説を向田邦子さんが書いて女の内面の描き方の見事さを絶賛されているが、(経験がないからわからないのだが)すごいのだなと思う。表題作の「おんな舞台」が絶品ではあるが、「焙烙」が特に印象に残る。戦後すぐの日本を描いたものとして小品だが「屋根の上のマッカーサー」も貴重だと思う。「焙烙」が手に入りにくいとあるが、最近はネットですぐ見つかるのだよな。
読了日:02月19日 著者:半村良
 覆面作家は二人いる 新装版 (角川文庫)の感想
覆面作家は二人いる 新装版 (角川文庫)の感想
再読。コメディーである。北村作品らしく、コメディーであっても本格推理として、上滑りすることなくきっちりとまとめられている。主人公は美貌のお嬢様で、かつ異能の人である。異能の人を出せばかなりの部分物語は興味をひくことができるのだが、そこに適切な脇役を配して強固な結構とするところが作者の腕であろう。
読了日:02月15日 著者:北村 薫
 冬のオペラ (角川文庫)の感想
冬のオペラ (角川文庫)の感想
再読。前に読んだときはあまりすきになれなかったのだが、もう一度読んでみるとそうでもない。メイントリックの概略は覚えていたが、幕切れがあんなに切れ味が良かったというのは再認識。相川司さんの解説にあるけれども、巫弓彦という探偵名・探偵の造形もなんとなく小林信彦(中原弓彦)の神野推理を思わせるところがある。あくまでこれは本格推理小説なのであるな。
読了日:02月12日 著者:北村 薫
 街の灯 (文春文庫)の感想
街の灯 (文春文庫)の感想
田中絹代主演の映画「兄さんの馬鹿」が1932年だからヒロインの花村英子は1917年生まれくらいだろう。何不自由なく生活を楽しんでいる英子だが、戦中戦後とどのような人生を歩むのだろう、と思ってしまう。終戦時に30歳手前になるはずだ。
読了日:02月07日 著者:北村 薫
 謎物語 (あるいは物語の謎) (創元推理文庫)の感想
謎物語 (あるいは物語の謎) (創元推理文庫)の感想
推理小説の好きなむきにはよい本であろう。つぎつぎと紹介される逸話や本について、すぐに読んでみよう(全部ではないにしても)と思えなくなったのは、環境から図書館に自由にアクセスできないこともあるが加齢が主な原因であろう。気合が入らないのである。
読了日:02月05日 著者:北村 薫
 太宰治の辞書 (創元推理文庫)の感想
太宰治の辞書 (創元推理文庫)の感想
図書館で借りて一回読んだのだが、シリーズを改めて読み返していて手元になかったので購入。これも「六の宮の姫君」ほどではないがぺダンティックである。「花火」は芥川だからいいのだけれど、太宰治に関しては私はよい読者ではないので、パスですなー。思わぬところでクラフト・エヴィング商會が出てきてびっくり。
読了日:02月01日 著者:北村 薫
 水に眠る (文春文庫)の感想
水に眠る (文春文庫)の感想
これも再読だが、「くらげ」のみ明瞭に記憶に残っていた。おそらくSFとしての結構が堅固なせいだろう。SFともファンタジーともつかない短編集だが、著者の手際はあざやかである。あざやかすぎてよくわからないところもあるが、いずれにせよ水際立った短編集である。他人事でない年になって認知症を扱った「弟」が印象にのこる。それ以外はすでに追憶の世界である。
読了日:01月27日 著者:北村 薫
 朝霧 (創元推理文庫)の感想
朝霧 (創元推理文庫)の感想
「秋の花」は重かったし、「六の宮の姫君」はぺダンティックすぎ、「朝霧」でやっと軽さと深みと楽しさのシリーズのたのしみが戻って来た気がする。傑作。
読了日:01月23日 著者:北村 薫
 夜の果てへの旅〈上〉 (中公文庫)の感想
夜の果てへの旅〈上〉 (中公文庫)の感想
高校生のころに買って、読まずにいた上下巻だが、上巻だけ読んでやめることにした。この汚物をまき散らしたような作品は発表時の1932年には衝撃だったのだろうが、いま読み返してみても興味をひく所は(私には)なかった。
読了日:01月18日 著者:セリーヌ
 六の宮の姫君 (創元推理文庫)の感想
六の宮の姫君 (創元推理文庫)の感想
2度目なのだが、私の大正時代の文学の知識では到底立ち行かず、今回もよくわからなかったと言わざるを得ない。難解である。本筋の他に大量の周辺情報が詰め込まれている上にさらにサブストーリーがあり、初心者は混迷を極める。かろうじて菊池寛はどんな迷いがあろうとも成仏できると考え、一方芥川龍之介はそれは違うと思ったらしいということだけはわかった。今は幸いどちらも青空文庫で簡単に読めるし、主要な作品を読んで行こうかと思う。いやー、難しい小説ですね。
読了日:01月14日 著者:北村 薫
 秋の花 (創元推理文庫)の感想
秋の花 (創元推理文庫)の感想
「空飛ぶ馬」「夜の蝉」と傑作掌編を積み重ねてきての同シリーズの長編なのだが、テーマが人の死であり、重苦しい雰囲気が続く中で、いかにサブストーリーの軽く明るい挿入部分があっても、救いにはなりにくい。読み進めるのに抵抗がある。これは長編にしたのは失敗なのではないか。それと「隠れんぼうの鬼」は探す方であって、隠れる方ではないのではないか。
読了日:01月11日 著者:北村 薫
 夜の蝉 (創元推理文庫―現代日本推理小説叢書)の感想
夜の蝉 (創元推理文庫―現代日本推理小説叢書)の感想
創元文庫の解説の吉田利子さんの言うように、「円紫さんと私」シリーズは「私」のビルドゥングスロマンである。時は流れる。このシリーズも時代が色濃く反映している。ネットもスマホもない時代である。「夜の蝉」には郵便が主要なテーマとなっているが、今の制度ではここまでゆるくないのではないかと思う。
読了日:01月06日 著者:北村 薫
 空飛ぶ馬 (創元推理文庫―現代日本推理小説叢書)の感想
空飛ぶ馬 (創元推理文庫―現代日本推理小説叢書)の感想
再読なんですが、面白かったという印象だけで、ほとんど忘れている(呆)。「円紫さんと私」シリーズ一作目だが、ややぺダンティックなのだな。傑作であるのは間違いない。北村薫さんの燦然たるデビュー作である。ただ、嫌いな人もいるかもしれない。古田織部の話は謎解きにやや無理があるように思うがどうか。
読了日:01月05日 著者:北村 薫
読書メーター
読んだ本の数:48
読んだページ数:13330
ナイス数:263
 羊をめぐる冒険(下) (講談社文庫)の感想
羊をめぐる冒険(下) (講談社文庫)の感想再読なのだが、まったく記憶に残っていなかった。ようするにロジカルな結末によるカタルシスのようなものが決定的に欠如しているのだろうと思う。覚えられないのだ、スジが。前半は彼女とのロードムービーみたいで楽しくもあるのだが、後半はとにかくわけがわからないとしかいいようがない。
読了日:12月31日 著者:村上 春樹
 レキシントンの幽霊 (文春文庫)の感想
レキシントンの幽霊 (文春文庫)の感想確か持っていたと思ったら、やっぱり持っていた本。「沈黙」「七番目の男」をはじめ、かなりシリアスで重い話題を扱っているので、読み応えのある短編集だと思う。「めくらやなぎと、眠る女」は「蛍・納屋を焼く・その他の短編」に収録されたものの短いバージョンということである。
読了日:12月25日 著者:村上 春樹
 色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 (文春文庫)の感想
色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 (文春文庫)の感想面白かった。相変わらずセックスだらけだが、超自然的なところがほとんどなかったので、歓迎である。夢の話は出てくるが夢は夢なのでいかに非現実的でも許容できる。超自然的でも吹っ切れているもの(ムクドリがどんどん大きくなる)のはキライではないのだが。沙羅がいっしょに歩いていたのは、お気に入りの叔父さんかもしれないではないかと思う。
読了日:12月21日 著者:村上 春樹
 テスカトリポカの感想
テスカトリポカの感想なぜアメリカ大陸の古代文明はユーラシア大陸の西の端に生まれた西洋文明に敗れたのか。ジャレド・ダイアモンド「銃・病原菌・鉄」のテーマである。まったく異次元の倫理性を持つ宗教を描いていて労作であるが、臓器売買のシステム作りを進めていく中盤ですでにうんざりしてしまう。
読了日:12月13日 著者:佐藤 究
 螢・納屋を焼く・その他の短編 (新潮文庫)の感想
螢・納屋を焼く・その他の短編 (新潮文庫)の感想題名からしても寄せ集め短編集なのだろうが、まとまりのない印象である。「めくらやなぎ」が一番よかったかな。「蛍」は「ノルウェーの森」の原型のように感じられる。特にラストの部分とか。
読了日:11月23日 著者:村上 春樹
 文にあたるの感想
文にあたるの感想くどい。校正というのがいかに大変な仕事で、一方報われることが少ないか。問題なくてあたりまえ、間違いを見逃せばずっと汚点になる。それはわかりましたよ。これだけ何度も繰り返して書いていただければ。著者や編集者となど、興味深い逸話がないとはいわないがほとんど出てこないし、この本は買って損しました。なにしろ繰り返しが多いのはひどいと思う。それで稿料を稼いでいると言われてもしかたないでしょう。仕事が無味乾燥でも、それについての本が無味乾燥になる言い訳にはならないと思います。
読了日:11月17日 著者:牟田 都子
 雁 (新潮文庫)の感想
雁 (新潮文庫)の感想これも趣旨のよくわからない小説なんだよなぁ。お玉さんは出てくるが恋愛になるわけでもなく、雁殺して喰って終わり。最後の部分に言い訳めいたことが書いてあるが、なんなんだこれは。
読了日:11月12日 著者:森 鴎外
 新装版 パン屋再襲撃 (文春文庫)の感想
新装版 パン屋再襲撃 (文春文庫)の感想この短編集が好きだ。特に冒頭の「パン屋再襲撃」はある種の爽快感がある。何でももっている結婚して2週間の妻もかっこいいし。この短編集にはそこここに「渡辺昇」が登場する。ネコの名前でもある。ファミリーアフェアの「フリオ・イグレシアス」をモグラの糞に喩えるとことも爽快である。その昔、フリオのLPをもらったことがあるが、ほとんど聞かずにどこかになくしてしまった。ジャケットのフリオの写真、首筋におできか剃刀負けのようなものがあったのが妙に記憶に残っている。
読了日:10月28日 著者:村上 春樹
 回転木馬のデッド・ヒート (講談社文庫)の感想
回転木馬のデッド・ヒート (講談社文庫)の感想この本も読むのは何度目かわからない。著者の前文によれば、他人から聞いた話をそのまま文章にしたものだという。従って聴取のシーンがあれば村上氏自身が登場する。フィクションともノンフィクションともとれる不思議な短編集である。
読了日:10月25日 著者:村上 春樹
 カンガルー日和 (講談社文庫)の感想
カンガルー日和 (講談社文庫)の感想超自然的なテーマもあるが、まずまず現実世界にとどまる話がおおい。最後の図書館奇譚は例外的だがイメージが明確で読んでいて不快感はない。
読了日:10月21日 著者:村上 春樹
 中国行きのスロウ・ボート (中公文庫)の感想
中国行きのスロウ・ボート (中公文庫)の感想この本は何度か読んでいるのだが、他の村上春樹の短編集同様、何度も読み返したくなる魅力がある。大して筋があるわけでないのだが、結局読んでいて居心地のよい文章なのだろう。ちなみにこの短編集は比較的セックスは少な目である。
読了日:10月16日 著者:村上 春樹
 女のいない男たち (文春文庫 む 5-14)の感想
女のいない男たち (文春文庫 む 5-14)の感想映画化された「ドライブ・マイ・カー」を含む短編集。相変わらずセックスの話だが、最後から二本目の「木野」だけが少々色合いが違う。村上ごのみの超自然が顔をみせているのだ。他の短編は書き下ろしの最後の「女のいない男たち」を除いて現実世界の法則に則って(変なところはあるにせよ)書かれている。村上の他の短編集同様ときどき読み返したくなる。映画は見ていないが、オリジナルが短いだけに映画独自の脚色が多く施されているのだろう。
読了日:10月14日 著者:村上 春樹
 まぼろし小学校―昭和B級文化の記録の感想
まぼろし小学校―昭和B級文化の記録の感想1996年の本だが、昭和の小学校が活写されている。よくぞ残しておいてくれました。平均的な投稿者層が私よりやや若いので知らないこともあるけれど、懐かしい話もたくさん出てくる。ポキールありましたね。
読了日:10月07日 著者:串間 努
 出家とその弟子 (岩波文庫 緑 67-1)の感想
出家とその弟子 (岩波文庫 緑 67-1)の感想とっくに指摘されているだろうが、最後に審判されるとか、罪は先に償われているとか、非常にキリスト教の影響が感じられる。唯円とかえでの逢瀬のところが楽しい。親鸞も善鸞も唯円もさびしいという。人皆さびしいものなのか。
読了日:10月05日 著者:倉田 百三
 明暗 (新潮文庫)の感想
明暗 (新潮文庫)の感想未完ではあるが、前半は漱石の最高傑作といっていいのではないか。相変わらず面倒くさい登場人物が出てくるが、小林というのは漱石の小説中では新しい人物造形だと思う。手術後に湯治に行くところが展開としては無理がある気がする。清子の真意を質しに行くのだが、そんなことなら、自分が結婚する前に済ませておけよと思うが、そこが漱石のややこしい登場人物である。やってしまってからああでもないこうでもないと懊悩するのである。湯治場のシーンは夢の中のような表現である。これは続きが書きたくなるよね。
読了日:10月02日 著者:夏目 漱石
 連句のたのしみの感想
連句のたのしみの感想これは力作。8つの歌仙の解説は大変だったろうと思います。特に、柳田/折口の歌仙は高踏的で、解説も両者の著作をかなり読み込まないとできない力業。
読了日:09月21日 著者:高橋順子
 道草 (新潮文庫)の感想
道草 (新潮文庫)の感想主人公の健三にしても、法律上の義務もないのだし、昔世話になった人の無心など、きっぱり断ればいいと思うのだが(この点では奥さんに同情的)ぐずぐずしている。明治の気分だろうか。この夫婦、感情的にはすれ違っているくせに子供はばんばんつくっているのもよくわからない。
読了日:09月12日 著者:夏目 漱石
 こころ (新潮文庫)の感想
こころ (新潮文庫)の感想時代と言ってしまえばそれまでなのだろうが、「先生」の行動は考えられないことばかりであり、感情移入も難しい。Kの告白を聞いて、自分も告白すればいい話だし、相手の母親に承諾をもらう前に、本人の承諾を得るのが先だろうし、それもKを含めて正々堂々と勝負すればいいだろうし。ねるとんみたいに(喩えが古いな)有力な親族に本来自分のものであるべき資産をいいようにされてしまうというのは漱石のこだわるテーマで、こちらの問題については、場合によっては現代でも起き得ることかとも思う。
読了日:09月04日 著者:夏目 漱石
 行人 (新潮文庫)の感想
行人 (新潮文庫)の感想漱石お得意の「なぜか面倒くさい人」が出てくる「嫂コンプレックス」がテーマの小説だと思っていたが、再読してみると、さすがによく書けているし、面白い。特に、最後の書簡の中で描かれる一郎の「常に不安にさいなまれている」というのは、程度の差はあれ、わからないでもない気がする。
読了日:08月25日 著者:夏目 漱石
 新書762「君が代」 日本文化史から読み解く (平凡社新書)の感想
新書762「君が代」 日本文化史から読み解く (平凡社新書)の感想現行の「君が代」の詳細な成立経緯を追うのではなく、この「国歌」の擁する広大な歴史的背景を描いている。特に上代からはじめは「我が君は」と歌い始められたものが徐々に変化して、多くの作品に広がっていく描写が興味深い。「君が代」はこの長い歴史を持つ日本の「うた」と西洋音楽のハイブリッドだといってよいだろう。一方で、アジア的な背景としてはそれほどの厚みを持つものではないということも明らかになる。
読了日:08月20日 著者:杜 こなて
 彼岸過迄 (新潮文庫)の感想
彼岸過迄 (新潮文庫)の感想大患を経た漱石が、肩慣らしをしながらすこしずつ他愛もない話を重ねながら、結局は彼の小説に毎度登場する「面倒くさい男」としての須永市蔵という人物にたどり着き、しかも手紙で終わるという毎度な展開である。この面倒な男にかかわりを持ってしまった千代子もいい迷惑であろう。自家撞着に陥ってしまう須永の性情は漱石自身もその一面にもっていた性格なのだろうと思う。時代を感じさせる表現に満ちていて読むこと自身を楽しめる小説ではある。
読了日:08月18日 著者:夏目 漱石
 門 (集英社文庫)の感想
門 (集英社文庫)の感想改めて読んでみると、以前は何かはっきりしない小説だと思っていたが、結構筋もきちんとあり形式的にも整った小説だと再認識した。禅寺にいくくだりはあまりに唐突だし、十日やそこらで悟ることもできないだろうから不自然極まりないが、そこを除けばストーリーとして整ったものだと思う。当時は不義姦通といったことに厳しかったことがわかる。そもそも御米は「妹」と紹介されているのだから仕方ない面があるような気がする。一方で時代は畜妾には全く寛大だったことを思うと理不尽が気がする。
読了日:08月03日 著者:夏目 漱石
 それからの感想
それからの感想どうも明治の男は「遊蕩」と「恋愛」を峻別できたらしい、というのが結論である。代助は三千代との恋愛にはしるわけだが、その間にも「遊蕩」はしているようで、このあたり私にはよくわからない。もちろん作者の漱石も「峻別可能」と考えていたのだろう。「高等遊民」というが、親兄弟にたかって生きているというのも倫理的にはおかしい。というようなことは多々あれど、代助が自分の気持ちに気付き、三千代がこれに応えるという本筋が魅力的なのである。
読了日:07月27日 著者:夏目 漱石
 19階日本横丁 (1977年) (集英社文庫)の感想
19階日本横丁 (1977年) (集英社文庫)の感想文庫が昭和52年だから、主に70年代の日本の総合商社の活躍というか葛藤というか、ドタバタというかを描いた小説で、いま読み返しても十分考えさせられる。舞台は明確には書いていないが、今戦争をしている当事国の大都市であろう。私自身は商社マンではないが海外とのお付き合い(20年ほど後だが)があり、ここで描かれる彼我の文化や商習慣の違いには直接のひりひりした思いがあり、他人事とは思えない。作中、ベトナム戦争で出たスクラップを商社が買い取る話が出てくるが、今次のウクライナ戦争では誰が買い取るのだろうか。
読了日:07月21日 著者:堀田 善衛
 三四郎の感想
三四郎の感想漱石の描く女性も虞美人草の藤尾からかなり進化した。地方から出てきた学生が年上の女におもちゃにされるという、行ってみればそれだけの話だが、時代の空気も感じられて面白い。里見美禰子が"Stray Sheep"(イザヤ書 53:6)という謎をかける。漱石の描く女は謎を掛けるのが好きで、男はまたちょっとした謎に戯れるのが大好きなようだ。
読了日:07月10日 著者:夏目 漱石
 斜めから見たマエストロたちの感想
斜めから見たマエストロたちの感想N響事務局長が綴る往年の招聘指揮者の逸話を中心に、クラシック、特にオーケストラに関するよもやま話を集めた本で、大変面白いのだが、再版も文庫化もされていないようで大変残念である。有馬大五郎氏の逸話もすさまじく、サヴァリッシュへの手土産として石燈籠を航空便で送らせたなどというのはすごい話だ。
読了日:07月08日 著者:長谷 恭男
 虞美人草の感想
虞美人草の感想もちろん再読・再々読であるが、やっぱり面白い。現代的な感覚からすれば藤尾だって単に金持ちのスポイルされたお嬢さんに過ぎないので、なにも憤死するところまで追い詰めるというのは周りのいい大人のすることとしてはやりすぎである。欽吾=一コンビ+宗近のオヤジ、やりすぎ。誰が一番悪いかといえば優柔不断の小野さんが悪いのだけれどね。小野さんも一に言われてしおしおとなるくらいなら最初から(以下略)謎の女、藤尾のおっかさんにしたってそんな悪人かなぁ。どこにもいますよああいう人。やっぱりやりすぎだと思う。
読了日:07月05日 著者:夏目 漱石
 dele (角川文庫)の感想
dele (角川文庫)の感想テレビドラマを数話録画して残してあったものを再度見て、やっぱり面白いと思って、原作を読んだ。TVドラマにはない設定も出てきて興味深い。ネコも登場する。
読了日:06月22日 著者:本多 孝好
 父・こんなこと (新潮文庫)の感想
父・こんなこと (新潮文庫)の感想大変な親であり、大変な子である。要は大変な親子である。読者の側としては「こんなこと」を「こんなこと」と思うかどうかが問われる。彫琢された文章が「大変なこと」を正確に誠実に切り出して読者の前に提示する。これからはこういうものを読む人も少なくなるだろうと思うとさみしいが。
読了日:06月06日 著者:幸田 文
 ねこのほそみち ―春夏秋冬にゃーの感想
ねこのほそみち ―春夏秋冬にゃーの感想ネコに関する俳句集。
読了日:05月04日 著者:堀本 裕樹,ねこまき(ミューズワーク)
 歌仙の愉しみ (岩波新書)の感想
歌仙の愉しみ (岩波新書)の感想このお三方の知識は該博(あたりまえ)で、わたしなんぞ到底足下にも及ばず、このレベルに達するのは無理だと早々にあきらめた。 逆に言うと、非常にぺダンティックなお遊びで、当人たちには大変楽しいのだろうけれど、できあがった歌仙を読み解くのは同程度の教養を(それも3人分)もっていないと無理だ。 これだけ解説されれば、なるほどとも思うが、素の歌仙そのものを読んでもまずわからないと思う。通底する俳味なり俳諧趣味はわからないでもないが。
読了日:04月30日 著者:大岡 信,丸谷 才一,岡野 弘彦
 たとえばの楽しみ (講談社文庫)の感想
たとえばの楽しみ (講談社文庫)の感想読書好き、本好きには大変居心地のよいエッセイ集である。
読了日:04月27日 著者:出久根達郎
 いつのまにやら本の虫 (講談社文庫)の感想
いつのまにやら本の虫 (講談社文庫)の感想本(古本)にかかわるエッセイ集であるが、大変楽しく読むことができた。言葉の調子がよいこともあろう。
読了日:04月09日 著者:出久根達郎
 本のお口よごしですが (講談社文庫)の感想
本のお口よごしですが (講談社文庫)の感想大変面白いエッセイ集であった。本に関する話題が尽きない。それにしても最近は本が売れないらしいですね。古本屋さんがまとまった数の不要の本が出ても、出張買取をしてくれなくなった。2015年の話ですが、古本商に電話したら「いまもう古本は売れないのですよ」と言われてしまった。さみしいことであります。
読了日:03月27日 著者:出久根達郎
 コンサル一年目が学ぶことの感想
コンサル一年目が学ぶことの感想kindle unlimitedの期間内だったので好奇心から手に取った。こんな当たり前のこと書いて金とるんじゃないよ(ってとられてないけど)っつーか、最近の人はこういうことを本を読まないと教えてもらえないのか。
読了日:03月06日 著者:大石哲之
 マエストロ : 3 (アクションコミックス)の感想
マエストロ : 3 (アクションコミックス)の感想オーケストラの懐事情から内部の対立、クラシック音楽のあるあるを拾いながらストーリーは進む。しかし、残念ながらコミックスでは音は出せない。映画化もされたようだが未見である。
読了日:03月05日 著者:さそうあきら
 そそっかしい小猫 (ハヤカワ・ミステリ文庫)の感想
そそっかしい小猫 (ハヤカワ・ミステリ文庫)の感想実は昭和35年発行の砧一郎訳、ハヤカワ・ポケット・ミステリで読んだ。モトイエに眠っていたHPMシリーズがまだ何作かある。この作品、翻訳がもっと読みにくいかと思ったがそうでもなかった。すべてのヒントが小猫の習性にかかっているところなど、実に洒落ており、謎解きも小手先ではない堂に入ったもので流石ペリー・メイスンものという風格をもっている。
読了日:02月02日 著者:E.S. ガードナー
 神保町奇譚の感想
神保町奇譚の感想これは計画倒産であり、倒産における資産の隠匿であって、詐欺罪を構成するんじゃないか?これを不問に付すのはいかがなものか。
読了日:01月29日 著者:池井戸 潤
 古書カフェすみれ屋とランチ部事件 古書カフェすみれ屋と本のソムリエ (だいわ文庫)の感想
古書カフェすみれ屋とランチ部事件 古書カフェすみれ屋と本のソムリエ (だいわ文庫)の感想三作目。ちょっと切れ味が落ちたかなぁと思いました。謎解きがくどい気がする。1-2作目はもっとすっきり、やられた感があったのですが…
読了日:01月29日 著者:里見蘭
 古書カフェすみれ屋と本のソムリエ (だいわ文庫)の感想
古書カフェすみれ屋と本のソムリエ (だいわ文庫)の感想料理の説明がくだくだしいのは、それを楽しみに読む人がいるからだろう。こういう日常のミステリーというのも大変結構である。まずミステリーなのに人が死なない。北村薫さんのものほどぎりぎり煮詰められていないが、この緩やかさが味というものだろう。
読了日:01月27日 著者:里見蘭
 古書カフェすみれ屋と悩める書店員 古書カフェすみれ屋と本のソムリエ (だいわ文庫)の感想
古書カフェすみれ屋と悩める書店員 古書カフェすみれ屋と本のソムリエ (だいわ文庫)の感想料理を中心にした推理モノであるが、まったく料理のできない私でも面白かったのだから、おすすめできる一冊である。いろいろな本が出てきてかなり引用や要約もあるのでずるいような気もするが…面白ければいいでしょう。実は幸田文は好きなのだ。
読了日:01月25日 著者:里見蘭
 書店員 波山個間子 1巻
書店員 波山個間子 1巻読了日:01月23日 著者:黒谷 知也
 書店員 波山個間子 2巻の感想
書店員 波山個間子 2巻の感想これで少しでも本に興味をもって読んでくれる若い人が増えればいいが、いずれにせよ紙の本はもう終わったんだろうなぁ。何冊あっても古本屋さんが見に来ないようでは。少なくとも古本業界は壊滅。ネットショップのロングテールに期待するしかないか。
読了日:01月23日 著者:黒谷 知也
 書店員 波山個間子 番外編 (空汀書房)の感想
書店員 波山個間子 番外編 (空汀書房)の感想マイクロノベルがなかなか面白かった。
読了日:01月21日 著者:黒谷知也
 ミュジコフィリア : 5 (アクションコミックス)の感想
ミュジコフィリア : 5 (アクションコミックス)の感想取材も大変であっただろう。力作である。しかし、これを読んで現代音楽を聞いてみたいという人がどのくらい増えるかは疑問であるな。
読了日:01月17日 著者:さそうあきら
 史上最強の内閣 (小学館文庫)の感想
史上最強の内閣 (小学館文庫)の感想作者は某朝○新聞と某みずほさんがキライらしいが、話は面白かった。防衛大臣が「わしに向かって脅しかけた人間で、 立って息しとるのはお前だけじゃ、あとはみんな宮島沖に沈んどる」とか聞いてみたいものだが(笑)
読了日:01月16日 著者:室積 光
 おれたちの歌をうたえの感想
おれたちの歌をうたえの感想どうもよくわからないので、再読してみた。やっぱりいろいろなところに無理がある。なぜ文男は妹を強姦しようとした犯人である飯沢と仲良くなるのかが一番わからない。また、一応ロジカルにはこじつけてあるものの、近藤殺し、千百合殺し、それぞれの裏付けが薄弱すぎるし、肝心の犯人がそれを認めることなく姿を消してしまう。このあたりがあってしかるべき(これだけの大長編の)カタルシスをもたらさない原因ではないだろうか。竹内三起夫の一家惨殺にしたところで、いかに心神耗弱状態にあったとはいえ、根拠が薄弱すぎる。
読了日:01月09日 著者:呉 勝浩
 日中戦争 (岩波新書 黄版 302)の感想
日中戦争 (岩波新書 黄版 302)の感想どうも太平洋戦争の方にばかり目が向いて、日中戦争はなおざりにされている感がある。達成されるべき目標のない戦争であり、そもそも日本があの広大な中国を支配することなど誇大妄想に過ぎないといまなら思えるが、当時の「恐怖」はそういう理解を許さなかったのであろう。南京大虐殺は象徴的出来事ではあるが、日中戦争全体での双方の損失は甚大なものがある。日本人はこれを整理することなく、ここまで来てしまった。日中戦争をもう一度考えることなく中国や台湾との関係を整理することはできないだろう。
読了日:01月03日 著者:古屋 哲夫
読書メーター
一年に一回、一枚一枚、年明けの光の中で、あの人この人と記憶を新たにするのは悪くない。印刷の年賀状はよくないとかいうが、手間をかけて作ったものもあるだろうし、たとえ出来合いのものにしても健在証明だ。一筆なくても心は伝わる。年賀状はいとおしい。
 イエスタディ・ワンス・モア Yesterday Once More(新潮文庫)の感想
イエスタディ・ワンス・モア Yesterday Once More(新潮文庫)の感想作者が1959年(昭和34年)を徹底再現したタイムスリップものである。私は物心つく少々前ではあるが、時代の雰囲気はよくわかる。テレビの草創期であり、前回の東京オリンピックに向けて日本が全力疾走していた時代である。60年安保の年、まだ米国進駐軍(占領軍)の名残りがあり、日本人の海外渡航が不自由だった時代。残念ながら1959年の東京を目指そうとまで言う気にはなれないがノスタルジーはあり、時代の空気は懐かしい。葛飾区郷土と天文の博物館の展示は昭和37年準拠だったと思うが、こちらは更にその3年前を再現している。
読了日:06月11日 著者:小林 信彦
 背中あわせのハート・ブレイク (新潮文庫)の感想
背中あわせのハート・ブレイク (新潮文庫)の感想1988年作品。描かれているのは1949-1950年の「文京区の高台」にある「対学習院戦」をやる高校の映画研究会である。キーとなる人物、教師の「矢部」は「太平洋戦争中の(日本の)狂気がまだ生きのびている」ような人物である。物語は後半で一高校の話から朝鮮戦争と「逆コース」を描き出す。時代の描き方が克明で、それが世界情勢、ひいては2021年現在まで尾を引く日本の政治状況の問題点のスタート地点を明確に描き出している点で、今でも読むに値する小説だと思う。
読了日:06月12日 著者:小林 信彦
 悲しい色やねん (新潮文庫)の感想
悲しい色やねん (新潮文庫)の感想表題作はヒットソング「悲しい色やね」を題材に小林信彦に執筆依頼があって書かれた小説で、題名は「悲しい色やねん」で、1988年に仲村トオル主演で映画化された、ということらしい。小説の方は落語家と作家のやり取りだけで構成されているので映画の脚本とはかなり違うらしい(映画は未見)それ以外に3篇の短編が並べられているがよく言えばバラエティに富み悪く言えばバラバラである。戦中戦後のヤクザものを描いた「みずすましの街」が面白かった。
読了日:06月14日 著者:小林 信彦
 神野推理氏の華麗な冒険 (新潮文庫 こ 10-2)の感想
神野推理氏の華麗な冒険 (新潮文庫 こ 10-2)の感想神野推理氏はどうもキャラクター立てが中途半端だったように思う。シャーロック・ホームズを下敷きにして、旅行嫌いだがミーハーでといった設定はあるのだが今一つはっきりせず、コメディリリーフで援用した「大統領シリーズ」由来の旦那刑事の方が存在感があるくらいになってしまった。雑誌「太陽」の気楽な読み物という点ではよかったのだろうが、小林信彦作品の中では目立たない存在となってしまった。単行本は小林泰彦氏の洒落た挿絵で、本としての存在感はあるのだが。
読了日:06月18日 著者:小林 信彦
 唐獅子株式会社 (1978年)の感想
唐獅子株式会社 (1978年)の感想オヨヨ大統領シリーズに匹敵する、むしろ凌駕するパロディシリーズの第一作である。ヤクザもののパロディだが、キャラクターがどれも立っている。語り手にして主人公の不死身の哲、ダーク荒巻、インテリヤクザの原田、大親分、学然和尚、とスターが揃っている。1970年代後半の世相を皮肉ってあますところがない傑作だが、これを理解する人も減ってきているだろう。皮肉られるのはサラリーマン化するヤクザであり、西海岸ブームであり、ハイトレポートなどだが、いずれもギャグが冴えている。
読了日:06月19日 著者:小林 信彦
 唐獅子惑星戦争の感想
唐獅子惑星戦争の感想唐獅子株式会社のシリーズの5-7作目にあたり、1-4作の勢いはやや失われたとはいうもののパロディとして十分に成り立っていると思う。一緒におさめられているあとの4作の傾向があまりにバラバラで面食らうが、作者の両面性を如実に示しているのが興味深い。
読了日:06月20日 著者:小林 信彦
 唐獅子超人伝説の感想
唐獅子超人伝説の感想唐獅子「株式会社」「惑星戦争」ときて三作目の「超人伝説」であるが、フォーマットが定着するとともに安定してきた感がある。私には、架空のバナナ・リパブリックを舞台にした「唐獅子脱出作戦」が面白かった。シリーズ外の同梱作品もこの単行本に関してはコミカルなものが多いので、違和感なく読める。「親子団欒図」が小品ながらおかしい。
読了日:06月21日 著者:小林 信彦
 超人探偵の感想
超人探偵の感想再読である。探偵にしてテレビのシナリオ・ライターである神野推理氏が復活する。いずれの掌編も職人芸といっていい、推理小説のパロディになっているのだが、どうも今一つ印象が薄いのはやはり神野推理という主人公のキャラが立っていないから、のように思われる。むしろワトソン役で語り手の星川の方がまだしものように思う。そこへおなじみの学然やらダーク荒巻やらが絡んでくるのだが今一つ精彩を欠くという印象である。
読了日:06月28日 著者:小林 信彦
 唐獅子源氏物語 (新潮文庫)の感想
唐獅子源氏物語 (新潮文庫)の感想1980-1982年。作者が手慣れた設定、おなじみのキャラクターを縦横に動かして楽しませてくれる、唐獅子シリーズ円熟の7編である。一作目の唐獅子株式会社のきらめきこそないが、充実したパロディ/パスティーシュになっている。
読了日:06月30日 著者:小林 信彦
 関東軍 在満陸軍の独走 (講談社学術文庫)の感想
関東軍 在満陸軍の独走 (講談社学術文庫)の感想昭和40年(1965)の本。関東軍の歴史を淡々と叙述していく。日清・日露戦争後の日本のソ連に対する恐怖心が大きかったことを知る。それは結局1945年4月6日の日ソ中立条約のソ連側からの一方的廃棄となって現実のものとなる。そもそも日本の国力で米英ソ中を相手にしての全面戦争など無理に決まっているのだが、ずるずると泥沼に引き込まれていく。どこで引き返すこともできなかったであろう。
読了日:07月02日 著者:島田俊彦
 ドジリーヌ姫の優雅な冒険 (1978年)の感想
ドジリーヌ姫の優雅な冒険 (1978年)の感想雑誌「クロワッサン」の昭和52-53年(1977-1978)に連載された小説である。傑作である。一種のロマンポルノ以前の日活ヒーローもののパロディであり、かつグルメ小説なのだが、逸話のひとつひとつが価値あるものであり、ギャグも冴えている。
読了日:07月04日 著者:
 ビートルズの優しい夜 (新潮文庫)の感想
ビートルズの優しい夜 (新潮文庫)の感想内向的な中編4篇からなるが、いずれもテレヴィ界、ラジオ、映画というメディアに関わる物語である。最初の物語の登場人物は最後にちらほらと姿を見せ、全体に統一感を与えている。大変よくできた掌編組曲だ。特に最後の「ラスト・ワルツ」はおよそ創作に関わる人間は是非、自らの身を守る為にも読んでおくべきテキストだと思う。世の中にはひどい奴がいるのだ。
読了日:07月07日 著者:小林 信彦
 変人十二面相 (角川文庫 (5588))の感想
変人十二面相 (角川文庫 (5588))の感想子供向けというのだが、内容は最初の部分を除いてほとんど子供向けではない。1980年の記録とでもいうべきものではないか。1980年、山口百恵が引退し、巨人軍の長嶋が監督を辞任し、王が引退し、ジョン・レノンが射殺された年である。タイムマシンから同年を覗き見るような気持で再読した次第である。
読了日:07月10日 著者:小林 信彦
 紳士同盟(新潮文庫)の感想
紳士同盟(新潮文庫)の感想1979年の作品。もちろん再読だが、今回読んでみて傑作だと思った。おそらく前回読んだときはこちらが若すぎたのだろう。コン・ゲームのプロットは穴があるけれどもエンターテインメントとしてのキズにはなっていない。最後のオチまで気が利いている。80年代前夜の気分がキライでなければ面白い小説である。薬師丸ひろ子主演の映画があるが、映画の方は基本的コンセプトをこの小説に借りているだけでプロットからして全くの別物のようである。
読了日:07月13日 著者:小林 信彦
 紳士同盟ふたたび(新潮文庫)の感想
紳士同盟ふたたび(新潮文庫)の感想「紳士同盟」とそのシークエルである本作を少々過小評価していた。同名の映画は小説とはほぼ関係ない。小説の方は、よくできたエンターテインメントで、まいどおなじみのカモとエサを配しながら、本番のコン・ゲームはそれぞれ舞台と方法を工夫して飽きさせないようにうまく書かれている。1984年作品。当時の空気・風俗が懐かしいという意味で評価が甘くなっているかもしれないが。
読了日:07月16日 著者:小林 信彦
 発語訓練の感想
発語訓練の感想1984年作品。装丁といい、帯の惹句といい、この本をどう売っていいのかわからないのがありありとしているという意味でも面白い。パスティーシュなのだが、パスティーシュの大家、清水義範さんの「蕎麦ときしめん」が1986年だから、小林作品の方が早いのではないか。パロディ(という言葉は小林氏はキライらしいが)の中に批判精神が横溢しているのが大変うれしい。日本がソ連に占領されていたらという「サモワール・メモワール」一作とってみても見事なものだと思う。
読了日:07月19日 著者:小林 信彦
 ちはやふる奥の細道 (新潮文庫)の感想
ちはやふる奥の細道 (新潮文庫)の感想1983年、小林信彦さんのパロディの労作である。わざわざニューヨークに取材し、そのための机を新調したという文字通りの労作(といってもその解説までパロディだったらどうしよう)。労作ゆえに読むのもちょっと大変である。最初に読んだ時も少々苦労した覚えがある。一つには私が奥の細道をよく知らないせいでもあるのだが。パロディをパロディととらずに批評が出たりしたのはおそらく本当のことだろう。それほど当時はパロディに対する世間の理解が浅かったということだろう。その後清水義範さんが出たりして多少はよくなったと思うが。
読了日:07月28日 著者:小林 信彦
 生きるとか死ぬとか父親とか(新潮文庫)の感想
生きるとか死ぬとか父親とか(新潮文庫)の感想TVドラマ(吉田羊・國村隼)がよかったので、原作をキンドルで読んだ。創作もあるのだろうが、かなりの「私小説」である。ジェーン・スーさん自身のお顔は存じ上げているのでいいのだが、お父様の方はどうしても國村さんで再現されてしまうのはいたしかたないところ。妻・娘だけでなく複数の女性に末永く慕われ、仕えられちゃうタイプ。
読了日:08月03日 著者:ジェーン・スー
 村上朝日堂 はいほー! (新潮文庫)
村上朝日堂 はいほー! (新潮文庫)読了日:08月09日 著者:村上 春樹
 村上朝日堂 (新潮文庫)
村上朝日堂 (新潮文庫)読了日:08月17日 著者:村上 春樹,安西 水丸
 ドルチェ(新潮文庫)
ドルチェ(新潮文庫)読了日:08月20日 著者:誉田哲也
 ドンナ ビアンカ (新潮文庫)
ドンナ ビアンカ (新潮文庫)読了日:08月23日 著者:誉田 哲也
 小説8050の感想
小説8050の感想林真理子さんとの対談で憲法学者の木村草太さんが「リアリティがある」とコメントしていたので読んでみた。大変面白い。テーマは重いが、さすがは手練れの小説家の手にかかって、エンターテインメントとしてもきっちり成立している。
読了日:09月09日 著者:林真理子
 シガレット&チェリー 11 (チャンピオンREDコミックス)の感想
シガレット&チェリー 11 (チャンピオンREDコミックス)の感想読んでしまった。面白かった。
読了日:10月08日 著者:河上だいしろう
 みらいめがね2 苦手科目は「人生」ですの感想
みらいめがね2 苦手科目は「人生」ですの感想面白かった。
読了日:10月18日 著者:荻上 チキ,ヨシタケ シンスケ
 昭和史 新版 (岩波新書)の感想
昭和史 新版 (岩波新書)の感想1959年の本だが、1926年から戦後十数年までの歴史をコンパクトにまとめたものとして未だに価値があると思う。時代が近い分、戦時のことがより身近に感じられる良書。
読了日:10月22日 著者:遠山 茂樹,藤原 彰,今井 清一
 星間ブリッジ (4) (ゲッサン少年サンデーコミックス)の感想
星間ブリッジ (4) (ゲッサン少年サンデーコミックス)の感想上海を舞台にした日中戦争下の恋愛物語。表現はマイルドだが面白かった。
読了日:10月30日 著者:きゅっきゅぽん
 民王 シベリアの陰謀 (角川書店単行本)の感想
民王 シベリアの陰謀 (角川書店単行本)の感想コロナ禍下真っ最中に発表された風刺小説といっていいと思う。未知のウィルスに真っ当な対策をとろうとする政権に対して、既存権益に胡坐をかいて動こうとしない医師会、新しいことには一稿に取り組もうとしない官僚、といった多くの障害をリアルに描き出している。一種のカリカチュアであるから、コメディタッチを失わずにシリアスな問題を描き出すのはさすが手練れの作者だと思わされる。
読了日:10月31日 著者:池井戸 潤
 サバエとヤッたら終わる 1 (BUNCH COMICS)の感想
サバエとヤッたら終わる 1 (BUNCH COMICS)の感想愛読しております。
読了日:11月04日 著者:早坂 啓吾
 Dr.コトー診療所 完全版(25)の感想
Dr.コトー診療所 完全版(25)の感想この島の診療所は急患にして重篤な患者が来過ぎ(^^♪。それはともかく、絵といいストーリーといい、素人にはわからないとはいいながらそれらしい医療のノウハウといい、充実していると感じさせる。筆力というのでしょうか。
読了日:11月13日 著者:山田貴敏
 「日本」ってどんな国? ──国際比較データで社会が見えてくる (ちくまプリマー新書)の感想
「日本」ってどんな国? ──国際比較データで社会が見えてくる (ちくまプリマー新書)の感想RADWIMPSのボーカルである野田洋次郎氏の言葉が引用されているが、「国に何も期待しない、自分のことは自分で守る」という言明の如何に浅慮であることかが明確に述べられている。各種調査の数字を基にした日本論。一聴に値する。
読了日:11月19日 著者:本田由紀
 ミチクサ先生 上の感想
ミチクサ先生 上の感想漱石はよく読んだので、登場人物の一々を覚えなくてもわかっているのがありがたい。創作であるからどこまでが史実かわからないが、まぁ、こんなこともあったろうかと思いながら楽しく読ませていただきました。
読了日:11月30日 著者:伊集院静
 ミチクサ先生 下の感想
ミチクサ先生 下の感想修善寺の大患からあとがやや急ぎ足すぎる感はあるが、面白く読んだ。永井荷風とか、古い人のように思うが漱石からすれば弟子のひとりのようなものなのだな。
読了日:12月04日 著者:伊集院 静
 海猿 完全版 10の感想
海猿 完全版 10の感想海賊対策のくだりはどういうミッションだったのかよくわからない。結末部分も一番中心となるべき二人がどうなったのかよくわからなかった。人死にが多い割にはカタルシスがない。
読了日:12月10日 著者:佐藤 秀峰
 村上朝日堂の逆襲 (新潮文庫)の感想
村上朝日堂の逆襲 (新潮文庫)の感想再読。コーヒーにはラム酒と思っていたのは、この本の中で、ドイツでは寒いときにはコーヒーにラム酒を入れて飲むという叙述があって、おいしそうだと思ったのがきっかけであったことを思い出した。
読了日:12月13日 著者:村上 春樹,安西 水丸
![史記4 呉越燃ゆ 下 ([テキスト] 史記 4)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Gzkc0VQSL._SL75_.jpg) 史記4 呉越燃ゆ 下 ([テキスト] 史記 4)の感想
史記4 呉越燃ゆ 下 ([テキスト] 史記 4)の感想なんとなく知っている話が出てくる。勉強になりました。それにしても、剣を両手でもって自らの首を切り落とす形の自決シーンがたくさん出てくるが、あれは可能なのだろうか。
読了日:12月27日 著者:久保田 千太郎
 おれたちの歌をうたえの感想
おれたちの歌をうたえの感想これが2000円は高かった。
読了日:12月28日 著者:呉 勝浩
読書メーター
読んだ本の数:73
読んだページ数:19745
ナイス数:354
 楽譜の風景 (岩波新書)の感想
楽譜の風景 (岩波新書)の感想岩城さんの苦労話が面白い。日本のオーケストラ、現代音楽の草分け的存在だからご苦労も多かったであろう。「春の祭典」を振り間違える話は大変だなぁと思う。そのあとのメルボルン響の慰め方がなかなか泣ける話である。確かに暗譜で振るとかっこいいけどねぇ。「作曲家の中には、自分が書いた複雑な音を聴き分けられない人が、少なからずいる。」「初演の練習の時に作曲家は病気になってはいけないのである。」「世の中には、いろいろな演奏者がいる。はっきり言えば、おそろしくバカなピアニストもたくさん存在するのだ」等草創期ならではの警句も
読了日:01月03日 著者:岩城 宏之
 プレゼント (中公文庫)の感想
プレゼント (中公文庫)の感想葉村晶シリーズの記念すべき第一作である。文章の書き方そのものにトリックが仕掛けてある場合があるので、うかうか読んでいると最後にどんでん返しできれいに決められても、どういう意味かがすぐにわからずもう一度読み直すことになったりする。二度楽しめてお得といえばお得だろうか。
読了日:01月05日 著者:若竹 七海
 依頼人は死んだ (文春文庫)の感想
依頼人は死んだ (文春文庫)の感想女性探偵でハードボイルドをやろうという趣旨は非常に面白い。最後にどんでん返しを食らって、もう一度読み直させられることがあるのは前作同様である。書き下ろしの最後の短編は超自然的な終わりになっていてあまり面白くない。強力な催眠術なんか導入したらせっかくの推理小説をスポイルしてしまう。
読了日:01月12日 著者:若竹七海
 悪いうさぎ (文春文庫 わ 10-2)の感想
悪いうさぎ (文春文庫 わ 10-2)の感想葉村晶シリーズの長編なのだが、今一つ調子が出ていない感じはある。若竹さんの持ち味である「驚きのどんでん返し」は長編ではやりにくい面もあるだろう。結局、女ハードボイルドの葉村と警察の柴田や探偵会社の桜井らとのやりとりを楽しむことになり、それはそれで結構なのだが…大家の光浦がいいキャラでこれはクリス松村さんにぜひ演ってもらいたい。
読了日:01月20日 著者:若竹 七海
 オリヴィエ・メシアンの教室 作曲家は何を教え、弟子たちは何を学んだのかの感想
オリヴィエ・メシアンの教室 作曲家は何を教え、弟子たちは何を学んだのかの感想思ったより実例を挙げての説明に乏しく、期待したものとは違っていて私としてはつまらなかった。一部春の祭典の分析などちょっと顔を出すのだが…楽譜の書ける音楽の話は譜例がなかったら始まらないと思うのだが。
読了日:01月25日 著者:ジャン・ボワヴァン
 暗い越流 (光文社文庫)の感想
暗い越流 (光文社文庫)の感想葉村晶、いよいよ殺人熊書店員となる。シリーズではないけれど、「狂酔」が面白かった。南治彦シリーズも最後にもう一ひねりというのがしつこくもあり、サービス精神ともいえるだろうが微妙なところだ。
読了日:01月26日 著者:若竹 七海
 ジャズからの出発 (1973年)の感想
ジャズからの出発 (1973年)の感想50年代には「ジャズを推し進めて世界革命が起きる」とまじめに考えていたのだろうか。とするとこれは赤軍派にも匹敵する妄想である。銀巴里のセッションというのがYouTubeに上がっていたので聞いてみたがお寒い限りで、日野皓正が光っているくらいで山下洋輔にしろ菊地雅章にしてもおぼつかない。高柳昌行に至っては…山下洋輔は「まともなジャズ」では勝負できないのがわかってフリーに「逃げ」、そこへまともな渡辺貞夫が帰ってきた。この本はむしろ演歌・歌謡曲論の方が面白い。結局ジャズの理解できなかった著者の本だという気がする。
読了日:01月31日 著者:相倉 久人
 さよならの手口 (文春文庫)の感想
さよならの手口 (文春文庫)の感想面白かった。特に最後の一ひねりは洒脱である。ただ、長編をもたせるための骨格になる謎がすっきりしていない。なるほどこれですべての説明がつく、というカタルシスに欠けるのだな。ディテールはいつものハムラもので、楽しませてくれるが…しかしハードボイルドとはいいながら怪我の多い探偵である(笑)
読了日:02月04日 著者:若竹七海
 現代音楽史-闘争しつづける芸術のゆくえ (中公新書, 2630)の感想
現代音楽史-闘争しつづける芸術のゆくえ (中公新書, 2630)の感想大変勉強になった。私の「現代音楽」の時間はせいぜい80年代で止まってしまっており、そのあとの40年近くを駆け足で取り戻すのに本書は大変よい助けであった。私自身の創作は80年代から細々と続いてはいたがそれは主にジャズやポップスの世界においてであり、その後の現代音楽の展開にはあまり興味を持てないでいた。この40年間が「現代音楽」にとって豊かな時代であったかというのは簡単には答え得ない質問であろうが今でも70年代的感性しか持ち合わせない私にとってある種の「開き直り」をさせてもらうのに、本書は大変助けになった。
読了日:02月12日 著者:沼野 雄司
 錆びた滑車 葉村晶シリーズ (文春文庫)の感想
錆びた滑車 葉村晶シリーズ (文春文庫)の感想再読ですが、やっぱりなにかしっくりこない。話がだれてくると探偵を無茶な窮地に放り込む。サブストーリーの一つ二つはいいのですが、それがどうも有機的なつながりが感じられない。最後の謎解きも凝ってはいるがとってつけた感がどうしても残る。この小説に関しては微妙であります。
読了日:02月26日 著者:若竹 七海
 不穏な眠り (文春文庫)の感想
不穏な眠り (文春文庫)の感想面白かった。掌編というのか、このくらいの長さが葉村モノには適しているのではないか。こちらが老齢化で長編を追いきれなくなっているだけかもしれないが。
読了日:03月01日 著者:若竹 七海
 レキシントンの幽霊 (文春文庫)の感想
レキシントンの幽霊 (文春文庫)の感想再読である。村上春樹さんの短編・中編はどれも好きなのだが、「めくらやなぎと、眠る女」が、言葉の細かいディテイルまで彫琢されたことがよくわかり、読んでいて快い。
読了日:03月06日 著者:村上春樹
 哀しい予感の感想
哀しい予感の感想この小説が書かれた1988年には、アメリカに居て、父の容体がよくないことを聞かされて夏には一時帰国、葬式をすませてまたもどったのだった。時代の空気感というものはありますね。初読だが、これについていくにはもう歳をくい過ぎた。
読了日:03月09日 著者:吉本ばなな
 あすなろ物語(新潮文庫)の感想
あすなろ物語(新潮文庫)の感想いまさらという感もあるが再読である。主人公は一貫しているが掌編集といった方がいいだろう。最後の終戦後の物語が、結局自分の体験に一番近いこともあってか面白かった。
読了日:03月14日 著者:井上 靖
 日本人とユダヤ人 (角川文庫 白 207-1)の感想
日本人とユダヤ人 (角川文庫 白 207-1)の感想70年代のヒット作を再読。批判本が出たくらいで、インパクトのある本であった。ユダヤ人という鏡(まったく平らではない鏡だが)に映してみて日本人はどう見えるのかという実にユニークな視点で、「日本教」という概念を提示した画期的な書物だったと思う。ユダヤ人とその歴史についての記述が不正確ということはあるかもしれないが、それを持って本書の日本人とその文化に対する発見が無になるものではないと思う。50年を経て日本人理解の切り口は古びてはいない。
読了日:03月19日 著者:イザヤ・ベンダサン,Isaiah Ben-Dasan
 日本の詩歌 (9) 北原白秋 (中公文庫)の感想
日本の詩歌 (9) 北原白秋 (中公文庫)の感想本棚の奥で未読になっていたのを引っ張り出してきた。白秋でも意味の取れないところが結構あり、この本の注釈は大変参考になった。「若きロテイの物思い」のロテイがPierre Lotiとはこの本に教えられた。
読了日:03月25日 著者:北原 白秋
 日本教について (文春文庫 155-1)の感想
日本教について (文春文庫 155-1)の感想再読である。本多勝一さんへの最初の手紙は確かに「失礼」かもしれないが、内容的には本質をついている。明らかに虚偽とわかる情報についてもそれが一旦「踏絵」になってしまうと是認する「証拠=証言」を山のように集めてくる。異なる証言の間を分析して真実にせまることができなくなる。日本教の日本教たる所以で、これは21世紀になっても令和になっても変わらない。実体語・空体語のモデルはモデルに過ぎないが実に秀逸なモデルである。昨今の事例に当てはめてベンダサンさんの説明が聞きたいところだ。
読了日:03月29日 著者:イザヤ・ベンダサン
 「法華経」を読む (講談社現代新書)の感想
「法華経」を読む (講談社現代新書)の感想面白いが紀野さんの御説であって「法華経を読む」という題名が正しいかどうかは疑問である。「人間は、自分で自分にきめた生きざまというものがある。それを破りたくはない。…いつでも絵に描いたようにすっきりと生き、そして死にたいものである」なんてのは、いっちゃあなんだが、それがもっとも離れるべき「欲」ではなかろうか。一方、紀野さんが戦後に非道な命令を受けて上官を斬りに行こうとするエピソードなんかは面白い。人間を見る思いがする。いずれにせよ私なぞ「智なきもの」なので箸にも棒にも掛からぬようだ。これを縁なき衆生という。
読了日:04月10日 著者:紀野 一義
 福家警部補の挨拶 (創元推理文庫)の感想
福家警部補の挨拶 (創元推理文庫)の感想以前、檀れいさんの主演のテレビドラマを見て記憶にあった。刑事コロンボの舞台を現代日本に移し、主人公を風采の上がらない「女性」刑事にしたところが工夫である。倒叙であるから犯人はわかっている。それを地味な福家警部補がじわじわと捜査を進めていかに逮捕に持ち込むかが興味の中心である。「あと、もう一つ」というのもコロンボ風だ。おんぼろの車にのる代わりにいつも警察手帳をごそごそとカバンのなかで探していたりする。最初の出会いで実は犯人がわかっていた、というのもコロンボ流ですな。面白く読みました。
読了日:04月17日 著者:大倉 崇裕
 社会人1年目からのとりあえず日経新聞が読める本 (「やるじゃん。」ブックス)の感想
社会人1年目からのとりあえず日経新聞が読める本 (「やるじゃん。」ブックス)の感想経済形ハウツー本の中ではまともなものでお勧めするにやぶさかではないが、株式投資をすすめておいて、でも自己責任で、というのは当然と言えば当然だがいかがなものか。定期預金を選ぶという戦略もあり得ると私は思います。この手の本の宿命としてどんどん古くなるのが難点。ツボは押さえているのでこれを片手に最新の日経新聞を読めということでしょうな。2016年時点の情報で構成されているが、この時はコロナのことなんか予想もつかなかったですよねぇ。
読了日:04月19日 著者:山本 博幸
 とにかく散歩いたしましょうの感想
とにかく散歩いたしましょうの感想小川洋子さんは確かに岸本佐知子さんと通底するものがある。旅行の時など、大事に際してささいなことが気になるのはとてもよくわかる。そのささいなことに神経を集中して大事をやり過ごそうとしているとご本人も気が付いておられるがおそらくその通りだろう。外出嫌いも我が意を得たりと思うところである。めったやたらにアウトドアな人が理解できないが、まぁ人それぞれということでもあろう。
読了日:04月20日 著者:小川 洋子
 さいはての彼女 (角川文庫)の感想
さいはての彼女 (角川文庫)の感想こういうのがライトノベルというのでしょうか?何か引っかかるものがまったくないのがいいようなつまらないような。
読了日:04月25日 著者:原田 マハ
 ジョーカー・ゲーム (角川文庫)
ジョーカー・ゲーム (角川文庫)読了日:04月30日 著者:柳 広司
 わたし、定時で帰ります。(新潮文庫)の感想
わたし、定時で帰ります。(新潮文庫)の感想仕事にどこまでエネルギーを注ぐかという問題を扱う。残業、サービス残業、有休取得しない、休日出勤、果ては何日も徹夜。インパール作戦まで持ち出して無茶な仕事ぶりが糾弾される。自分のことを想えば、時代もよかったし、会社にも余裕があったと思う。熱があればさっさと帰って医者に行けと言われたし、最高月間残業時間は60時間、サービス残業はもちろん、残業そのものはなるべくやめるようにという社風であった。さらに企画という仕事が決まった時間を消費するという性格のものではなかったことも大きい。あ、小説としては面白かったです。
読了日:05月07日 著者:朱野帰子
 マーブルな女たちの感想
マーブルな女たちの感想また、小説のふりをしているが小説でないものを読んでしまった。最後まで読んだのだから特に苦情はないのだが、何か小説らしくない。そこがいいのだろう。「文学」を求める向きにはおススメしない。
読了日:05月09日 著者:きじまはるか
 青の炎 (角川文庫)の感想
青の炎 (角川文庫)の感想よくできた倒叙ものなのだが、何より主人公が漱石「こころ」の登場人物の心理が理解できないという点に非常に共感するものである。ホントあの「先生」という人は理解を超えている。漱石は好きだが、「こころ」はよくわからないといわざるを得ない。
読了日:05月11日 著者:貴志 祐介
 逆ソクラテス (集英社文芸単行本)の感想
逆ソクラテス (集英社文芸単行本)の感想何度も「歩」君の心理描写を繰り返してクライマックスに至る手法は面白かった。これが評価されるのも本屋大賞ならではというところか。
読了日:05月20日 著者:伊坂幸太郎
 大統領の密使の感想
大統領の密使の感想何度読んだかわからないが、昭和46年の初版だから最初によんだのは中学生の時だろう。驚くことにほとんどのギャグ・くすぐりの類を覚えていることである。伝奇小説のパロディであるが、B級サスペンスの要所をきっちり押さえているところがさすが小林信彦である。アレン・スミスのプラクティカル・ジョークの話や、戦後の闇市の話など関係ない脱線が楽しい。小林信彦さん自身「落語の笑い」がベースにあると書かれているから、私の笑のセンスも結局そのあたりに基礎をおいたことになる。
読了日:05月20日 著者:小林信彦
 日中戦争―和平か戦線拡大か (中公新書 133)の感想
日中戦争―和平か戦線拡大か (中公新書 133)の感想1931年の満州事変から1945年の日本の敗戦に至るまで、日中間の戦争の動向を淡々と記している。日本が中国大陸に侵攻することで中国の人々の生活にどのような影響を与えたかといったミクロな話はひとまず置かれているきらいはあるが、死者数、傷病者数、そして日本に連行された中国人の話など読み進むにつれ、日本が何をしたのかが明確なイメージをもって立ち上がってくる恐ろしさがある。日本が韓国、満州、蒙古、そして中国にどれだけの被害を与えたのかを今一度確認するのに便利な小史である。
読了日:05月21日 著者:臼井 勝美
 大統領の晩餐 (角川文庫)の感想
大統領の晩餐 (角川文庫)の感想本作のテーマは求道小説と中華料理。猫探しもテーマのひとつであるが、この点はあまり掘り下げられていない。東映映画・日活映画に関する蘊蓄も語られている。1972年作品だが、1972年というのは私にとっては沖縄返還と六文銭の年であり、ある種のターニングポイントであった。オリジナルの表紙はおなじ絵柄だがもっと淡い色遣いである。
読了日:05月22日 著者:小林 信彦
 合言葉はオヨヨ (角川文庫 緑 382-6)の感想
合言葉はオヨヨ (角川文庫 緑 382-6)の感想再々読くらいだ。これに先立つ「大統領の密使」「大統領の晩餐」にくらべて脱線が少ないのがややさみしいのと、プロットに凝りすぎてわかりにくいのが難点だが、多少は残っている脱線部分はとても楽しい。週刊朝日にこのような遊びの多い小説が連載されていたというのも不思議だ。時はこれもまさに1972年、沖縄返還と六文銭の年である。
読了日:05月27日 著者:小林 信彦
 秘密指命オヨヨ (角川文庫 緑 382-7)の感想
秘密指命オヨヨ (角川文庫 緑 382-7)の感想これも再々読くらいだと思う。サスペンスであり観光小説であるので、テンポが今一つだが、ところどころにある脱線が面白いのでそこを楽しみに読むことになる。作者はヨーロッパ各地、南はモロッコまで取材旅行をされたようだが、それが1972年。作中にすでに日本からのパックツアーが描かれているので、そろそろエコノミックアニマルの本領発揮といった時期だったのであろう。
読了日:05月30日 著者:小林 信彦
 ノルウェイの森 上 (講談社文庫)の感想
ノルウェイの森 上 (講談社文庫)の感想再読だが、ほとんど忘れていた。要は、一にセックス、二にセックス、三にセックス、4に自殺、自殺、自殺、5に二股、という小説である。くだらないとは言わないし、洒落た会話や名言もちりばめられているが、要するにそういうことだ。
読了日:06月03日 著者:村上 春樹
 38万人の仰天 (中公文庫)の感想
38万人の仰天 (中公文庫)の感想1982年作品。私が初めて大阪という魔界の地に足を踏み入れたのが1981年。当時の風俗・気分が活写されていて、その興味で読み直した。思えば大阪へ行って(1年間ではなかったが)配偶者をつれて東京に戻ったのは主人公の草薙と同じであるな。
読了日:06月07日 著者:かんべ むさし
 ムーン・リヴァーの向こう側 (新潮文庫)の感想
ムーン・リヴァーの向こう側 (新潮文庫)の感想平成7年作品。ラブ・ストーリーはともかくとして、丹下健三=鈴木俊一による「町殺し」という小林信彦さんの持論がはっきり展開されている小説である。「深川」とか「川向う」とかのキーワードから東京の成り立ちも語られる。江戸の北の郊外に育った私には遠い世界だが、東京を多少知るにつけ興味深い。
読了日:06月09日 著者:小林 信彦
 イーストサイド・ワルツ (新潮文庫)の感想
イーストサイド・ワルツ (新潮文庫)の感想再読。平成7年の「ムーンリヴァーの向こう側」に先立つこと2年、1993年作品だが、どちらも中年男が年下の女性といい仲になるというおとぎ話めいた設定であり(いや、世の中にはそういうこともあるらしいが)、女が深川生まれで「川向う」と川の西側の物語であるという点も同じで、この二作は双子のようによく似ている。本来の東京の「下町」「山の手」を記録しておきたいという作者の意図がよく表れており、また成功していると思う。
読了日:06月10日 著者:小林 信彦
別にWordでなくてもいいのだが、デジタルで(ワープロで)作られた文書をわざわざ印刷して、その上に手書きで朱を入れるという行為のむなしさを強調したい。それをやると、その手書きの修正を、まただれかが元のデジタルファイル(ワープロにしろDTPソフトにしろ)に打ち込みなおさなければいけない。
最初から朱を入れる人がデジタルな修正を直接かければこの二度手間は省ける。確かに印刷された紙に手書きで直すということのメリットもあるとは思うが、Wordをはじめとして校閲記録が残せるソフトウェアがある以上、それを使った方がいいのではないか。文章が固まったら、InDesignでもLatexでも、Wordよりはるかに優れたDTPソフトに流し込んだらいいだろう。
直接関係ない話だが、マイノリティに気配りのない無神経なワード族(Windows)が相手の都合も考えずにワードファイルを送りつけてくる問題については、相手がそのフォーマットに対応しているかを確認してから送るのが礼儀だろうし、その方が結局早いだろう。ただ、ビジネス界ではWindows=MS-Wordが非常に普及しているので、MacはPagesがワードを読めるようにしているそうだ。
