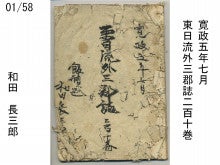四.転換点としての大津皇子の変
 (大津皇子の墓ー鳥谷口古墳)
(大津皇子の墓ー鳥谷口古墳) 六七二年に近江朝を斥け、壬申の乱に勝利し、天武は畿内大和に倭国を再興し、大和朝廷をここに開朝したに関わらず、その三〇年後の七〇一年、大和朝廷は大宝を建元し、天智が呼称した日本国と改める。正史編纂もまた倭国を再興した天武が計画したが、成立を見たのは日本国の天智を顕彰する正史であった。そこでは天武紀が大書されるも、倭国再興の誉れは壬申の乱とされ、天武は「賊」扱いされ、持統の父・天智皇統が正統とされている。それゆえ歴代皇統の位牌を祀る京都の泉涌寺には、天武系七代の天皇位牌はない。(天武陵↓)

天武は天智皇統の近江朝を斥け大和朝廷を立ち上げた。その大和朝廷の皇統への変質なしに、倭国から日本国への転換はありえない。その契機はどこにあったのか。六八六年天武が崩御するや持統は称制を引き、六九〇年に即位するも、六九六年に孫の文武に禅譲する
ところで、『日本書紀』は幕引きされ転換記事を記さない。しかし、唐の正史・『旧唐書』日本国伝は、
 (←天智陵)
(←天智陵)
「倭国は自らその国名を嫌い、日本と改称した」と日本国の言い分を記す一方、「日本はもと小国、倭国の地を併合した」と記す。この『旧唐書』の後者の知見が確かなら、事件は天武崩御の六八六年から七〇一年の間にあったはずだ。簒奪は隠してこそ誉れとなるなら、六八六年の天武崩御に連続する大津皇子の変の末尾が「この年、蛇と犬がつるめり、しばらくして共に死す」とあるのは大いに注目されよう。蛇は出雲王朝の、犬は「倭は呉の太伯の後」とされた九州王朝の嚆矢となった金印国家・委奴(イヌ)国のトーテムであることに気づくなら、その意味は天武体制である九州・出雲連合をここに粛清したことを、これは寓意するものだ。この大津皇子の処刑と前後して持統と藤原不比等の政治の表舞台への登場が始まる。ここに持統から文武への道筋がつけられ、その十年後、高市を除き、持統からの文武への禅譲をうたい『日本書紀』は閉じる。その文武は天武の孫だが、大和朝廷がこのとき尊重したのは持統を介して文武に流れた天智皇統の血統であった。ここに一度は六七〇年に天智が日本国を標榜するも挫折した夢を、天智と鎌足の子である持統と不比等がその血統を戴き、七〇一年に日本国を成就したわけだ。

の変の痕跡は、何一つないかに見える。しかし、正史がその倭国から日本国への転換を、持統の称制と即位の裏に隠したように、飛鳥の大津皇子の変の粛清現場は、大化改新の粛清現場に姿を変え、これ見よがしに公開されている。飛鳥寺裏の入鹿の首塚(写真)が大津皇子の処刑場なら、その飛鳥寺と向きあった甘橿丘の裾野から蘇我邸宅跡が発見を見たが、それは大津皇子の物部氏の邸宅で、そこから山辺皇女は髪を振り乱し、裸足で走り出て大津に殉じたのだ。そして飛鳥名物の石舞台古墳は通説は蘇我馬子の古墳とするが、真実は壬申の乱で、東国の物部氏を糾合し、近江朝に苦杯を舐めさせた物部連雄君の古墳が墓暴きされ、無惨な姿を晒すが、それが自然崩落にあったように観光客は見ている。
この大津皇子の素性を隠すために、『日本紀』を改竄し、現在の『日本書紀』は成立するが、系図一巻は紛失していた。その大津の母・大田皇女の父を『日本書紀』は天智とする。しかし、大田と大津に加え、その姉・大伯皇女はこぞって大を誇っており、出雲王朝源流の大洲(おおくに)の大氏の流れにあったことを証言する。ここに指示表出による実証史学の危うさがあり、私が幻想表出による幻想史学を提唱する理由がある。その大氏は八岐大蛇(やまたのおろち)退治により、また大国主命も国譲りにより共に出雲を追われ、その末裔は共に東の畿内大和を新天地とした。三輪山周辺の唐古遺跡や纏向遺跡はこの大氏一族に加え、九州の倭(やまと)を追われた出雲系皇統の饒速日命(ニギハヤヒ)により拓かれたから、その地を大倭(おおやまと)と呼ぶのだ。
その大氏と結ばれた物部氏に、蘇我氏に九州を追われた物部守屋の子・物部連雄君があり、彼は壬申の乱で東国の物部氏を組織した大功によって、戦後、物部氏の氏上となる。その子が大田皇女で天武の第一皇后であったことを『日本書紀』は隠した。つまり天武体制とは天武・物部体制で、その申し子・大津の次期皇位は誰一人疑う人はなく、姉の大伯も喜んで伊勢斎宮に下った。しかし、雄君に次ぐ、予期せぬ大田皇后の急死に伴い、持統の第二皇后の誕生で歯車は狂い、天武崩御に及んで持統は称制を引き、大津皇子の首は吹っ飛び、天武体制は崩壊する。
室伏志畔の大阪講演会
演題 大化改新の構造
日時 2017年9月9日13時
場所 天王寺の吉田ビル2F
阿倍野ステーションビルから谷町線沿いに150m、饅頭屋の隣り
連絡先8053046373 吉田安男まで