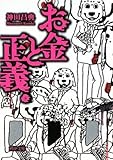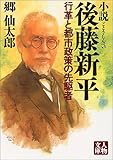スペンド・シフト
スペンド・シフト ― <希望>をもたらす消費 ―
posted with amazlet at 12.02.15
ジョン・ガーズマ マイケル・ダントニオ
プレジデント社
売り上げランキング: 22351
プレジデント社
売り上げランキング: 22351
著者は消費者行動の研究家ジョン・ガーズマ氏とフリーランス・ライターのマイケル・ダントニオ氏。ジョン・ガーズマ氏はTEDカンファレンスの講演者でもあります。
序文の執筆は「マーケティング・マネジメント」、「マーケティング3.0」のフィリップ・コトラー氏です。
訳者は「ブルーオーシャン戦略の」訳者でもある有賀裕子さんです。
<メモ>
・消費者は量より質、見た目よりも実質、謳い文句よりも実体験を重視している。消費者はすでにマーケティングの意図を見抜き、個人を企業と対等な立場に置く「つながり」やクチコミの力を味方につけている。
・世界的に新しい価値観に基づいて行動する「スペンド・シフト」の実践者が増えている
①不屈の精神:災い転じて福となす
②発明・工夫:自助自立に徹し、社会と自身の向上を追い求める
③しなやかな生き方:環境に順応できるつましい生き方を目指す
④協力型消費:協力をとおして問題を解決し、新たな選択肢を見つけようとする
⑤モノ重視から実質重視へ:これからは創意工夫が充実した生活への道である
・パタゴニアは製品の好ましい点とそうでない点を説明し、情報をガラス張りにすることで、誠実で信頼できる企業として歓迎されている。
・規模がビジネス上の優位性につながる時代は終わろうとしている。零細事業者は、顧客と納入業者と共通の利害や深いきずなを速やかに築くことにより、商売を繁栄させている。
・家計は今後、「有償」「交換」「無償」という三タイプの消費の併用によって成り立つだろう
有償:従来のあり方
交換:オンラインサービスの助けを借りた無償交換など
無償:修繕して使用価値を高める。友人、図書館から無償の助力を得る。
<感想など>
各国のスペンド・シフト実践者の比率が示されて、アメリカ55%、フランス53%、カナダ51%と比べて、日本は26%と中国と並ぶ低い比率です。
ただ、この本の原著が出版されたのは2010年なので、3.11以降の比率は上がっているだろうと思います。
日本でも、ソーシャルネットからの知人の情報を元に行動したり、商品の悪い点も公開するスーパーが人気になっているなど、この流れが広がってることを感じます。
2022―これから10年、活躍できる人の条件
2022―これから10年、活躍できる人の条件 (PHPビジネス新書)
posted with amazlet at 12.02.12
神田 昌典
PHP研究所
売り上げランキング: 6
PHP研究所
売り上げランキング: 6
今年1/19発売の神田昌典さんの最新作。
3章までWEB公開されています。
http://www.php.co.jp/2022/
帯の言葉:なぜ神田昌典は、「日本人(あなた)の未来は明るい」と言い切れるのか?
<メモ>
・日本は2020年まではまだいいが、その後は一気に下り坂。
・中国の勢いは、2020~2025年頃まで続く。
・東南アジア諸国が勢いづくのは、2030年ごろから
・世界経済の成長エンジンとなるアジアに生まれてきたのは、どれだけすごいことか。
・日本がアジアのリーダーであると自覚したとたん、世界は変わる!
・ドラッカーの「ネクスト・ソサエティ」で、NPOが社会の中核的組織になっていくと、予言していた。日本では2015年以降がNPO時代の夜明けではないか。
・情報を得るだけでは価値がなくなってきた。個人の気づきを世界に向けて表現することが大事。
・40代のビジネスパーソンは、これまで組織で働いてきた経験を生かし、イノベーションとホスピタリティの分野で組織を側面から支援する役割が生まれてくるのではないか。
・経営の効率性、サービスの革新性、顧客との親近感の3つは衝突しあう文化。会社の強みを明確にし、不得意分野については積極的にアウトソーシングすべき。
・定年後も働かなければならない時代では、40代になったら、ライフワークを自らはじめられる力をもつべき。
この本の1章にでてくる「70年周期説」。これは、米国でトップクラスのファンドマネージャーとして活躍する大竹愼一氏からひとつの指標として教わった、「日本経済は、70年周期でまわっている」という仮説だそうです。
新しい価値観は、圧倒的な欠落に気づいたときに生み出される。
1877年―西洋国家に太刀打ちできない中での国力の「圧倒的な欠落」
1945年―焼け野原の跡の物質の「圧倒的な欠落」
これから2015年までにも「圧倒的な欠落」気づくことになる。
それは、人間の心・可能性について何も知らなかったこと。
70年周期説に関する神田昌典さんの他の書籍も読んでみました。
2005年発売。大正デモクラシーの時代に生まれ、太平洋戦争を生き抜いた近藤藤太の激動人生。
近藤藤太の言葉:「戦争で命を投げ打ってくれた人たちは、自分たちの子ども、孫たちが、素晴らしい日本を創ってくれることを信じ、犠牲になった。そのことは、どんなことがあっても決して忘れてはいけない。その犠牲に恥じない世の中を、一人ひとりの日本人が創っていく責務があるんだよ。」
2015年に新しい時代がスタートすると考えると、ボクらがすべき行動の方向性がだんだんと見えてくる。まず分かるのは、その時代の主役は、今20~30代前後の団塊ジュニアを中心とする世代だろうということである。
2006年発売された作品に、著者による解説などが加えられて2009年に文庫本として発売された本。執筆時からすると未来となる世界を描いた小説です。
この本で著者が未来の物語を描いているのは、未来を予言する、というよりはシナリオ思考という、物語を書くことによって内的に自分自身を見つめるという思考ツールを使って、、問題を深く考えるためのようです。この本のシナリオ思考の解説を読むことによって、著者が「優しい会社」という小説を書いた意味、「全脳思考」でシナリオを作る意味、が少しわかった気がしました。
小説 後藤新平
小説 後藤新平―行革と都市政策の先駆者 (人物文庫)
posted with amazlet at 12.02.03
郷 仙太郎
学陽書房
売り上げランキング: 26696
学陽書房
売り上げランキング: 26696
東北に生まれ、台湾・満鉄の経営、関東大震災からの復興計画を推進した後藤新平の小説。著者は石原慎太郎知事のもとで東京都副知事の経歴をもつ郷仙太郎氏。
この本は1999年初版の小説ですが、東日本大震災の後、この後藤新平が再評価されています。
<メモ>
台湾統治
・当時三十六歳でアメリカにいた新渡戸稲造を、破格の待遇で迎え入れた
・軍政優先から民政優先に切り替えて、ゲリラに対して総督府を伝えることで大量に投降させた。
・清国が長年何度も試みて失敗している台湾全土の土地調査を実施し、税収二倍という効果を上げた。
・基隆港、鉄道、道路、上下水道整備、台湾銀行設立など様々なインフラ整備を行った。
満鉄経営
・狭軌だった線路を一年で全線広軌化した。この間、満鉄は一日も営業を休まなかった。
・大連港、大病院、幅50メートルの道路を含む都市計画を行った。
関東大震災からの復興
・入閣するなら日露国交回復を担う外務大臣でなければ意味がないと考えたところに、内務大臣での入閣要請を受けた。入閣要請は普通は二つ返事で承諾するものだが、後藤は返事をしなかった。そんな時に関東大震災が発生した。ここに至っては内務大臣だろうが無条件で入閣することにした。
・東京は、百年に一回は大地震に見舞われていることから遷都論が浮上したが、震災5日後に閣議に提出した「帝都復興の儀」で東京が首都であり続けることを明示した。その6日後に「帝都復興」の勅語が出され、天皇の名をもって「遷都」がないことが内外に明らかにされた。
<感想>
後藤新平はどの時代にも以下のことを実践しています。
これは現在でも通じる重要な考え方だと思いました。
①無私の心で良いと思ったことを信念を持って実行する。
②本格的な調査を実施し事実ベースで判断する。
③縁故・派閥によらず能力のみで人を登用し、評価する。
特に③の考え方は「ビジョナリーカンパニ2」の"最初に人を選び,その後に目標を選ぶ"と共通するところがあると思いました。
現在自分が台湾関係の仕事をしていること、祖父が終戦まで満鉄にいたこと、東日本大震災後のこの時期に読んだことで、個人的にもとても興味深かったです。