ヨーロッパ巡りの始点が、イタリアならば、その後の仏国のパリやら英国のロンドンの魅力が半減するような気がします。
例えば、初めにディズニーランドを入園したあと、翌日に地方の遊園地を行くと、その魅力が半減するようなものです。
丸ごと博物館のようなヨーロッパの旅巡りの終点は、イタリアが似合います。
イタリアは、それぐらい魅力的な国です。
昨日、福井県立美術館で開催されている「ミケランジェロ展 天才の軌跡」に見学に行って参りました。

今回のミケランジェロ展は、福井県立美術館の学芸員の方が企画立案したということで、開催場所は、東京と福井だけの二会場ということになったとのこと。
2013年6月28日~8月25日 福井県立美術館
2013年9月6日~11月17日 国立西洋美術館
今年は、イタリア・ルネッサンスを代表する三人の巨匠の展示会が、奇跡的に日本で開催されました。
ラファエロ展とダ・ヴィンチ展は、東京のみでの開催・・今回のミケランジェロ展は、例外的に福井開催ということでした。
おそらく、このような展示会は、二度と無いとのことでした。
そのせいか、県外からの美術ファンの来場者も大変多かったです。
開催から50日未満で既に6万人を超えたようです。

さすがに、ミケランジェロの彫刻や天井画や建築物を、日本まで持ち運ぶのは不可能です。
実際の展示品は、素描の習作や現物の手紙が多く、システィーナ礼拝堂の天井・壁画の傑作「最後の審判」がプリントされた薄い布地のレプリカやカラー写真で説明されたものがあり、ミケランジェロが何を意図して描いていたのかと分かりやすく説明していたのは、ヨカッタ!!
勿論、展示会場内は、写真撮影禁止です。
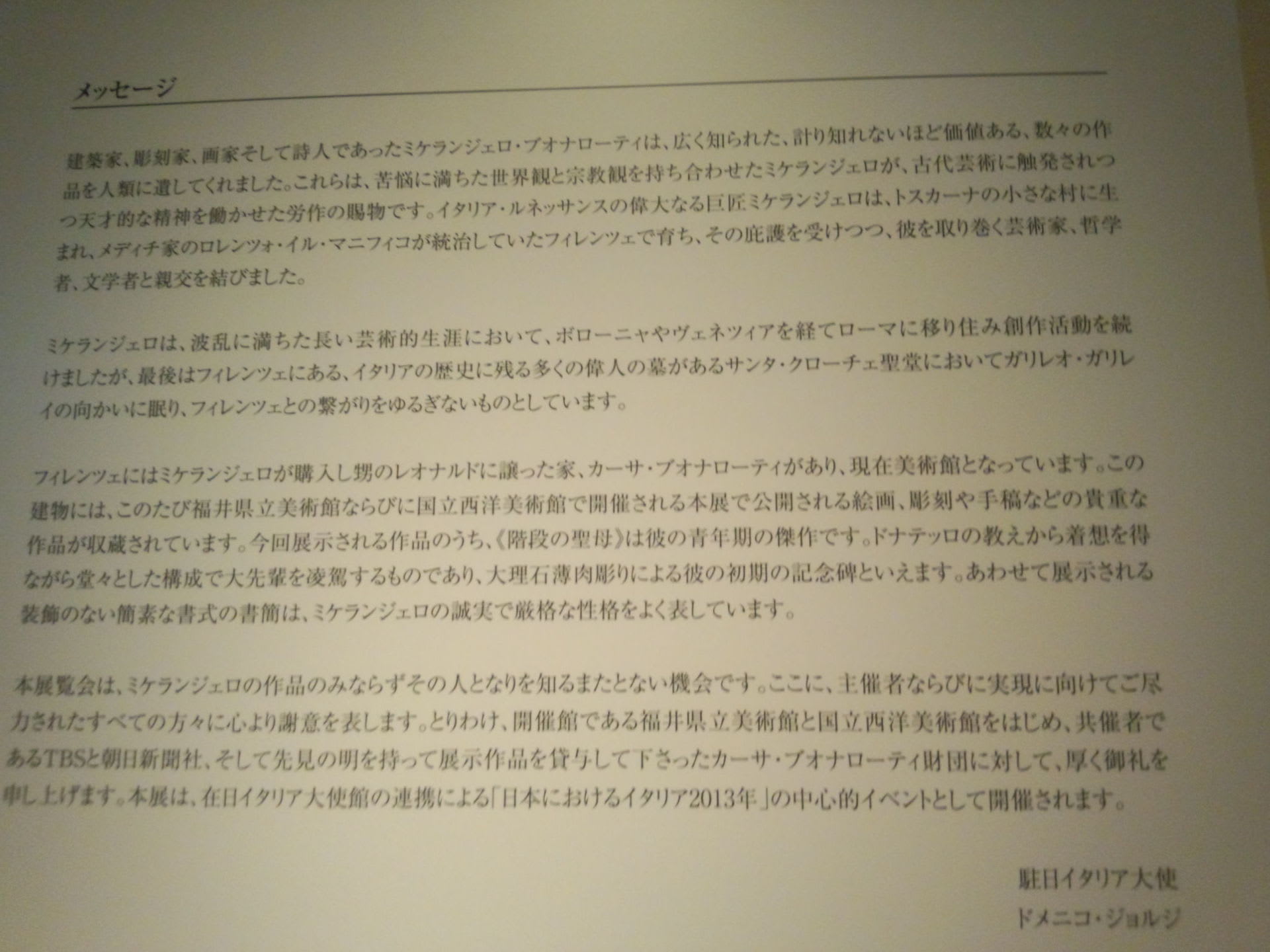
今回のミケランジェロ展の目玉作品は三点・・世界一美しいと言われる「レダの頭部」素描習作。
ミケランジェロが15歳の時の作品、大理石のレリーフ「階段の聖母」・・日本初公開の門外不出作品。
ミケランジェロの最後の作品と言われる・・木彫りの「キリストの磔刑」。
ミケランジェロの最初と最後の頃の作品が、展示会の出口に置かれてあるのが、とても印象深いものがありました。

今回のミケランジェロ展・・なかなかよかったです。
それよりも、福井県立美術館の学芸員の企画力に感心しました。
地方でも、こういうことが出来るんだという「実行力」と「運営力」です。
・・見倣いたいものです。

神のごときの芸術作品を生み出したミケランジェロ。
・・陰気、情熱的、偏屈、孤独だったミケランジェロの言葉です。
「わたしは金持ちになったが、けれど始終貧乏人の暮らしだった」
