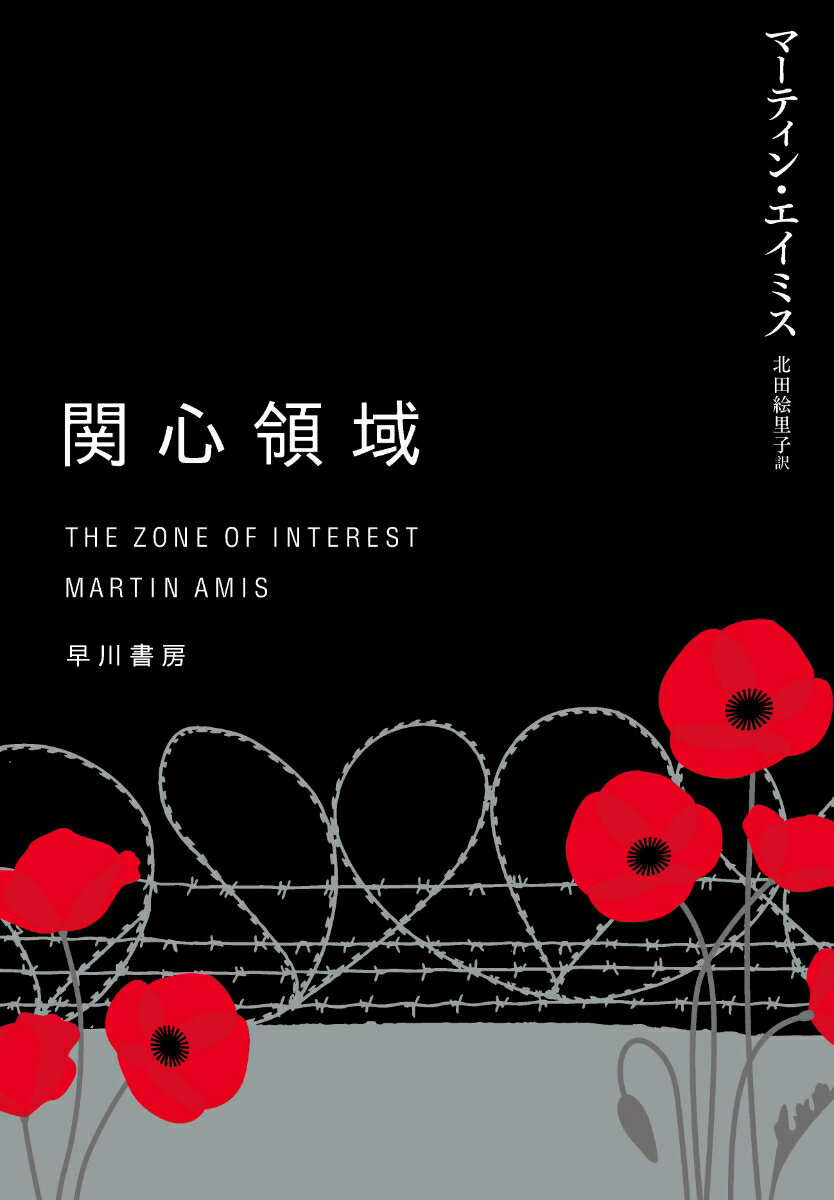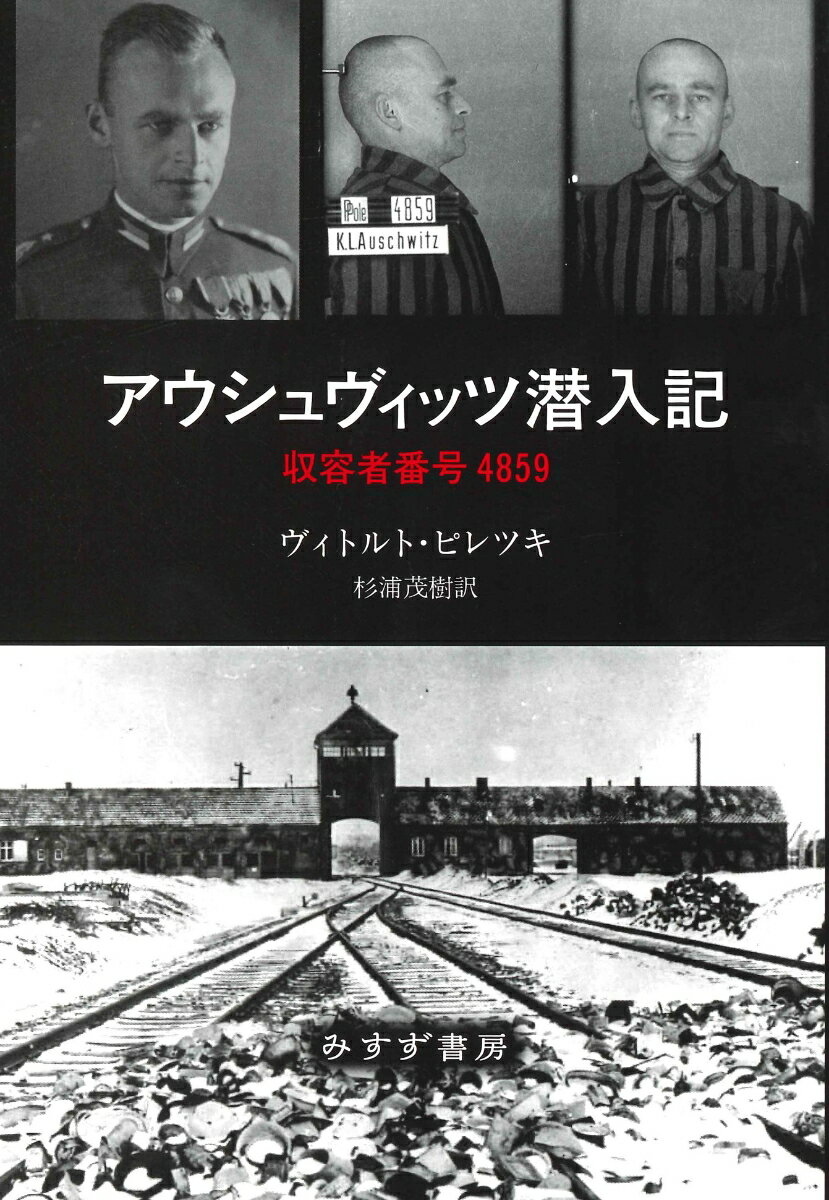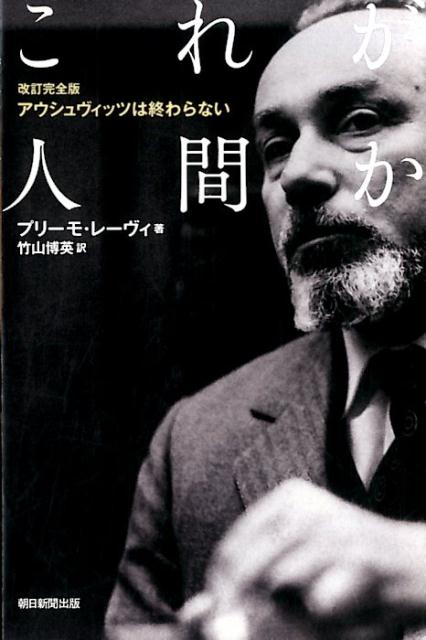予告で「無関心と言う恐怖」「目をそらすな」という文字に、観ないといけないのではと思いました。
《あらすじ》公式サイトから
空は青く、誰もが笑顔で、子どもたちの楽しげな声が聞こえてくる。そして、窓から見える壁の向こうでは大きな建物から煙があがっている。時は1945年、アウシュビッツ収容所の隣で幸せに暮らす家族がいた。第76回カンヌ国際映画祭でグランプリに輝き、英国アカデミー賞、ロサンゼルス映画批評家協会賞、トロント映画批評家協会賞など世界の映画祭を席巻。そして第96回アカデミー賞で国際長編映画賞・音響賞の2部門を受賞した衝撃作がついに日本で解禁。
マーティン・エイミスの同名小説を、『アンダー・ザ・スキン 種の捕食』で映画ファンを唸らせた英国の鬼才ジョナサン・グレイザー監督が映画化。スクリーンに映し出されるのは、どこにでもある穏やかな日常。しかし、壁ひとつ隔てたアウシュビッツ収容所の存在が、音、建物からあがる煙、家族の交わすなにげない会話や視線、そして気配から着実に伝わってくる。その時に観客が感じるのは恐怖か、不安か、それとも無関心か? 壁を隔てたふたつの世界にどんな違いがあるのか?平和に暮らす家族と彼らにはどんな違いがあるのか?そして、あなたと彼らの違いは?
《感想》
スタートからインパクトがある映画だった。何も映像がなく、段々音だけが聞こえてくるのだ。
この作品は「目で観る」というよりも「耳で聞く」映画だ。繊細に聞き耳を立ててほしいという監督の意図がある。
1945年、アウシュビッツ収容所の隣に、幸せそうに暮らす家族は収容所所長一家だった。映像は所長一家の日常生活がメインだ。画面の奥に見えるレンガ塀一枚を隔てた向こう側、煙突から出る煙、始終どこかから聞こえてくる叫びや不穏な物音によって、隣で何が行われているのかを想像させる映画だった。
壁の向こうから声が聞こえたりするが、訳されてないので、私にはわからない。わからなくて良かったのであろうと思うのだ。
囚人や暴力を見せることはない。
私はアウシュビッツ収容所のことをあまり知ってないことに気づかされた。私も無関心だったのだ。
よくわからないまま、映画が終わってしまい、調べることにした。
ジョナサン監督は、この映画を通して「われわれはなぜ学んでこなかったのか? なぜ同じ過ちを繰り返すのか? ということが最も訴えたいこと」だった。
監督は「ホロコーストは80年前に起きた出来事であり、歴史で、現代とは関係ない話だというふうに見せるつもりはなく、いまこの現代にちゃんと訴えかけられるような作品になるようにフレーミングしたかったんです。」と言う。
監督は、「人間の原始的な性質である暴力性や、加害者のなかにある我々との共通性について語ることでした。彼らは異常者ではなく、段階的に大量殺人者となった普通の人々であり、自分たちが直接手を下すのではなくその犯罪行為からは大きく隔たっていたために、自身を犯罪者とは思っていなかった。壁の向こうで起こっていることに対する彼らの無関心、世界の恐怖を切り離して無視することは、自身の贅沢と安定を保つためであり、そういった傾向は、わたしたち自身に共通するものでもあるわけです。それこそが本作を今日の観客に関連づける鍵でした。」と話す記事に出会った。
監督は、「わたしたちは暴力に頼ること、そうした思考と負の行動から進化する必要がある。そこから抜け出せないとは思いたくありません。しかし、それに対処しなければならないのは社会ではなく、ひとりひとりです。個人的に思うのは、わたしたちは自分を被害者として見て、他人を加害者として見る傾向があるのではないかということ。それはわたしたちをどこにも導かないでしょう。誰もが加害者になる可能性はあるし、そのとき我々は何を選択するのか。それを考えなければならないと思うのです。」と話していた。
『「黙認」すると、最終的にどこに行き着くのかということを極端な例で示したつもりでいます。ヘス家は野心あふれるブルジョワの一家ですが、彼ら家族の中に自分を見出すことができれば、そうした黙認や共犯関係が続けば最終的にどこに行き着くかということに合点がいくと思います。頭で考える作品ではなく、体でずっしり感じる作品にしたつもりです。もう二度と口にしたくないような、苦味を感じてほしい。』との思いで作られていることを知った。
可能な限り真実に近づくことが大切だったからアウシュビッツの隣で撮影したのだという。
妻のヘートヴィヒは、このような環境でありながら塀があったからでしょうか?理想的な暮らしであったようだ。なので、夫から昇進と転勤になることを聞かされると、ここを離れたくない。単身赴任してくれとお願いし、私と子どもたちはここで生活したいと言うのだ。
確かに、素敵なお庭でしたし、家も申し分ない大きな家だったし、近くに川が流れていて、アウシュビッツ収容所の隣でなければ、素敵だなと思う。
ベートヴィヒは、虐殺されたユダヤ人が着ていた服を何も感じなく着ることができ、そして、ポケットに入っていた口紅も試せる程だった。
子どもたちもここでの生活に慣れているようだった。
優越感に浸れる生活だったのかな⁈
疑問を持たずに生活することの怖さを感じる。
サーモグラフィー映像でりんごを地面のあちこちに埋めていく少女が映し出される。アウシュビッツの囚人たちのために行っているのだ。この少女は実在のモデルがいて、アレクサンドラ・ビストロン・コロジエイジチェックという人物だ。アレクサンドラは監督がポーランドでリサーチを重ねている時に出会った当時90歳の女性。12歳の時に彼女はポーランドのレジスタンスの一員として、度々収容者にこっそりと食事を与えていたというのだ。
監督は「私たちに似た人間でも、簡単に残虐な行為に及ぶ恐ろしさを伝えている。そんな中アレクサンドラは人間にも善意が残ってると示してくれた。そんな彼女の存在に救われたような気がした」と物語の唯一の希望の光として描いたアレクサンドラの姿に、平和への願いを込めたことを明かしている。
ぴあアプリ 「池上彰の映画で世界がわかる!」の記事より抜粋
《戦後、ここの施設にユダヤ人を送り込む責任者だったアイヒマンはイスラエルによって逮捕され、死刑になりますが、裁判が始まると、本人は「命令を実行しただけ」と弁解。まるで小役人のような態度に世界は驚きます。
この裁判を傍聴したアメリカ・ニューヨークの大学教授だった哲学者ハンナ・アーレントは、アイヒマンに“悪の凡庸さ”を見出します。平凡な人間が思考停止によって悪を実行するものだと指摘したのです。
アイヒマンのことを極悪人だと思っていたユダヤ人たちは猛反発しますが、アーレントの指摘は、誰でも思考停止すれば極悪人のような犯罪に手を貸すことになるというものでした。この映画を観ると、強制収容所で働く軍人たちや、その家族たちの様子は、まさに“悪の凡庸さ”そのものです》と書いてあった。
誰もが思考停止すると極悪人のような犯罪に手を貸してしまうのか。誰もが加害者側になるのだということ。考えることを怠ってはいけないことを教えてくれた映画だったのですね。
最後の靴の山の展示の映像かおぞましかった。
死んでいい人なんていなかっただろうに。
エンドロールの音が耳にこびりつき、音がトラウマになりそうだった。
心が落ち着いたら、『シンドラーのリスト』を観てみようかなと思う。