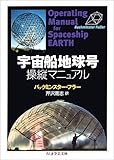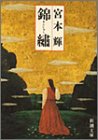朝起きると、体中が痛い。
腕も脚も腰も肩も。
ふと、翌日に筋肉痛?
大体、一日遅れでやってくるのに、
この時ばかりは翌日。
嬉しいのか体がバカになっているのか。
でも少しだけ若返ったような気がして嬉しかったりもする。笑。
そんな喜びもつかの間。
集合時間まであと30分。
朝ごはんは途中のコンビニで済ませるとして、
急いでホテルを出発。
到着したのが二分前。
この日は月曜だったにもかかわらず、
昨日よりも人が多く、おそらく60人ぐらいいました。
一番人手がいりそうな家に行く事になり、
横浜からきていた方の車に乗せてもらい、
また、旧警戒区域へ。
その日のお宅は納屋に溜まった泥と流されて壊れた家財道具の搬出。
体力の無さを痛感しながら、
泥を掬って、袋に詰めて、ネコ(一輪車)で空き地へ捨てに行く。
ほんの少し膨らんでいる程度にしか見えなかったのに、
いざ袋に詰めていくと、何十袋にもなり、
積み上げられた土嚢袋をみると、
復興の遠さを肌で感じます。
休憩は30分に一回。
一回の作業時間が短すぎるような気もするが、
初めてボランティアに参加する自分のような人間にはそれくらいで
ちょうどよかった。
というのも、
作業することに夢中になり過ぎるあまり、
休憩する事を忘れてしまうからだ。
実際、一日目なども適度に休憩があったものの、
自分自身の体力と相談しながら作業をしないと
ばててしまう上に、倒れてしまいそうにもなる。
そうはいっても、
やはり、なかなか自分ひとりだけ休んでしまうと言うのも
居心地が悪い。
だから、
小刻みにみんなで休憩する必要があるのだと思う。
休むたびにペットボトルを一本消費するような
炎天下での作業にも終わりが見えてきた。
腰を上げて周りを見渡せば
着た時とは全く違う景色になっている。
けれど、
達成感はどこにもない。
結局一件の家の出来る限りの作業が終わっただけで、
そこで暮らしが始められるわけでもないし、
それで後は自分たちで出来るわけでもない。
二日間で行った三軒の家の他にも
まだまだボランティアを待っている人たちがいる。
その他にも、
行政の力を借りなければ出来ないようなこともあるし、
街としての『これから』を『これまで』以上にすることで、
そこに住む人たちのモチベーションをあげていくことも必要だろう。
先が見えるようでまるで見えない。
だからと言って暗くなる必要はないし、
踏み出す足を止めるわけにもいかない。
淡々と歩き続け、
復興していかなければならない。
今回初めて参加したボランティアと言うものは、
私感でいえば、『人助け』ではない。
単純作業であり、それらを粛々と行っていく。
評価も労いも感謝も達成感も伴わない。
ひたすら目の前にある物事を片付けていくだけ。
そこにあるのは無常感に近いかもしれない。
ここら辺の言葉の整理はまだできていない。
けれど、
復興はまだまだだという事。
出来る事は微細でも構わないと言う事。
その二つを自分の中に確かなものとして
捉える事が出来ただけでも今回の行動は
起こしてよかったと言える。
この後。
どうする?自分?
腕も脚も腰も肩も。
ふと、翌日に筋肉痛?
大体、一日遅れでやってくるのに、
この時ばかりは翌日。
嬉しいのか体がバカになっているのか。
でも少しだけ若返ったような気がして嬉しかったりもする。笑。
そんな喜びもつかの間。
集合時間まであと30分。
朝ごはんは途中のコンビニで済ませるとして、
急いでホテルを出発。
到着したのが二分前。
この日は月曜だったにもかかわらず、
昨日よりも人が多く、おそらく60人ぐらいいました。
一番人手がいりそうな家に行く事になり、
横浜からきていた方の車に乗せてもらい、
また、旧警戒区域へ。
その日のお宅は納屋に溜まった泥と流されて壊れた家財道具の搬出。
体力の無さを痛感しながら、
泥を掬って、袋に詰めて、ネコ(一輪車)で空き地へ捨てに行く。
ほんの少し膨らんでいる程度にしか見えなかったのに、
いざ袋に詰めていくと、何十袋にもなり、
積み上げられた土嚢袋をみると、
復興の遠さを肌で感じます。
休憩は30分に一回。
一回の作業時間が短すぎるような気もするが、
初めてボランティアに参加する自分のような人間にはそれくらいで
ちょうどよかった。
というのも、
作業することに夢中になり過ぎるあまり、
休憩する事を忘れてしまうからだ。
実際、一日目なども適度に休憩があったものの、
自分自身の体力と相談しながら作業をしないと
ばててしまう上に、倒れてしまいそうにもなる。
そうはいっても、
やはり、なかなか自分ひとりだけ休んでしまうと言うのも
居心地が悪い。
だから、
小刻みにみんなで休憩する必要があるのだと思う。
休むたびにペットボトルを一本消費するような
炎天下での作業にも終わりが見えてきた。
腰を上げて周りを見渡せば
着た時とは全く違う景色になっている。
けれど、
達成感はどこにもない。
結局一件の家の出来る限りの作業が終わっただけで、
そこで暮らしが始められるわけでもないし、
それで後は自分たちで出来るわけでもない。
二日間で行った三軒の家の他にも
まだまだボランティアを待っている人たちがいる。
その他にも、
行政の力を借りなければ出来ないようなこともあるし、
街としての『これから』を『これまで』以上にすることで、
そこに住む人たちのモチベーションをあげていくことも必要だろう。
先が見えるようでまるで見えない。
だからと言って暗くなる必要はないし、
踏み出す足を止めるわけにもいかない。
淡々と歩き続け、
復興していかなければならない。
今回初めて参加したボランティアと言うものは、
私感でいえば、『人助け』ではない。
単純作業であり、それらを粛々と行っていく。
評価も労いも感謝も達成感も伴わない。
ひたすら目の前にある物事を片付けていくだけ。
そこにあるのは無常感に近いかもしれない。
ここら辺の言葉の整理はまだできていない。
けれど、
復興はまだまだだという事。
出来る事は微細でも構わないと言う事。
その二つを自分の中に確かなものとして
捉える事が出来ただけでも今回の行動は
起こしてよかったと言える。
この後。
どうする?自分?