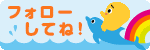さて、いよいよ懸案の長編小説の書き直しに入る。
この長編は、ほとんどをこのブログにも投稿したので、読んで下さった読者もおられると思いますが、ブログには長すぎて、投稿しなかった部分が幾つかありす。ちょうどニュージーランド映画の話を書いた折、登場人物のひとり、マオリのジャンリュック・ケバウの話から未発表部分を投稿させて頂きたいと思います。では……
* * *
「カウリ松の原生林は半島の中ほど、低い山々の連なりから俺がよく行く釣り場のあたりまでを覆ってるんだ。カウリ松はカリフォルニアのセコイアと並んで地球上で最も大きく寿命の長い樹だよ。現存する最古のカウリ松は樹齢二千年と推定されてる。日本にも屋久島の杉とかがあるんだってね。
カウリ松はラテン語ではアガテイス・オーストラトスっていうんだ。この松がなぜ絶滅に瀕しているか話しておきたいんだ。
この松は樹齢が重なると下の方の枝が落ちて幹が真っ直ぐ垂直に伸びるのさ。そこで、最初にニュージーランドに来たヨーロッパ人、おもに英国人たち。中でもロイヤル・ネーヴィーがこの樹に眼をつけた。幹が真っ直ぐなこと。その丈の高さ。材質の堅牢で均質なとこが船材として理想的だった。とりわけ真っ直ぐで長い幹は帆柱にうってつけというわけさ。船腹に張る板としても長い一枚板が取れるからこれ以上最適な樹はない」
「ヴァイキングの末裔のしわざか」
ジャンヌ・マリーが小声で叫んだ。
「最初は毛皮目当てのアザラシ猟の小舟の修理所や製材所がたちまち大きくなり、川から海へ伐採したカウリ松の幹を流すため川を塞き止め、貯木場までできたさ。こうして、この国の北半分を覆うようにして生えていたカウリ松の原生林は、たちまちのうちに切り尽くされてしまった。ほかの松や杉と違って絶滅に瀕するまでに至ったのは、ほかならないこの樹の成長が他の樹と比べて極端に遅く、材木として使えるまでに最低百年、成熟するのに八百年という途方もない時間がかかるためなんだ。人間の寿命や、人間の産業活動、社会活動のペースと極端に隔たってるために松や杉のように植林してもらえず、人類の文明世界から隔絶した所でゆっくりと成長し成熟し、森の王者として幸福なほど太陽光線と温帯の風とを享受していたところへ、ある日突然、人間どもが斧を持ってやって来て、つぎつぎと切り倒して行ったんだから。人間の産業活動が性急すぎてカウリ松が子孫を残すことが出来なかったんだね。今は、俺が鱒釣りに行ってた森は国が保護森に指定して伐採を禁じたので、かろうじて絶滅は免れているがね」
「人類の発生前の植物なんだね」
李君が言葉を挟んだ。
「カウリ松の森は遠くから見ると、灰色がかったまっすぐな幹を紺青の天に向かって並べ、梢ちかくの枝と葉を互いにからみ合わせて人間の攻撃から最後に残された種の存続を必死に守ろうとしてスクラムを組んでいるように見えるよ。まだこの樹についてあるんだ」
ケバウは、喋り疲れたのかふっと息をついた。
「なぜこの松が絶滅に瀕しているか知ってるかな?」
「ラテン語と絶滅と関係あるみたい」
頭のいいイザベルが答えた。
「そのとおり。アガテイスって名はメノウを思わせるだろ。メノウに似た物質とカウリ松との絶滅と関係あるんだ。
ケバウはなおも喋り続けた。
「この松の樹脂は、カウリ・コパールといって幹を伝って根元の地中に貯まり、そこに石化してちょうどコハクのような鉱脈を成していたのさ。マオリの原住民たちは生の樹脂を口で噛んで唾液と混ぜ、松明の油にしたり、顔や身体に模様を描く時の顔料に使っていた。ところが、これもやはりヨーロッパ人が眼をつけ、当時、ペイントとして貴重だったニスの原料として珍重されていた松ヤニが大量に地下鉱脈を作って埋まっていることを発見し狂喜したヨーロッパ人が、このカウリ・コパールを掘り出しに押し掛けた。そのすさまじさはちょうどカリフォルニアのゴールドラッシュほどだったというよ。最盛期には、この松ヤニ掘りだけで二千人も移住して来たというから。そして二・三十年で地中の松ヤニという松ヤニを全部掘り尽くしてしまったのさ。地下のコハク色の金脈がなくなって、失業した移民の多くは、平野に出てブドウ栽培を始めたそうだ。今では、ワインはカリフォルニアと並んでこの国の重要な外貨獲得源になってるけどね。コハク色のニスの原料が、ルビー色やコハク色の赤や白ワインに変わったってわけさ」
ケバウはどうやらいちばん話したかったことは話し終えたようだった。
「キャプテン・クックが植民地にした二週間あとにフランスの航海者が着いたのよ」
イザベルがまた学識を披露した。
「小さいけどフランスのコロニーもあるよ。ペタンクをやる老人チームがある」
「フランスはいつも遅れてばっかり」
ジャンヌ・マリーが自嘲をふくんで言った。
「さあ。自然を利用しつくす人間の欲望がカウリ松を絶滅寸前に追いやり、カウリ・コパールを掘り尽くしてしまった。あなたの祖国への郷愁と自然への愛情はよくわかるわ。でも、そろそろ核の話をはじめて」
ジャンヌ・マリーは優しくケバウを促した。
「そうか。でも、その前についでだから僕の故郷とフランスとの関係で忘れられない事件についてひとこと」
ケバウはなかなか譲らない性格だ。
「十年前のフランスの核実験の時は、グリーンピースの連中がオークランドを基地として阻止行動をやった。当時のフランスの社会党政府は秘密諜報員を派遣してグリーンピースの行動を探った。若いフランス情報局の男女がニセの夫婦に化けて諜報活動するなんて映画そこのけをやったんだよ。潜水服を着た工作員がオークランド港に係留してあったレインボオワリアーの船底に水中から爆弾を仕掛けて爆破したんだ。運悪く船に戻ったカメラマンが死んだってことはみんな知ってるね。信じらんないことだが、フランスは権威を守るためには、ときどきトンマなことをやるよ。ね。そうでしょう。シャノワール先生?」
ケバウはシャノワール先生の顔を覗きこんで挑発的に言った。先生は頭を昂然とそらし、口を真一文字に結んでケバウを睨むと、言い返した。
「トーゼンじゃない。国益を守るのが権力を委ねられた人間の仕事なんだから。あの時の実験はフランスはじめ先進自由主義国の平和と安全を守るために必要だったわよ。偶然が災いして一人の人間が死ぬ事故になったのは残念だったけど……」
「さあ。もうこの辺で、今日の本題に入りましょうよ」
ジャンヌ・マリーがまたケバウをうながした。