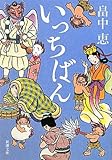最近読んだ本から。出張に行くと行き帰りに本が読めます。
まずこの二冊から。
消費は生産力人口の絶対数とリンクする、と。そう言われてみればその通りですね。
マクロだけではなく、「北海道」「札幌圏」でも検証ができそうです。
自分でもよく手に取ったもんだ、と思います。
物理学の本。
私、ごりごりの文系です。高校の時、最後の物理のテストは16点でした。
「確信する脳」
事業再生をするときにまず、
「絶対出来る!」と確信をするところから始まります。しかし、その「確信」って何?と言われると非常に心もとなくて、説明ができない状態です。
この本を読んで、「確信ができるメカニズムはこういうことです!」というヒントが欲しかったのですが逆によくわからなくなってしまいました… ^^;
今年の私の自由研究テーマ、「仏教と神社」の一環です。
今年途中からむくむくと大きくなってきた、事業承継ニーズへの興味。この本を一読すると、本気で承継をするためにはここまでやらなくてはいけないのか…?ということが理解できます。事業承継も来年にかけての研究テーマになります。(事業承継、ほとんど事業再生と内容がかぶります。詳細は別記事書きます)
ちょっと一息。
まずこの二冊から。
消費は生産力人口の絶対数とリンクする、と。そう言われてみればその通りですね。
マクロだけではなく、「北海道」「札幌圏」でも検証ができそうです。
角川書店(角川グループパブリッシング)
発売日:2010-06-10
経済変動を人口構成の変化でうまく説明する藻谷氏の新著です。
今のデフレや不況をうまく説明するのは「労働力人口の減少」と明示され、改めて納得しました。
前著の「実測!ニッポンの地域力」でも明らかでしたが、これを北海道にあてはめれば大体の景気動向は解ってくるのではないでしょうか。
そこからちょっと発展させて商圏を仮定して(例えば石狩市は独立した商圏ではなく、札幌圏、など)今後数十年の人口動態予測と重ねれば小売業、飲食業など、個人消費関連の産業のマーケット規模は大体解るのではないでしょうか。
今のデフレや不況をうまく説明するのは「労働力人口の減少」と明示され、改めて納得しました。
前著の「実測!ニッポンの地域力」でも明らかでしたが、これを北海道にあてはめれば大体の景気動向は解ってくるのではないでしょうか。
そこからちょっと発展させて商圏を仮定して(例えば石狩市は独立した商圏ではなく、札幌圏、など)今後数十年の人口動態予測と重ねれば小売業、飲食業など、個人消費関連の産業のマーケット規模は大体解るのではないでしょうか。
自分でもよく手に取ったもんだ、と思います。
物理学の本。
私、ごりごりの文系です。高校の時、最後の物理のテストは16点でした。
幻冬舎
発売日:2010-09-28
文系の私にとって「素粒子」「強い力・弱い力」「暗黒物質」などちんぷんかんぷんもいいところ。
でもこの本を読んで解ったのは、「2000年以降、物理学では『何が解らないのか』がわかってきた」ということ。
宇宙の総重量のうち、元素が占める割合は「4%」で残りのうちほとんどが何でできているかわからない…とか。
知的刺激を受ける本です。
でもこの本を読んで解ったのは、「2000年以降、物理学では『何が解らないのか』がわかってきた」ということ。
宇宙の総重量のうち、元素が占める割合は「4%」で残りのうちほとんどが何でできているかわからない…とか。
知的刺激を受ける本です。
「確信する脳」
事業再生をするときにまず、
「絶対出来る!」と確信をするところから始まります。しかし、その「確信」って何?と言われると非常に心もとなくて、説明ができない状態です。
この本を読んで、「確信ができるメカニズムはこういうことです!」というヒントが欲しかったのですが逆によくわからなくなってしまいました… ^^;
河出書房新社
発売日:2010-08-18
確信とはどこから来るのか。
記憶なのか。脳内物質が引き起こす感覚なのか。
遺伝により性格のうちかなりの部分は決定されます。その一方で生まれた後の学習で行動が変わるのも事実です。
脳が常に正しいか?というとそうでもなく…与えられた情報により脳は「思いこむ」。また、その時に正しく記憶していたことも後でどんどん改変する…
スペースシャトル事故のとき、どこで何をしていたか、を書きとめてもらい、それを2年後に本人に見せる、という実験をしたところ、過半数の人が「これは正しくない。別の場所で別のことをしていたはず」と答えたという実験にはなるほど、と思いました。「これは間違いなく私の書いたものですが本当ではありません」と答えた人もいたということです。
そうなると、コンサルタントの私の分野にかぶってくるものは、「必ずできる」「やりぬくことができる」という確信がどこからわいてくるのか、そしてその根拠は?という部分です。
そしてそれの正体は、
「不明」
確信を持ってコンサルに当たる、というその大本の部分が「不明」?
こちらの分野も引き続き研究が必要ですね。
記憶なのか。脳内物質が引き起こす感覚なのか。
遺伝により性格のうちかなりの部分は決定されます。その一方で生まれた後の学習で行動が変わるのも事実です。
脳が常に正しいか?というとそうでもなく…与えられた情報により脳は「思いこむ」。また、その時に正しく記憶していたことも後でどんどん改変する…
スペースシャトル事故のとき、どこで何をしていたか、を書きとめてもらい、それを2年後に本人に見せる、という実験をしたところ、過半数の人が「これは正しくない。別の場所で別のことをしていたはず」と答えたという実験にはなるほど、と思いました。「これは間違いなく私の書いたものですが本当ではありません」と答えた人もいたということです。
そうなると、コンサルタントの私の分野にかぶってくるものは、「必ずできる」「やりぬくことができる」という確信がどこからわいてくるのか、そしてその根拠は?という部分です。
そしてそれの正体は、
「不明」
確信を持ってコンサルに当たる、というその大本の部分が「不明」?
こちらの分野も引き続き研究が必要ですね。
今年の私の自由研究テーマ、「仏教と神社」の一環です。
小学館
発売日:2010-10-01
仏教について、サンガ新書であたらしい発見をし、苫米地氏なら仏教をどう見るのか、と思い買ってみました。
意識、思考の抽象化という背景に宗教を置いてみると…
すでに「この世は不確定」というところで宗教は死んだ、とします。
釈迦が説いた仏教の姿も明らかにします。
意識、思考の抽象化という背景に宗教を置いてみると…
すでに「この世は不確定」というところで宗教は死んだ、とします。
釈迦が説いた仏教の姿も明らかにします。
今年途中からむくむくと大きくなってきた、事業承継ニーズへの興味。この本を一読すると、本気で承継をするためにはここまでやらなくてはいけないのか…?ということが理解できます。事業承継も来年にかけての研究テーマになります。(事業承継、ほとんど事業再生と内容がかぶります。詳細は別記事書きます)
すばる舎
発売日:2009-12-18
事業承継をやるならここまでやってみろ、という本です。
綿密に造られた計画を数年かけて実行されています。
事業承継を考えておられる経営者の方におススメです。タイトルのように「ここまでできますか?」
綿密に造られた計画を数年かけて実行されています。
事業承継を考えておられる経営者の方におススメです。タイトルのように「ここまでできますか?」
ちょっと一息。
新潮社
発売日:2010-11
おなじみ畠中さんの「しゃばけ」シリーズの中の1冊です。文庫で発刊になったので買いました。
若旦那を始め登場人物もなじみですし安心して楽しめる一冊です。
若旦那を始め登場人物もなじみですし安心して楽しめる一冊です。