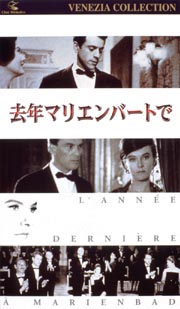「去年マリエンバートで」

1961年6月25日フランス公開。
1964年5月2日日本公開。
フランス・イタリア合作映画。
1961年ヴェネツィア国際映画祭金獅子賞受賞。
脚本:アラン・ロブ=グリエ
監督:アラン・レネ
キャスト:
- A - デルフィーヌ・セイリグ
- X - ジョルジュ・アルベルタッツィ(ジョルジョ・アルベルタッツィ)
- M - サッシャ・ピトエフ
- 淑女たち - フランソワーズ・ベルタン、ルーチェ・ガルシア=ヴィレ、エレナ・コルネル、フランソワーズ・スピラ、カリン・トゥーシュ=ミトラー
- 紳士たち - ピエール・バルボー、ヴィルヘルム・フォン・デーク、ジャン・ラニエ、ジェラール・ロラン、ダビデ・モンテムーリ、ジル・ケアン、ガブリエル・ヴェルナー、アルフレッド・ヒッチコック

ストーリー:
主人公の男Xは、女Aと再会する。Xは去年マリエンバートで会ったと語りかけるのだが、Aは記憶していない。しかし、AはXの話を聞く内に、おぼろげな記憶を取り戻していく。Aの夫であるMは、「去年マリエンバートで」実際に何が起こったのか知っている。
あらすじ:
豪奢だが、どこか冷たいたたずまいを見せる城館に、今日も富裕らしい客が、テーブルを囲み、踊り、語って、つれづれをなぐさめている。
まるで凝結したような、変化のない秩序に従った生活。
誰も逃げ出すことの出来ない毎日なのだ。
この城館の客である一人の男が、一人の若い女に興味をもった。
そして男は女に、「過去に二人は愛しあっていた、彼は女自身が定めたこの会合に彼女を連れ去るために来た」と告げた。
男はありふれた誘惑者なのか、異常者か?女はこの突飛な男の出現にとまどった。
だが男は真面目に、真剣に、そして執拗に、少しづつ過去の物語を話して聞かせながら言葉をくり返し、証拠を見せる……。
女はだんだん相手を認めるようになった。
しかし、女は今迄自分が安住していた世界を離れることに恐怖を感じた。
それはやさしく、遠くから彼女を監視しているようなもう一人の男、多分彼女の夫である男によって表現される世界であった。
だが、彼女は、男によって、真実性を帯びてくるつくられた話に抵抗できず、ためらい、苦悩する。
今や苦悩は女の現実であり真実となった。
現在と過去はついに混り合った。
三人の間の緊張は女に悲劇の幻想さえおこさせたが、ついに女は男の望んだ通りの存在であることを受け入れ男とともに、何ものかに向って立ち去った。
それは、愛か、詩か、自由か……それとも死かもしれないのだが……。

コメント:
1961年公開のフランス・イタリア合作映画。
アラン・ロブ=グリエによる脚本をアラン・レネが監督したモノクロ映画である。
1961年、ヴェネツィア国際映画祭金獅子賞受賞。
現在と過去が交錯する幻想的な物語。
構図、美術、ココ・シャネルによる衣装、映像、全てが美しい。
「マリエンバート」というのは、チェコ語でマリアーンスケー・ラーズニェ(Mariánské Lázně)といい、チェコの首都・プラハの西方約130km、カルロヴィ・ヴァリの南にある温泉療養地である。
ヒロインを演じているデルフィーヌ・セイリグが実に美しい。

この人は、中東のレバノン生まれでフランスで活躍した女優。
余り知られていないが、レバノンというのは、中東一の美人の産地ともいわれている国なのだ。
興味のある方はこちらのサイトをご覧あれ:
この作品は、幻想の世界での男女の恋を描いているようだ。
1人の男の繰り返されるセリフを聴きながら、華麗に装飾された天井の、延々と続く長い廊下を進むカメラ。
この冒頭シーンで、レネ監督は我々を幻想の世界へ誘う。
綿密に計算して構成された物語をバラバラにして再構築した本作は、黒澤明の『羅生門』からイメージされた、3人の登場人物の“記憶”の違いを描くものだ。
しかしレネ監督は、1つのストーリーの一人称をぼかし、我々を混乱に貶める。
何が真実なのか?何が嘘なのか?しかしその真実も嘘も、いったい“何”に対してのものなのかさえ判らない。
ゴテゴテと装飾過多な暗い城(ホテル)の中と、幾何学的に整えられたシンメトリーの人工的な庭園の陽光、それらの対比が鮮やかな美しい映像。その城に集まる人々はまるで彫像のようだ。
「去年、マリエンバートでお会いしましたね」と、執拗にヒロインに思い出話を聞かせる男は、本当にヒロインがかつて愛した男なのか、それとも卑劣な詐欺師か、あるいは単なる勘違い男なのか?
覚えていない男の愛の言葉を聞くうちに何が本当か嘘か見分けのつかなくなるヒロインも、果たして本当に貞淑な妻なのか、不倫に燃える情熱家なのか、それとも男を手玉に取る悪女なのか?
“計算された迷宮”に迷い込む登場人物と、それを観ながら“混沌とした迷宮”に迷い込む観客。
おびえた鳥のように大きな瞳を見開き、肩を縮こませるヒロインの表情が眩惑的で、ますます虚実の判断がつかなくなる。
そんな中で、泰然としている夫の存在が何やら不気味だ。
いつも妻の愛人とゲームで勝つ彼は、針金のような容姿にもかかわらず、常に2人を上から見ている。
「真実」を知っているのはこの夫だけなのかもしれない・・・。
ではその「真実」はいったい何なのか?
そもそもこの登場人物は存在しているのか?
城に住み着く亡霊ではないのか?
我々が迷い込んだのは、虚実の迷宮ではなく、この世とあの世の境ではないのか?
だとしたら、この夫は黄泉の扉を開く番人なのではないだろうか?
そう考えると本作に漂う寂寥感の意味が解るような気がする。

何度か観てみないと真実が分かってこないような不思議な映画なのだ。
これぞ、『羅生門』の世界と同じ、高レベルなミステリー作品だ。
実に面白い!
脚本のロブ=グリエ自身の言によれば、黒澤明監督の『羅生門』に触発されて作られた作品である。
黒澤明がなぜこの映画を100本に選んだのかが分かる。
自分の映画『羅生門』がお手本になったと聞いたからだ。
黒澤明が「世界のクロサワ」と呼ばれる所以は、黒澤明の映画が世界中の映画人たちから注目され、多くの作品プロットが参考にされたからだ。
後年、脚本を担当したロブ=グリエがこの映画の仕掛けについて語っている。
それによると、黒澤明の『羅生門』がモチーフとなっており、最初に以下の脚本が作られたという。
- 現在
- Xの回想(Xにとっての主観的事実)
- Aの回想(Aにとっての主観的事実)
- 過去(客観的事実→Mの視点)
この4本の脚本をバラバラにつなぎ合わせて、最終的な脚本が完成した。
その際に、それぞれの場面が1から4のどの脚本に該当するのかがなるべくわからないように慎重につなぎ合わされ(時間軸の入れ替えも行われている)、最終的に完成した脚本はダイヤグラムシートを伴う、非常に複雑なものになった。
さらに、このダイヤグラムシートは一部のスタッフにしか知らされていなかった。
その為に、出演者はしばしば自分が何を演じたらいいのかわからず、混乱状態に陥ったが、それも全て内容をより効果的にするための計算であった。
ただ、服装やセットなどは明確に1から4の脚本で区別されていて、注意深く見れば、どの場面が1から4の脚本のどれに当たるのか判別できる仕掛けになっている。
結果として、ロブ=グリエ曰く「非常に緻密に計算された作品で、曖昧さのかけらもない」作品になったのだ。
このアイデアは、まさに『羅生門』だ。
京マチ子と三船敏郎と森雅之の3人の間で起こった事件の真相を巡って繰り返される疑わしい映像の展開。
事件の目撃者や関係者がそれぞれ食い違った証言をする姿によって深まる謎。
このミステリアスな映画が、欧米の映画制作者や映画ファンをいかに興奮させたことか。
その結果、1951年のヴェネツィア国際映画祭における金獅子賞を受賞したのだ。
『羅生門』のブログはこちら:
そして、その10年後、本作が1951年のヴェネツィア国際映画祭における金獅子賞に輝いたのである。
『羅生門』という映画がいかに世界で評価されたのかを裏付けるトピックスなのだ。
この映画は、TSUTAYAでレンタルも購入も可能: