2020年5月22日 5時35分 東洋経済オンライン

PCR検査を国民全員に受けさせるということの意味を考えてみよう。写真は中国・武漢(写真:REUTERS/Aly Song)
新型コロナウイルス禍に出口らしきものが見え始めたとたん、国民全体をPCR法その他で検査し、感染が疑われる人を隔離することで経済を立て直そうという提言が出てきた(小黒一正・関山健『新型コロナ・V字回復プロジェクト~「全国民に検査」を次なるフェーズの一丁目一番地に』5月)。
提言は、今の日本の問題は、ウイルス禍に対するに「命か経済か」の二者択一から離れられないでいるところにあるとする。だから、ここで大きな経済資源を投じて国民全体を検査する体制を整備し感染者を完全に隔離する体制を整えれば、非感染とされた人は安心して経済活動にいそしめるはずだ。つまり「命も経済も」という出口があるはずだ、そう主張するのである。
だが、すでに反論として書いたように(『「自由」を危機にさらす「全員PCR検査論」の罠』)、筆者はこれに反対である。理由は、検査と隔離だけでは感染爆発を止められないだけでなく、こうした提言が実施されたときに生じる自由あるいは人権への危機を予感せざるをえないからである。今回は、やや具体的に説明しよう。
個々人がどう動くか考えてみよう
あなたが、何かのきっけで新型ウイルスへの感染を心配する状況に至ったとする。すでにウイルス感染症への特効薬のようなものが開発されていて、それを処方してもらえばウイルスが完治する、あるいは、完治とまで行かなくても軽症化すると知っていたら、ぜひ検査を受けたいと望むだろう。検査結果が陰性なら安心するだろうし、陽性なら薬を処方してもらえるはずだからだ。
しかし、特効薬がなく陽性と出ても「隔離」されるだけとわかっていたら、あなたは検査を受けることを躊躇するのではないだろうか。決定的な治療薬がない状況での隔離は、あなたの命を守るためのものではなく、あなた以外の人の命を守るためのものでしかないからだ。
もちろん、家族や親密な友人たちがいて、あなたが彼らの命を守りたいと思えば、進んで検査を受けようとするかもしれない。しかし残念ながら、国民全員検査論者が頼りとするPCR検査の精度はあまり高くない。PCR検査が感染してしまっている人を非感染つまり陰性としてしまう確率は、検査を受けるタイミングにもよるが、20%とか30%もあるとされる。
これは、検査の仕方を改善すれば済むだけの問題ではない。このウイルスの潜伏期は10日から2週間にも及ぶと言われている。これに対して、このウイルス感染を検査が検知するのは、早くて発症の1週間前ぐらいからとされているからだ。検査で陰性と出たとしても、検査の数日後には自身が新たな感染源とならないことを保証するものでは「ない」のである。
だから、あなたが家族思いの人なら、あるいは社会の安全を何よりも重要と考える人なら、感染を心配せざるをえない状況であると感じた段階で、検査を求めるより「自主隔離」の道を選ぶのではないだろうか。社会を守るカギになるのは、検査結果により感染者を強制隔離する仕組みではなく、他者を感染させるリスクを最小化するための自律的行動なのである。
3月頃の話だったが、17歳の環境活動家グレタ・トゥーンベリさんが「ウイルスに感染したみたい、でも自分の国スウェーデンは希望するだけで検査を受けられる仕組みではないので、これから自主隔離に入ります」と書いて、一時、姿を消したことがあった。
筆者は気候変動リスクに関する彼女の主張の多くに強く賛同するものの、主張を表現するときの容赦なさのようなものにはやや引くところがあったが、これを知って気分が変った。この少女は、17歳にして、社会におけるモラルというものを知っているなと感じたからだ。
感染リスクの高い人ほど検査を受けない
検査を隔離と結びつけて運用し結果を出そうと考えるのなら、全国民PCR検査論が提唱するような「1~2週間に1度PCR検査(承認申請中の抗原検査を含む)」程度では、まったく不十分である。検査の直後に感染した人が次回の検査までに感染源となってしまう可能性を排除するためには1週に数度にわたる検査が必要なのである。
先の反論で、医療従事者や介護施設職員には3日か4日に1度はPCR検査を受けられる体制が与えられたほうがよいと書いたのは、検査を隔離と結びつけて運用するのなら、最低限そのくらいの検査頻度でなければ意味がないと考えたからだ。
付言すれば、筆者が望ましいと考えるのは、他者を感染させるリスクの中で働かざるをえない人たちが自律的な判断により職場からの隔離つまり自宅待機を選ぶことであって、全国民PCR検査論者が言うような感染疑惑者の隔離施設への全員収容などではない。しかし、自宅待機を選ぶこと自体が難しい人もいる。

ドイツでは都市封鎖に抗議する人を警察が拘束した(写真:REUTERS / Christian Mang)
思えば、職場からの物理的隔離に耐えられる人は恵まれた立場にある。筆者のように、パソコンとインターネットぐらいあれば講義もできるし論文も書けるという人間は気楽なものだ。だが、物理的に隔離された日常では仕事ができない人もいる。隔離により職場を離れることが家族の日常の崩壊を意味する人もいるはずだ。活動的で人に接することの多い仕事をしている働き盛りの人や若い人の家庭ほどそうなるはずだ。
そうした人たちにとっては、検査を受けて隔離施設に収容されることの悲惨さのほうが、感染して発症することの苦しみよりも大きいかもしれないのだ。それは、提案者たちが最も隔離したいと考えているはずの感染リスクの高い人たちほど、実は検査を受けたがらないという不都合な図式ができ上がることを意味する。
次の段階では「検査を受けない人を非難し強制する」
そこで何が起こるだろうか。筆者がおそれるのは、「希望者はすぐにPCR検査を」というキャッチフレーズが結果を出せなければ出せないほど、始めてしまったアクションを強化しよう、検査を受け入れない人たちを社会の敵として非難し、無理にでも受検に追い込もうとする動きが生まれることである。
提言の「次なるフェーズの一丁目一番地」といううたい文句にある「次なるフェーズ」は経済のV字回復につながるよりも、国民全員に「検査済み証明書」を携行せよと呼びかける全体主義的な精神運動になりかねないのだ。
今回のウィルス禍をきっかけに、20世紀の初め、具体的には第一次世界大戦中の1918年からから戦後の20年にかけて世界を襲い、大戦での死者1000万をはるかに上回る2500万から3900万ともいわれる死者を出したウイルス感染症、通称「スペイン風邪」を振り返る議論が出てきている。ちなみにスペイン風邪という通称は、大戦における中立国であったスペインからの情報が情報統制を行っていた参戦国よりも圧倒的に多く国際社会に流布したことによるものだが、そのことをここで論じようとは思わない。
この感染症の死亡状況は、実は欧米よりも衛生状態において劣位だったアジアにおいて深刻で、なかでも大英帝国に組み込まれていたインドでは、全世界の死者の約半数に達するほどの死者を出している。これに対し、日本は死亡者数を40万人程度と当時の欧米並みに抑えるという「成功」を収めている。
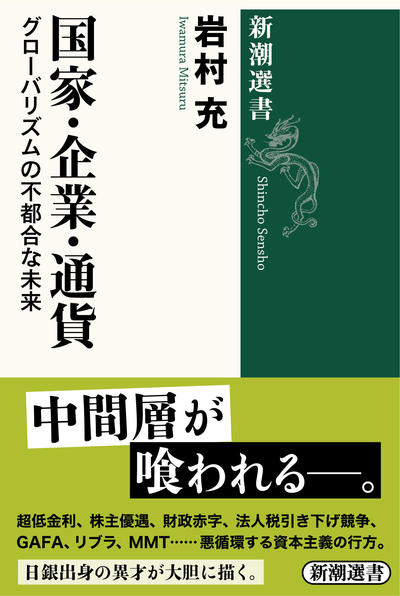
だが、それは良いことと悪いことの両方をもたらしたかもしれない。
もたらされた良いことは、感染症との戦いのためには官憲の監視ではなく、民衆における自律と自助が必要だということが証明されたことである。当時の日本は消化器疾患や結核などで毎年10万を超える死者を出していた。当時の医学では感染症に十分には立ち向かえなかったのだ。
そうしたなか、新しい脅威として登場したスペイン風邪に対して、いわば広汎な民衆運動として、マスクとうがいの励行そして感染者の早期隔離などの動きが広まった。新しい感染症は民衆を団結させたのだ。
だが、これは悪いことにもつながる。
明治以来の日本が経験した「戦争」の中でも、基本的に軍閥間主導権争いだった西南戦争や国外での支配権争奪戦争だった日清・日露両戦争と異なり、日本全国に現れた見えない敵であるウイルス感染症に対しては、民衆レベルでの「総力戦」が展開された。そのことが、その後の日本の国家のかたちに影響したようにも思えるからである。こうした経験が、国家権力と民衆の日常との精神的結合を生み、関東大震災や昭和恐慌の教訓ともあいまって、昭和の国家総動員体制の下敷きになっていったと考えるのは、歴史の見方としてシニカルすぎるだろうか。
「地獄への道は善意で敷き詰められている」
改めて断っておくと、筆者は、この感染症に対するのに国民全員PCR検査体制を提言する人たちを、それだけの理由で自由や人権を軽んじる人たちであると言いたいわけではない。しかし、この種の提言は、提言者がどう思っていたかということと離れて、予想もしなかった時代の「空気」を生み出しかねないことを忘れるべきではないことだけは警告しておきたい。
筆者がコロナ禍の直前に上梓した『国家・企業・通貨』では、コロナ禍については何も論じていなかったが、西欧世界にある「地獄への道は善意で敷き詰められている」という格言に触れておいた。感染症対策を論じる人たちには、今こそ、この格言の底にある歴史の教訓を考えてほしいと願っている。
出典:東洋経済オンライン
「会社四季報」は、「会社四季報オンライン」申し込みの上、お買い求め下さい。年間予約購読は3つのメリットがあります。1.ご自宅や勤務先に直接お届けします。2.買い忘れがありません。3.売り切れによる買い逃しがありません。東洋経済新報社 予約サービスセンター 0120-206-308 (受付時間:平日9:30-17:20)
----------------------------------------------------------------------
※投資の最終的な判断はご自身でお願い致します。
このブログに掲載の情報は、投資を保証するものでは一切御座いません。
連絡先:iso_investment@yahoo.co.jp