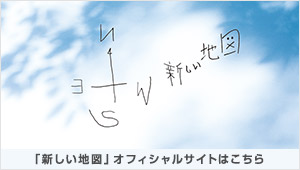くだらないことばかり書いて自分でイヤになる面があるけど、一方、ブログを利用して整理しておきたいという気持ちがある。誰でもかつて経験したことだけど、そういう体験を、今となって「よかった」と思うのだ。
8/4(土)ニュースカイホテルの幹事会会場では、彼女と同じテーブル。顔を見ただけでは誰なのか分からなくて、テーブルの上に置かれた出席者名簿を見て、「あっ」と思った。互いに予期していなかったはずだ。
「誰か分からなかった」と正直にそう告げると、「2年前に会ったでしょ」。
そうだった。2年前、同窓会の2次会、八代「白馬」で隣のシートに座って話をしたね。それが高校卒業してから初めての会話だった。そのときは突然に顔を合わせても何を話していいか分からず、やっぱり遠い存在だということを認識させられたようで、何だかさびしさと虚しさが残ったのだけど、それでも顔を合わせることができただけでもよかったのだ。
今回は始めから同じテーブルの隣同士に座って、彼女のスマホで娘や孫の写真を見せてもらったり、自然にプライベートな話をしたりして…。2人だけの世界にしばし浸った。
共通の友人であるリンゴ吉村くんが話題に上ったとき、彼女とがねの2ショット・写メを撮って、コメントなしのメールを彼女が送信した。リンゴと彼女はずっとつながっているのだ。送信終了の画面に「眞理子」という表示が目に入ったとき、まぁショックだった。文字が目に焼き付いた。
彼女とのことは遠い昔のことで、ホントにあったことなのかどうかさえ定かではない気がして、夢幻の如くなのだけど…。
がねが高校1年の同じクラスに気になるその娘がいて、独特の存在感を醸し出していた。おとなしくて誰ともあまり話をしない感じだった。映画のワンシーンのように、その娘がいると、他の人の顔が消えて、その娘の姿だけが浮かび上がる。それが毎日のように繰り返され、積み重ねられていた。クラスで友人と話をしていても、その娘の姿を無意識に探している。そんな状態が続いた。
しかし、ただ見つめるだけで、気軽に話をすることはなかったと思うのだけど…。この点は、「普通に話をしていたよ」と訂正されたけど。なにしろ夢幻だから。
それは思春期に特有のことだったのだろう。あるとき、発作のように感情が突然に湧き立った。一方通行で相手の都合など考えない、ストーカーのような感情だけど、なぜかしら、食事がのどを通らないなど、自分でも理解できない感情にどうしようもなくなった。ただ「好き」というだけの感情に支配されてしまって、自分をコントロールできなかった。繁殖期の動物と同じで、思春期に訪れるホルモンのせいだったのか。
その頃のがねは、全体に学校、世の中、家庭、いろんなものに背を向けていた。友達づきあいだけはあったし、ギターを弾き、好きな本を読んでもいたから、ましな方だったのかもしれないが、せつな的に生きていた。そして、自分が嫌いで、ましてや人を大切に思うことができるのかどうか疑わしいと思っていた。だから、一人の娘を好きでどうしようもないという自分の感情を知ったとき、自分にも人の血が通っているだと思った。
ある晩、彼女の自宅に出かけて行った。何をどう話するかなど何も考えず、ただ顔を見たかっただけの衝動的な行動だったろうと思う。玄関先で応接してくれる彼女に何やら訳の分からない話をして、すごすごと引き返してきた。
でも、がねがなぜ自分を訪ねてきたのかは、火を見るよりも明らかなことで、その後、彼女はそんことを表面上誰にも何も言わなかった。しばらくして、彼女から手紙が届いた。
そこには詩が書かれていた。今、思い出した。それは安西均の詩だった。それまでのがねが詩など読むはずもなく、「夜の帳が下り…」と読んでいくと、読み終わったときポロリと涙が落ちた。
直接に、好きだとか嫌いだとか書いてはない。彼女はがねを好きでも嫌いでもなかったのだろう。ただ、がねの気持ちを受け入れることにはならないということが示されていると感じた。これで終わった。それで涙がポロリ。
それから後は吹っ切れた。ただ、ここで橋渡しをしてくれたのが、リンゴ吉村くん。手紙を手渡してくれたのもリンゴ。リンゴは彼女とホントに親しい友達になった。がねはリンゴから彼女の消息を聞くだけになった。
高校生のとき、がねなんぞは相手の気持を考慮することなく、気分次第に自分勝手に行動しただけなのに、断わりの返事ではあったのだけど、優しく包み込むようにきちんと対応してくれたことを、今になって感謝する。
かつて好意を抱いた相手として、今は懐かしい思い出を胸に、特別に親しく話ができるようになったことをうれしく思う。彼女のそばにずっとまとわりついて話をして、彼女も楽しそうにがねに寄りそってくれた。
P.S.
果たして、つじつまは合ったのだろうか。