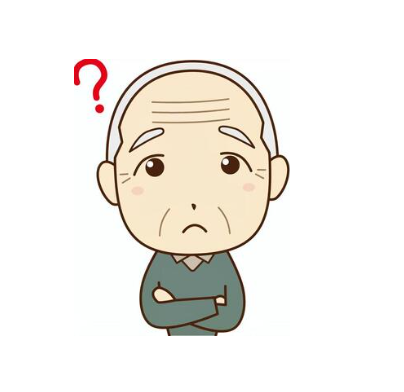久し振りにチョッと硬い話題:
少し前に「全地球史アトラス」は世界観の見直しをするくらいのインパクトがある事に付いて書いたが、今回はその内容に付いてもう少し書いてみる。
実は内容に触れようと書き始めたが全く筆が進まない。要するに65分のビデオを一回見たくらいでは大雑把なイメージしか把握していなかった訳で、もう一度見出したのだが解説に付いて行けない処が多く、何度も戻って見直しする事になった。何とか見終えて少しは理解が進んだものの、専門用語も多く矢張り完璧には程遠くて、素人が全てを理解するのは無理と諦め、私なりに気になったポイントだけを挙げてみる。
SD爺版「全地球史アトラス」ダイジェスト:
概要は地球の誕生、大気と海洋の誕生、陸地の誕生、有機物の誕生、生命・爬虫類・哺乳類等様々な誕生物語と、生物・恐竜・人類・地球等の色々な絶滅物語が次々と語られるのだが、もう少し個別に挙げてみる。
(紫文字は私が理解したビデオの内容だが、125億年のダイジェストなので、ポイントの列記だけでもかなり長くなってしまった。)
① 45億年前、天の川銀河が他の銀河と衝突し、星が爆発的に生まれ、その内の一つが太陽系となり、その中で微惑星の衝突で地球が生れた
② その後地球に衝突して来た様々な微惑星から炭素・窒素・酸素・水素が供給され大気と海洋が生れたが、当初は超酸性で重金属を含んだ海は生物がとても住めない猛毒の環境だった
③ 半径1000㎞クラスの微惑星衝突によりマントルが上昇し、プレートが沈み込む活動が始まり、海水が重金属を地下深くに運び海を浄化する一方、地震も起こる様になった(プレートテクトニクス)
④ 生命体の出現:地中の間欠泉でウラン鉱床からのエネルギーがアミノ酸や核酸塩基等を生み出し生命体へと進化した
⑤ 何度も繰り返される生物の絶滅メカニズムは:
銀河衝突による超新星爆発⇒宇宙線の増加⇒厚い雲の形成⇒太陽光の減少⇒全地球凍結及び大量の宇宙線被ばく⇒主要な生物の絶滅
⑥ 進化と絶滅は紙一重であり、絶滅の後には都度突然変異で新たな生物が栄える事になる
⑦ 生物の進化は秩序化の歴史だが、此れは「物事は放っておくと乱雑・無秩序・複雑な方向に向かい、自発的に元に戻ることはない」という物理の原則に逆らっている
(私の感想:この不思議な現象の理由は語られず、ミステリーのままである点は大いに気になる)
⑧ 酸素濃度増加のメカニズムは:
冷却する地球⇒海水がマントル深くに漏れる⇒海面低下600m(水漏れ地球と呼ばれる)⇒ 大陸・大陸棚増加 ⇒ 地球生命の温床化 巨大な河川・栄養分 ⇒ 酸素濃度の更なる増加
(私の感想:短期的には温暖化による海面上昇のリスクは大変怖いが、もっと長い時間軸で見ると海面は低下する様だ)
⑨ 植物大繁殖で酸素濃度は現代の1.5倍 ⇒ 植物が堆積して石炭となり人類の躍進に貢献
(私の感想:「大地の五億年」で語られた石炭として固定化されたCO2の開放による温暖化への悪影響という点は殆ど語られず、プラス面のみの表現となっている点は違和感も残る。人類も地球の歴史の一要素であり、躍進の後は衰退もある事を前提として、淡々と表現しているのかも知れない)
⑩ 人類進化のトピックス:
人類の脳の大きさが不連続に巨大化した時期が3回あり、HIRマグマという放射性物質を放出する大噴火のタイミングがこの3回と符合する
⑪ 人類の絶滅:
自己複製可能なAIロボットが、人間の限界を超えて進化し、生物としての人間の役割は終わりを迎える
(私の感想:人間とロボットを隔てる「意識」の本質が現代科学でも未だに解明されて居ない現状で、AIが「意識」を持つようになると決めつけて良いものか違和感は残る)
⑫ 水漏れ地球が更に進む ⇒ プレート移動を起こす潤滑油としての海水が足りなくなる ⇒ 核の冷却不足 ⇒ 地球磁場の消滅 ⇒ 太陽風で大気や海水が剝ぎ取られる ⇒ 生物絶滅 ⇒ 地表の温度は500度Cに
⑬ 80億年後、地球の消滅:
天の川銀河とアンドロメダ銀河の衝突で超新星爆発が起こり、膨張する太陽に地球は飲み込まれて消滅する。
⑭ 然しその時、生まれ変わったポスト人類が地球を脱出して新たな星を目指している(私の感想:プラス指向のメッセージで終えているのは、ビデオを見た人が絶望的にならない様にとの配慮とも思える。その為には⑪のAIロボットが人類に代わって繁栄する、という筋書きが必要だったのかもしれない。)
長くなったので、纏めの感想は次回に。