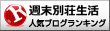(「秀庖(しゅうほう)」久我山岩通通り)
東京・久我山に住む囲碁トモのAさんが「餃子の旨い店がある、酢豚もいける」と地元の中華料理店を教えてくれた。「秀庖(しゅうほう)」という町中華である。
ちなみに、この手の店は「町中華」でなく「街中華」というのが適切な表現だと思うのだが、なぜか「町中華」が人口に膾炙しているのでその表現に従うことにした。
さっそく酒と餃子に目がないご近所の飲みトモBさんを誘って久我山まで行ってみた。
6時15分、この夜の一番乗りで店に入ると、奥の席に座ってテレビを見ていた老夫婦があわてて持ち場についた。なんだか団欒の場に踏み込んだ強盗のようでバツが悪い。
5分ほど遅れてBさん登場。まずは叉焼をツマミにビールで乾杯する。
(叉焼の下にはきゅうりがどっさり)
ビールは昔ながらのキリンラガーである。
「最近これが一番旨く感じるようになりました」
「若い時分はアサヒスーパードライが旨かったですよね」
「コクがあってキレもある」
「そうそう。今の私たちは・・・」
「コクもなければキレもない」
ああでもないこうでもない、ボケたりつっこんだりとしゃべり散らかしていると、厨房の中からご主人が笑いながら声をかけてきた。
「お客さんたちの話きいていると、なんだか漫才みたいだね~」
ほめられることが何より好きな二人組、さらに笑かしちゃおうとトークに一段とリキが入ったことは言うまでもない。
(この日のメイン焼餃子登場 町中華の餃子としては傑出している)
いつしか奥さんも話の輪に加わった。
鹿児島出身のお二人がこの地で町中華を始めたのが48年前のこと。ご主人は原宿「南国酒家」で修業をしたそうだ。つまり「秀庖」は広東料理店なのである。
「子供の頃南国酒家で揚げたバナナを水あめでくるんだヤツを食ったのを覚えてます」
「ああ、あれは料理っていうか、ちょっと違うんだけどね」
(広東料理の代表酢豚 旨し)
我々のトークに刺激されたらしく、ご主人も次第にノリノリに。
「48年、ていうとこの辺でも最古参でしょうね」
「そうだね。〇〇(昔ながらの和菓子店)とか、みんな店やめちゃったからね」
「これから先、いつまで店を続けたいですか」
「う~ん。・・・まあ今週いっぱいかな」
「・・・」
(なんだか家庭料理のような麻婆豆腐 四川風と違ってあまり赤くない)
「これを食いなさい、っていうお店のおすすめは」
「白いご飯。ザーサイで。中華鍋ふるわなくてすむから」
「・・・」
(無理やり中華鍋をふらせてカニ玉をこさえてもらった)
「店始めたころは岩崎通信機の社員さんが3000人いて、ザッ、ザッ、ザッって、その人たちの通勤の足音で目が覚めたの。昼も夜も大忙しだったね~」
そうそう、とうなづく奥さんはご主人の顔をじっと見ていた。
気がつくと時計は10時を回っていた。
この夜の客はハナから最後まで私たちだけ。
ただでさえ過酷な町中華である。老夫婦が店を閉じるの日はそれほど遠いことではないだろう。
ふと厨房を見ると、向こう側に座ったご主人がカウンターに指先を乗っけていた。中華料理店の職業病腱鞘炎が痛むのだろう。
店が閉じる前にもう一度足をはこぼう、そんな決意を胸に店を後にした。
(古いマッチ箱が店の歴史を物語る)