「大人が読書をしていない」ことも要因の一つか ─
読書には国を変える力がある
おはようございます みなさん
全く本を読まない子供が半数超
「大人が読書をしていない」ことも要因の一つか ─
読書には国を変える力がある
https://the-liberty.com/article/22480/
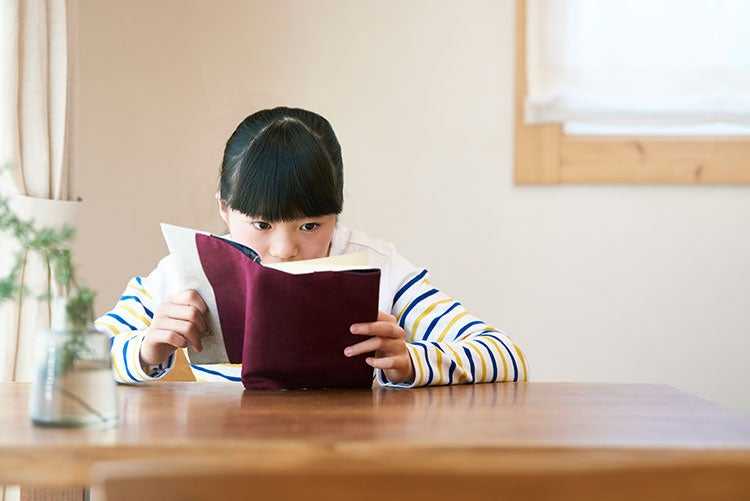
《ニュース》
ベネッセコーポレーションがこのほど
「1日に全く読書をしない子供が半数超え」
との調査結果を発表しました
《詳細》
今回の調査は
ベネッセ教育総合研究所と
東大社会科学研究所が共同で実施し
2024年7~9月にインターネットで行い
小中高生とその保護者の約1万2千組から回答を得ました
それによると
1日の間で読書をしない(0分)という回答は
52.7%と半数を超え
10年前の2015年と比べて1.5倍も増加しました
小1~3年が33.6%
小4~6年は47.7%
中学生59.8%
高校生69.8%と
いずれも15年に比べ14~22ポイント増加
1日の読書時間の平均は
小4~6年で15.6分
高校生で10.1分など
15年より約5~6分減少しました
読書時間の減少と反比例するように
スマホの使用時間は増加しているといいます
1日のスマホ使用時間は
小4~6年が33.4分
中学生が95.7分(1時間半以上)
高校生は138.3分(2時間以上)で
それぞれ15年と比べて
22~52分も増加しています
また
子供の読書量の低下をめぐっては
「保護者の読書意識」との関連性もみられたといいます
「読書をしない」子供のうち
「自分の能力を高めるために勉強することがある」と回答した
保護者の子供の割合は48.9%だったのに対し
「ない」と答えた保護者の子供は56.0%
また
家庭で
「本や新聞を読むことの大切さを伝えている」
保護者の子供の割合は44%でしたが
「伝えていない」
保護者の子供では67.9%だったとのことです
近年
「子供の読書離れ」が叫ばれていますが
その要因の一つとして
「大人が本を読まなくなり
読書の大切さを子供に伝えていないこと」があることが
本調査からうかがえます
全国学校図書館協議会による2025年の学校読書調査でも
「教員から本を紹介される機会が減少している」
ことが明らかになっています
《どう見るか》
子供が主体的に読書や勉強に取り組むことが当然
理想的ではありますが
そのためにも
身近な大人が「意識改革」をすることが重要でしょう
日本では
「月に1冊も本を読まない人が6割を超えている」
と言われています
(文化庁が2023年に行った調査)
ネットやスマホ
人工知能(AI)などデジタル社会が進展するにつれ
世界的にも読書離れは進んでいますが
日本は諸外国よりも加速しているという指摘もあります
例えば
コンサルティング会社パーソル研究所の調査では
「勤務先以外でどのような自己研鑽をしているか」
という趣旨の問いに
「特に何も行っていない」と回答した日本人が52.6%と
他国と比べても突出して低いことが判明
(次に低いオーストラリアが28.6%)
研鑽をしている人のうち「読書」と答えた人も
日本が最も少なかったといいます
(2022年「グローバル就業実態・成長意識調査」)
中には
「読書をしても仕事に役立たない」
と考える人もいるかもしれません
しかし読書は一種の「鍛錬」であり
淡々と読書を続けていく中で
意志力や精神力を鍛えることができます
また
豊富なアイデアや発想力も仕事には重要ですが
大川隆法・幸福の科学総裁はそれを得るための
「いちばん短い方法」
「短距離の方法」は
「読書」であり
「繰り返し繰り返し読んで
読めるものがあって
それで覚えているという力が
ものすごい力になる」と指摘しています
(『成功をつかむ発想法』)
さらに
「真の良書」は仕事に役立つどころか
「国力」とも大きく関係しています
読書の価値を唱え続けた故・渡部昇一氏は
サミュエル・スマイルズの『自助論』や
P・G・ハマトンの『知的生活』などが読まれていた時代に
イギリスは最盛期を迎え
その後
社会主義が台頭し『自助論』が忘れ去られるにつれ
国力が衰退していったと指摘
日本においても同様で
『自助論』や福沢諭吉の『学問のすすめ』が
ベストセラーになった明治期に
それが精神的な柱となり
世界の大国へと発展していきました
大川総裁も
「『本には
そういう力がけっこうあるものだ』と思っています」
と語っています
(『ハマトンの霊言 現代に知的生活は成り立つか』)
経済的にも社会的にも
停滞感が漂う日本の現状を打破するためにも
読書の価値を再考する必要があるのではないでしょうか
その意味でも
まずは大人が率先して本を読み
その価値を子供にも伝えていくことが大事です
今月30日発刊の本誌12月号では
「AI時代を生き抜くために読書をしよう!」と題し
読書の大切さや
おすすめの良書を紹介しています
是非
お読みください
ザ・リバティweb
近年はインターネットの情報量が多すぎて
読書まで手が届かないというのが実情でしょう
しかし
ネットの情報はほとんどが粗悪なものばかり
新聞や質の高いニュースを選択して情報を得るべきで
出来得る限り読書の時間に当てたいものです
今日の光の言霊は【自己確立】です
「阿羅漢の段階までは誰でも行かれます」
と説かれています
そして
自己確立が出来ると
ここからが厳しい菩薩への境地です
阿羅漢に成ったばかりの人が
菩薩の境地まで行くには何転生もかかるのではないでしょうか
今回の転生で阿羅漢になり自己確立できた人は
その境地を落とさず
自己中心的な心を他者への愛で
満たしていく努力が必要です
菩薩の境地はまず他者への愛の思いで満たされています
読書には国を変える力がある
おはようございます みなさん
全く本を読まない子供が半数超
「大人が読書をしていない」ことも要因の一つか ─
読書には国を変える力がある
https://the-liberty.com/article/22480/
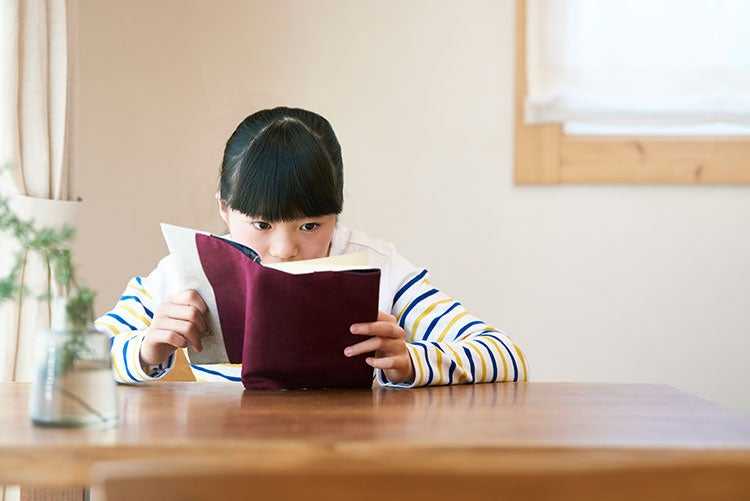
《ニュース》
ベネッセコーポレーションがこのほど
「1日に全く読書をしない子供が半数超え」
との調査結果を発表しました
《詳細》
今回の調査は
ベネッセ教育総合研究所と
東大社会科学研究所が共同で実施し
2024年7~9月にインターネットで行い
小中高生とその保護者の約1万2千組から回答を得ました
それによると
1日の間で読書をしない(0分)という回答は
52.7%と半数を超え
10年前の2015年と比べて1.5倍も増加しました
小1~3年が33.6%
小4~6年は47.7%
中学生59.8%
高校生69.8%と
いずれも15年に比べ14~22ポイント増加
1日の読書時間の平均は
小4~6年で15.6分
高校生で10.1分など
15年より約5~6分減少しました
読書時間の減少と反比例するように
スマホの使用時間は増加しているといいます
1日のスマホ使用時間は
小4~6年が33.4分
中学生が95.7分(1時間半以上)
高校生は138.3分(2時間以上)で
それぞれ15年と比べて
22~52分も増加しています
また
子供の読書量の低下をめぐっては
「保護者の読書意識」との関連性もみられたといいます
「読書をしない」子供のうち
「自分の能力を高めるために勉強することがある」と回答した
保護者の子供の割合は48.9%だったのに対し
「ない」と答えた保護者の子供は56.0%
また
家庭で
「本や新聞を読むことの大切さを伝えている」
保護者の子供の割合は44%でしたが
「伝えていない」
保護者の子供では67.9%だったとのことです
近年
「子供の読書離れ」が叫ばれていますが
その要因の一つとして
「大人が本を読まなくなり
読書の大切さを子供に伝えていないこと」があることが
本調査からうかがえます
全国学校図書館協議会による2025年の学校読書調査でも
「教員から本を紹介される機会が減少している」
ことが明らかになっています
《どう見るか》
子供が主体的に読書や勉強に取り組むことが当然
理想的ではありますが
そのためにも
身近な大人が「意識改革」をすることが重要でしょう
日本では
「月に1冊も本を読まない人が6割を超えている」
と言われています
(文化庁が2023年に行った調査)
ネットやスマホ
人工知能(AI)などデジタル社会が進展するにつれ
世界的にも読書離れは進んでいますが
日本は諸外国よりも加速しているという指摘もあります
例えば
コンサルティング会社パーソル研究所の調査では
「勤務先以外でどのような自己研鑽をしているか」
という趣旨の問いに
「特に何も行っていない」と回答した日本人が52.6%と
他国と比べても突出して低いことが判明
(次に低いオーストラリアが28.6%)
研鑽をしている人のうち「読書」と答えた人も
日本が最も少なかったといいます
(2022年「グローバル就業実態・成長意識調査」)
中には
「読書をしても仕事に役立たない」
と考える人もいるかもしれません
しかし読書は一種の「鍛錬」であり
淡々と読書を続けていく中で
意志力や精神力を鍛えることができます
また
豊富なアイデアや発想力も仕事には重要ですが
大川隆法・幸福の科学総裁はそれを得るための
「いちばん短い方法」
「短距離の方法」は
「読書」であり
「繰り返し繰り返し読んで
読めるものがあって
それで覚えているという力が
ものすごい力になる」と指摘しています
(『成功をつかむ発想法』)
さらに
「真の良書」は仕事に役立つどころか
「国力」とも大きく関係しています
読書の価値を唱え続けた故・渡部昇一氏は
サミュエル・スマイルズの『自助論』や
P・G・ハマトンの『知的生活』などが読まれていた時代に
イギリスは最盛期を迎え
その後
社会主義が台頭し『自助論』が忘れ去られるにつれ
国力が衰退していったと指摘
日本においても同様で
『自助論』や福沢諭吉の『学問のすすめ』が
ベストセラーになった明治期に
それが精神的な柱となり
世界の大国へと発展していきました
大川総裁も
「『本には
そういう力がけっこうあるものだ』と思っています」
と語っています
(『ハマトンの霊言 現代に知的生活は成り立つか』)
経済的にも社会的にも
停滞感が漂う日本の現状を打破するためにも
読書の価値を再考する必要があるのではないでしょうか
その意味でも
まずは大人が率先して本を読み
その価値を子供にも伝えていくことが大事です
今月30日発刊の本誌12月号では
「AI時代を生き抜くために読書をしよう!」と題し
読書の大切さや
おすすめの良書を紹介しています
是非
お読みください
ザ・リバティweb
近年はインターネットの情報量が多すぎて
読書まで手が届かないというのが実情でしょう
しかし
ネットの情報はほとんどが粗悪なものばかり
新聞や質の高いニュースを選択して情報を得るべきで
出来得る限り読書の時間に当てたいものです
今日の光の言霊は【自己確立】です
「阿羅漢の段階までは誰でも行かれます」
と説かれています
そして
自己確立が出来ると
ここからが厳しい菩薩への境地です
阿羅漢に成ったばかりの人が
菩薩の境地まで行くには何転生もかかるのではないでしょうか
今回の転生で阿羅漢になり自己確立できた人は
その境地を落とさず
自己中心的な心を他者への愛で
満たしていく努力が必要です
菩薩の境地はまず他者への愛の思いで満たされています
【自己確立】
幸福の科学の会員には
「まず
この後光が出る段階
心の曇りを取って
後光が出てくる段階
阿羅漢の段階を
目指してください」
と言っているのです
これを
「自己確立」
といいます
この自己確立ができると
ある程度
人を引き上げるように
なっていけるのです
「そこまでは
まずやりなさい
自分をつくるほうが
大事ですよ
人を引き上げるのは
それからあとですよ」
ということを
言っています
HS
『エル・カンターレ 人生の疑問・悩みに答える
幸せな家庭をつくるために』 P.199


