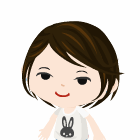六本木の俳優座のスタジオスペースでアイルランド戯曲「ラフタリーの丘で」を観た。
先日は同じ場所で優れたオーストラリア戯曲を知ったのだが(下記リンク参照)、今回は驚きのアイルランド戯曲との出会いがあった。
歴史ある劇団が国内外の優れた戯曲を均整のとれた劇団員が演じ、紹介してくれる、、、これぞ一つの演劇文化継承の形だと実感したのだが、それを目の前で見せてもらいながら、「2025年4月末に俳優座劇場閉館」という知らせも同時に目にするのはなんとも複雑な気分。
まあ、俳優座の活動は劇場の閉館とは別にさらに新しい環境のもとでの道を模索していくのだろうから(もしかしたら新たな俳優座の歴史の始まり・好機となるのかもしれないので)、あと2年弱の期間を使って、それこそ驚くような、今の時代を乗りこなした道を開拓していって欲しい、もちろん今回観させていただいたような丁寧な作品作りの伝統を残しながら、と感じた。
で、今回の「ラフタリーの丘で」なのだが、観劇後にはこのチラシのイラストの中の赤くなった草原を(必死に)駆けるうさぎ、または罠にかかって吊るされたうさぎたちへの見方、思いが劇的に変わる、そんな目から鱗どころか瞼が剥がれそうなショッキングな内容だった。
***** 演劇サイト より *******
アイルランドのある丘で暮らすラフタリー家では、18 歳になり結婚を控えたソレルを⾒てダイナが複雑な思いに駆られていた。この家で絶対的権⼒をもつ⽗親は家族を暴⼒で蹂躙し、トラウマをもつダイナは「沈黙」することで、いわば⽗親の共犯者となっていたからである。逃れること のできない閉塞した状況で、丘に縛り付けられる家族の隠匿された真実 とは…
*************
アイルランドの田舎町、親子三世代(認知症気味の祖母、封建的よりもさらに強度の絶対的暴君の父、そして二人の娘(?!)と一人の息子)が暮らすラフタリー一家。冒頭、父親を恐れ離れの牛小屋に暮らす息子デッド(齋藤隆介)の異常さとは裏腹に、家の中の世界はどこにでもある父親レッド(加藤佳男)を中心とした家族のようにみえた。
しっかり者の長女ダイナ(荒木真有実)、と家族の宝である末娘(!?)のソレル(高宮千尋)、徘徊の兆候はあるものの元気な祖母シャローム(松本潤子)。ソレルには結婚を控えた婚約者ダーラ(山田貢央)がいて、ダイナはその結婚式の準備に余念がない。
近所に住む男やもめの友人アイザックと趣味である狩猟に出かけ、うさぎを二匹仕留めたレッドがそれを持ち帰り、ソレルに処理をするように命令する。
デートから戻ったソレルとダーラ、二人の将来に関する会話を聞いたレッドは可愛い子ウサギ(ソレル)を自分のものにしておくために、彼が知っている唯一の方法=暴力(実際には暴力以上のやり方で)でソレルを組み伏せる。
そのことが引き金となり、ラフタリー家のおぞましい秘密が明らかになっていく。
どのようにしてレッド —それはラフタリー家に代々引き継がれてきた因習のようでもあるようだ — がこの一家をまとめ(?!!)あげてきたのか、その犠牲となったものたちがどのように力関係により洗脳されてきたのか。
最後の砦であったソレルが将来へ向けての決意を語るシーンで幕を閉じるのだが、とても面白いことにそのシーンに関しては演出家の意図する終わり方で、という作家の指示があり、戯曲ではオープンにされているとのことだった(アフタートークで演出家の高岸未朝とドラマトゥルクと翻訳を担当した坂内太が話していた)。
そのアフタートークで両人が(この二人の会話が無駄が一切なく、とても有意義な時間だった)、この劇は一つの作品としてストーリーが面白いのは確かだが、この戯曲で起こっていることだけでなく、もっと広い視野でこの今ある社会、そして人というものの存在をみているという点が興味深く、傑作戯曲である話していた。
まったくもってそのお二人の読みに同感で、一見マッド・lunaticにも見えるこの戯曲が、実のところこの世を的確に映し出している —> これは私が愛してやまないMartin McDonah (彼自身はロンドン生まれだが)のアイルランドを題材にした作品にも度々登場するlunatic(常軌を逸した人々の行い)さ— という、アイリッシュの作家恐るべしの事実なのだ。
そのアイルランドで注目の作家Marina Carr(マリーナ・カー)、確実にチェックすべき作家の一人であることは間違いなく、こんなに素晴らしい作家を紹介してくれた俳優座に、そして日本の観客へ向けて丁寧に演出してくれた高岸さんとドラマトゥルクの坂内さんにも、もう一度感謝の意を表したい。
例えば、前述のエンディングに加え、冒頭にはアイルランドで問題になっている多くの幼児や未成年者たちが犠牲になった修道院のスキャンダル(映画「マクダレンの祈り」)について、そして長年話題にするのがタブーとされていたカトリック神父による性的虐待問題についての語りがラジオ放送から流れてくる設定になっているのだが、これは少しでもアイルランドで起きている問題を観客にも共有してもらうための演出とのことだった。
(McDonaghの映画最新作。ぶっとんでいます!必見!!)
確かに、アイルランドのどこかの無名の田舎町で起きたことを描いているのだが、今、日本で起こっている権力が付随した大規模な性加害問題の社会的な闇を思い起こさずにはいられない。
また、このようなことが小さな田舎町で放置され続けているその村社会構造の問題、そして未成年児を親が所有物のように扱って彼らの将来をも奪ってしまう親と子、そして地域社会の問題、教育の問題、格差社会の問題、、、とまさにこの芝居から浮かび上がってくるものは数知れず、また遠いアイルランドの話ではすまされないものがある。
最後に悪魔のような男レッドを演じた加藤佳男の見事な演技に拍手を送りたい。