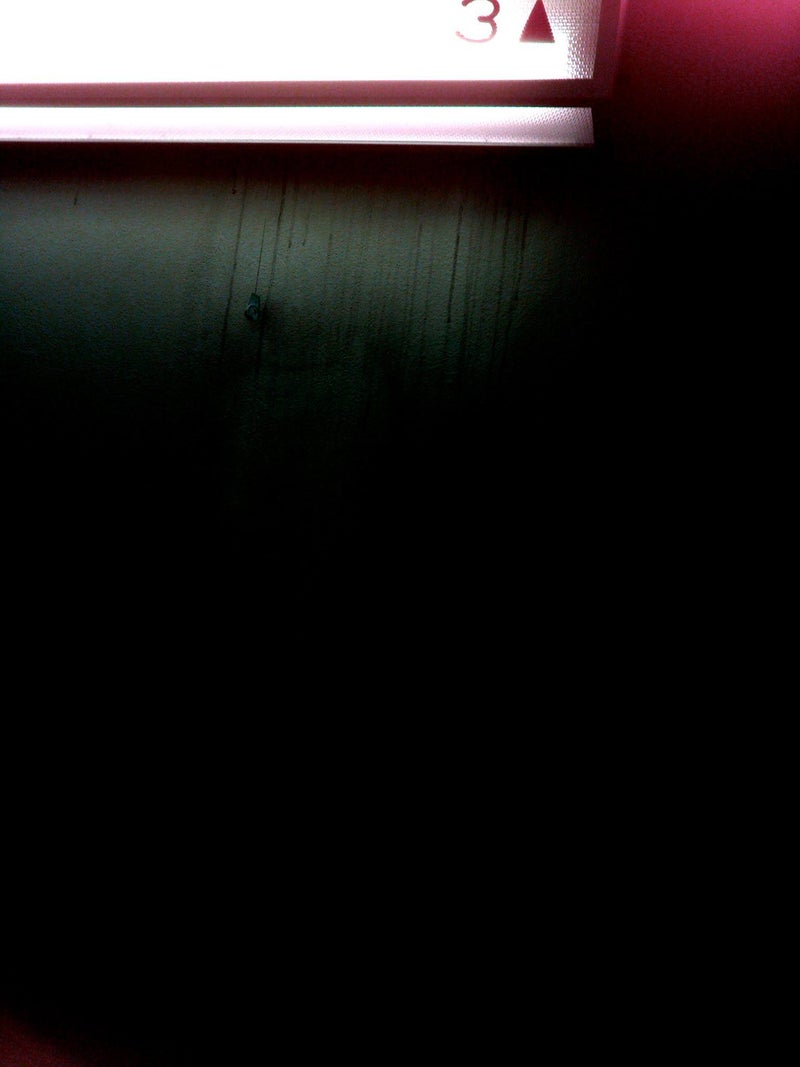( nemocnice )
死を迎える夜に月を壊れた窓から覘く
私は奇妙な病気にかかった。
それは病気と言うよりは事故のようなものだった。
私は私の時間のなかに取込まれてしまったのだ。
どうする事も出来ず病院に搬送されたが原因の特定すらできなかった。
結局幾つかの病院や研究施設をたらい回しされこの廃墟のような病院に収容されたのだがそこでもただ観察されるだけという状態だった。
私には2つの時間が存在していた。
一つは肉体に直接影響を与え私は幼児から老人への過程を何度も繰り返しもう一つの時間はそれにおかまいなく私の人生そのものが本来持っている時間の範囲内を好き勝手に動き回った。
私は幼児の姿で過去に戻り歩く事もままならない老人の状態で何十年か先の廃墟と化した病院に送られてしまうのだ。
時間移動している間は「今」と言う時間帯に存在出来ないので診察を受ける事も出来ない。
担当医である老医者は私に時計をつけさせた。
小さいが非常によく出来ていて年数と日付を現すカレンダーが付いた文字盤が2つ並んで付いていた。
並列に並べられた文字盤の一つは右回りに回り現在から未来を、もう一つは左回りに回る事で現在から過去へ向かう時間を記録できるようになっていた。
時間はすべて記録されたので私がどの時間にどのくらい滞在していたかわかるようになっているのだ。
だがそれでわかったのは私が生まれた正確な年月日とおそらく死期だろうという30年後の未来だけだった。
結局時間の移動には何の法則性も無く身体の変化もそれに関係したものではなかったのだ。
唯一の救いはナースのメルテビィだった。
彼女は勘がいいのか私が「今」に帰ってくると必ず待っていたかのようにベッドの側にいるのだ。
幼児の状態で「今」に戻っても精神も幼児のままだ。
時間の中を連れまわされるような異様な体験に幼児の精神力では付いて行けるわけも無い。
それに時間と言うものがデタラメになってしまった私にとって彼女が待っていてくれるところが帰るべき世界でありメルテビィはとても大切な指標になったのだ。
「貴方の体は貴方を作っているとても小さな物質に戻ってしまうの。そのせいで時間と言う約束に縛られずに移動できるのよ。それは貴方が望んだ事ではなくても貴方はそれを受け入れるしかないのよ」
「俺はもとあった状態に戻りたいだけなのだ。それには何処に行けば良いんだ?」
「私にはそんなことはわからない。でも時間を過去あったように戻す事はできないの。時間は流れる水のように前にしか流れて行かないのよ」
「だが俺は何度も過去を見て来ている」
「でも同じ過去じゃない。それはその度に少しずつ違う過去になっている それは戻っているんじゃなくて進んでいるのよ」
「じゃあいつまでも出口のない迷路の中を俺はなんのために徘徊し続けなければならないのだ?」
「そんなものに何の理由もないわ。誰も望んだ事ではないのよ」
だがそういうと彼女はもう違うことに気を取られている。
病院の壊れた窓から見える暗い空を低く飛ぶ大きな鳥を眺めているのだ。
あるとき隣に寝かされていた老人が灰になり吹き込んだ強風に散らされ跡形さえもなくなり病院の窓という窓が壊れて雨が遮るものもない私を容赦なく濡らした。
だがそれもすぐに収まり気がつけばいつものベッドでメルテビィが私を抱きかかえているのだった。
私はメルテビィの感情を匂いで理解できるのだ。
それは感情も物質が作り出すものだからだ。
だがそれは幼児期の僅かな間だけだ。
だが匂いから理解できるのはメルテビィの深い絶望だった。
それは私に対してではなくメルテビィにとっての環境そのものであって呪縛のように彼女を縛り付けているこの世界に対してのものだ。
メルテビィはとても深い闇の中に暮らしていてでもそれは私も大差なかった。
なにもかもが夢のように曖昧で断片的だったからあるいは本当に夢だったのかもしれない。
遠くで とても遠くで痩せた犬が解体されている。
皮を剥がれ腹を引き裂かれ内蔵が引っ張りだされ歪んで茶色く変色したアルミの鍋に投げ込まれていた。
縮れた髪の太った女がその様子を楽しそうに眺めている。
犬を解体しているのは私だった。
刃の欠けた大降りのナイフには血や脂がへばりつくので時々それを汚れた布で拭うのだが欠けた刃が布に引っかかり細い繊維が刃に絡み付いた。
それが神経かなにかのようにみえる。
そろそろ終りだと思うと私はベッドに転がる幼児に戻っていた。
そしてわからなくなる、あの刃に絡み付いていたものは私の神経だったのかそれとも哀れな犬のものなのか。
「その犬を知っている。私のとても大切な兄弟のような犬だった」
「俺は知らない。お前の過去はなにも知らないんだ」
「じゃあ貴方は自分の過去を胸を張れるようにちゃんと憶えているの?」
過去?自分の過去?なにも憶えていなかった。
自分がここに来る迄何処でなにをしていたのか何一つ思い出せなかった。
記憶というものはそれぞれの時間に留まって初めて成立するものなのかもしれない。
その時間とそこで起きた事象は本来関連付けられる個別な現象なのだ
だからそこから切り離され方向性を失った時間軸のなかではその事象自体が存続出来ず消えてしまうのだろう。
時計が指し示す数字はその瞬間の指標でしかなくその一瞬の変化しか捉えられなかったのだ。
記録としてならべられたどの時間にも法則のようなものは何一つも見出せなかった。
つまり今の私の時間にはその起点になるべき指標がなくそれは私という存在そのものが同じようなものだった。
時間を無くした事で私は自身をも喪失していたのだ。
過去の中で私は痩せこけた犬だった。
追い回され何度も棍棒で殴られ動けなくなった私の体をナイフが引き裂いた。
覗き込んだ誰もが笑っていて私は自分の内蔵が体から引き抜かれ汚れた鍋の中に投げ込まれるのをみた。
太った女が笑っていた。
もう動かない頭を誰かが動かしてそれでようやくナイフを揮う人間をみたのだがそれはメルテビィだった。
おかしいと思った。
犬である私は内蔵を抜かれとうに死んでいてなにも見えるわけが無い。
だがここにメルテビィが出てくることには違和感を覚えなかったのだ
そうだ。
どうせこれももどる頃には忘れてしまう。
ならその理由を考えても仕方が無い。
どうにもならない状況でなにを望んでもそれは叶うべくもないのだ。
老人だった夜、破れたカーテンの向こうにある壊れた窓から月が見える 。
それは窓に弧を描く糸のように細い美しい月でメルテビィにも見せたかったがそこには彼女の姿はなかった。
月はゆっくりと窓から離れて行き私はまた時間の奔流に投げ込まれていた。
混乱する記憶のナカで私はあらゆる時間に存在する
何度も何度も繰り返し夜がやってきて私はあらゆる時間のなかをただ流されている。
だがその実感をどうしても得る事が出来ないのだ。
いつの間にか私は眠っていて目が覚めたら傍らにはメルテビィがいてベッドの周りに散乱した犬の血や内蔵を片づけていた。
なぜそんなことになっているのか全くわからなかったがメルテビィがひどく悲しんでいることだけは彼女のにおいから理解できた。
「貴方は私の犬を殺したの。 でも貴方のせいではないし それにこの犬はもうずっと前に死んでいたの」
「よくわからない」
「そうね、もう憶えていられないものね。貴方の過去の時間が私の記憶と混ざりあっているのよ。貴方は私の記憶に迷い込んで本当は祖父がやる筈だったことを貴方がやってしまったの」
メルテビィの言っている事がわからなかった。
「私がまだ小さかった頃 うちには犬がいたわ。兄弟のように一緒に育てられた犬だった。でも 戦争が始まって食べるものがなくなって病気になった私に祖父がその犬を食べさせたの」
「戦争?」
「そう戦争。 私は随分遠いところから来たのよ」
「そうなのか?」
「病気が治ってしばらくして犬の事を知ったわ。 私は大好きだった祖父をずっと許せなかった。でも 犬は貴方が殺した。 もう 祖父を恨まなくて済むわ」
「じゃあ今度は俺を恨むのか?」
「わからない。 今は恨んでいないけど」
メルテビィはそういうと少し微笑んだように見えた。
その時はそうなのかと思った。
だがしばらくしてメルテビィは私の前から姿を消したのだ。
時間の中を彷徨いようやく「今」に辿り着いてもそこにはいつも待っていてくれる筈のメルテビィの姿がないのだ。
メルテビィが居ないだけで私は本当に今に帰って来れたのかどうか確信が持てず苦しんだ。
メルテビィこそが私にとって唯一の指針だったのだ。
私は酷い疎外感に苛まされ環境そのものに対して憎悪さえおぼえるようになっていた。
それは人間関係とかそういうものではなく世界そのものから疎外されているという感覚だ。
私は自身の妄想と現実の区別さえ付かなくなりあらゆる事象を恐れ壊れた窓を横切る鳥の影にさえ怯え憎悪を憶えた。
だがそのせいでメルテビィを深く愛していた事にようやく気付かされたのだ。
私は老医者に彼女の事を訊いたが彼はメルテビィを知らなかった。
そんなナースはここには存在していないと。
ナースでなくても同じ入院患者かもしれない。
私は執拗に食い下がり彼女の容姿や癖などを説明しているうちに老医者の表情はだんだん強張り年配のナースを呼んだ。
太った縮れ毛の女だ、どこかで会った筈だが思い出せなかった。
彼女は私に古い写真を見せた。
それは古びてすっかり黄変したぼろぼろの写真だったがそこには確かにメルテビィが無表情に座っていた。
「なんだ、やっぱりここにいるじゃないか」
「その娘は死人なの。私の姪なのよ」
「酷い摂食障害になってこの病院にいれたのだけどもう手遅れだった。彼女はあらゆる人間を恨んで死んだわ。もう30年も前のことになる」
年配のナースは考えるようにゆっくり話し始めた。
「それから時々見えるって人がいるの。でも貴方みたいに話したり世話をしてもらったなんて話は聞いた事が無い。」
「メルテビィ?」
「それは・・そんな名前じゃない」
ナースは思い出すように続けた。
「それは死者という意味よ。彼女の母親の国の言葉なの」
「彼女は誰なんだ?犬を祖父に殺されたって言っていた」
思い出してみれば彼女の事で知っていることはそれだけだった。
これだけ長い時間一緒に居て殺された犬の話しかしていなかった。
「それは・・」
老医師が口を開いた
「彼女にとってなによりも大切なことだったからだよ」
「彼女が死人だとしたらどうして俺にはみえたんだ?」
「お前が彼女を見る事が出来たのは時間を喪失していたからだ。死者には時間が存在しない、いや時間と言うものがなんの意味も持たないところで存在しているので我々にはすれ違う車窓のように一瞬にしか見える事の無い存在なのだ。でもお前は時間をなくしてしまった。つまり生きながら死人になっているのだよ」
「俺は生きているさ、ちゃんとこうやって話している」
「今はこうやって話している、いつものように何処にも行かないからな。いつもならすぐに時間に飲み込まれてしまうからこうやってゆっくり話す事等できはしない。それにおまえは犬だったのだよ。彼女に飼われていた」
「なにをバカなことを」
そう言いながら私はメルテビィに体を引き裂かれたのを思い出していた そうだ あのとき私は確かに犬だったのではないか?
「貴方は犬なのよ」
ナースがそういうのを聞きながら私はまた時間の奔流に飲み込まれていた。
時間の中でメルテビィが笑っていた。
彼女が笑うのをみるのははじめてだったので理由を聞きたかった。
だがそれは腹を裂かれて腸を引きずったまま彼女の元に駆け寄ろうとしている私を見て笑っているとわかり私は呆然とした。
私は犬で彼女に殺されようとしているのだ。
これが現実なのか妄想なのか確かめる手だてを思いつかない。
その間にも私は手際よく解体され内蔵が歪んだ鍋に投げ込まれた。
「これは復活の為の儀礼なのよ」
「貴方が死者となってちゃんとこっちに来る為の。 そうしないと貴方は永遠に時間の中に閉じ込められてとても狭い自我のなかを永遠に徘徊する事になるわ」
「でも なぜ犬なんだ? 俺は君に飼われていた犬じゃない」
「じゃあ自分を思い出せるの?」
そうだ もう自分のことを何一つ思い出せなかった。
「貴方は時間を喪失してそれから自分も無くしてしまったのよ。だから犬になった。そこにしか出口がなかったからよ。だから助けに来たの。貴方をあるべき世界に戻すのよ」
「あるべき世界?元に戻せるのか?」
「残念だけど動き始めた時間をもとあったように巻きもどすことはできないの。
確かに貴方の時間はとても不規則に揺れ動いているけどそれでも少しずつは未来に向かっているわ」
メルテビィは血の付いた手をそばにあったボロ切れで拭った。
「元には戻せないけど進める事は出来る。それか私のように時間から外れてしまうか、そのどちらかを選べる」
「それはどういうことなんだ?」
「貴方は貴方の時間から投げ出された時に自我を喪失し貴方である全てを無くしてしまったの。接触出来るのは死者である私だけ、貴方はもう随分前から死んでいるのよ。時間に見放された時からね。ただ貴方は死を認めず受け入れなかった。貴方を構成している一番小さな物質がそれに反応してしまったの」
良くわからなかった。
でも 確かにもう終わりにしたいと願った。
それにメルテビィがもう病院にはいないのならそこに居る理由もなかった。
私はメルテビィと居る事を強く願ったのだ。
「わかったわ、貴方のための終わりを用意する。犬とは違う貴方の出口」
メルテビィは私を強く抱きしめた。
彼女の匂いでいっぱいになったがもう彼女からは絶望の匂いはしてこなかった。
私の体は内蔵を垂らした汚れた犬の姿から老人へとゆっくり変わりはじめていた。
夜だ。
そして私はベッドに寝かされている。
固くてしみだらけのベッドだ。
時計は2つの文字盤が両方とも予告されていた私の終わりの時間を指していた。
暗く荒れ果てた病室にはもう誰もいない。
床はささくれ立ち窓から吹き込む風で破れたカーテンが揺れている。
壊れた窓のずっと高く暗い空を青白い月がゆっくりと流れていく。
もうなにも思い出せない。
だが自分がもうすぐ終わると言う事だけは理解できていた。
誰かにそう言われたのだ。
とても大切な誰かに。
おそらく私がこれから向かう永遠のその先で待つ者にあう為に。
私はとても小さな粒子となってそこに回帰するのだ。
それをあるべき未来と今は信じて
konec 2016 6/20