歴史には「あった歴史」と「あって欲しい歴史」があるという。
歴史学上には「あった歴史」の探求以外に歴史は存在しない。ましてや「愛」や「魂」とやらの感情は「歴史」に含めることはない。ある意味、歴史学は冷徹な学問だ。近年、「歴史・歴史」とかまびすしい北東アジア情勢である。まあ「歴史」が政治利用される典型ではあるが、歴史学を志した者とすればスポットが当たっている感もあり、また学者の意見を超え、史料を捻じ曲げてまで歴史を利用し構築しようとする動きも垣間見え、複雑な感情を禁じ得ない。
無論、歴史「認識」や歴史「観」というものは、画一化するべき問題ではない。最初から観点が複雑多岐に相違する思想内容に勝敗、優劣を単純にしかも結果論的に叙述した「歴史」にはそれこそ未来も正義すらも存在しない。歴史哲学・歴史思想という学問分野であれば、それが「あってほしい歴史」を予定調和的存在に該当させるであろうが、あくまでも概念・思想であり、事実関係を史料によって探求した上での「歴史事実」ではない。
歴史事実についての「意義」は当事者間の事情やその影響も含めた考察を丁寧に行い、残された史料が何を語り、何を事実と断定できるのか、同時代史料や比較考察によって「事実」を掘り起こす作業が必要である。それらの調査・研究に関して様々な角度から取り組んだ結果、定説が覆ることもしばしばある。それが歴史学だ。むしろ「定本的、画一的歴史」もしくは最初から「動かし難いと規定する歴史」こそ、最も歴史学の発展に対する難敵・障害そのものなのである。
「日本史」でいえば、鎌倉幕府の成立を「1192年」ではなく「1185年」にするという変更が行われたのは記憶に新しい。また聖徳太子、源頼朝、足利尊氏、武田信玄だと思われて定着していた人物画像について全てに「?」が生じていることも、歴史学の未来的発展の結果である。
そうした歴史学調査や研究の成果を、まずは「結論ありきの思想」として政治利用することは戒められねばならない。
さて中国史は世界有数の史料が集積されている豊富な素材の宝庫である。
その史料に関する扱いについて、考えさせられる事例が2つあるので紹介したい。
『春秋』斉襄公二十五(前548)年、「夏五月乙亥、斉の崔杼、其の君、光を弑す」という記録が見える。斉国の崔杼が斉の荘公(名は光)を弑殺したという事実を記録したものである。そこには判断は存在しない。ただ故人の営みがあるというだけだ。
崔杼は荘公の時の大夫(貴族)であり、荘公を殺して荘公の異母弟である景公を立てて、自ら宰相の任に着いた。司馬遷は崔杼が荘公を殺した間の事情について詳細に記録している。荘公の父である霊公は、魯の公女との間に生まれた光を太子としたが、後に寵愛した宋の戎姫の子牙を太子に立て、光を僻地に追放した。一度立てた太子を正当な理由もなく廃嫡するのは理不尽であるのみならず、当時の嫡長子相続を元にした世襲制度に反することであった。そのため、霊公が病気になると、崔杼は光を迎え入れてこれを擁立した。これが荘公である。荘公は斉に戻るとすぐに戎姫を殺し、即位すると太子牙も殺し復讐したのである。荘公は崔杼の尽力により斉の君主に着くことができたのであったが、荘公は崔杼の妻が特に美人であったためにこれと密通し、屡々、崔家に通っては乱行の限りを尽くしていたのであった。(『史記』斉太公世家)
荘公の破廉恥で「恩知らず」な行為に激怒した崔杼は、遂に荘公を自宅の兵で追い詰め殺害するに至った。
その日、懲りもせず崔杼の妻を誘惑していた荘公は、崔杼の自宅を警備する兵に追いかけられたため、荘公は「ワシは君主だぞ!」と大声で喚いたが、兵らが答えた。「我々は命令により好色な賊を捕らえようとしているのだ。それが君主などとは知らぬ。」という。塀際に追われた荘公は「一族の墓所で自殺させてくれ」と懇願したところ、激昂する兵士は「恥を知るならばそこで自害するがよい」と騒ぐ。そこで荘公は垣根を乗り越えて逃げようとしたが、途中で兵の矢が股に当たり、垣根から転がり落ちて死んだのであって、崔杼が直接殺した訳ではない。実際に殺害したのは自宅警備の兵だが、彼らに「殺せ!」と命令したのは崔杼である。
当時の中国では、国の役所に歴史を記録する官人である「史官」が必ず存在していた。斉の史官は、理由はどうあれ荘公の死の責任を崔杼に負わせ、崔杼が荘公を弑殺したと見做したため、崔杼による荘公の弑殺であると記録した。
史官が簡(木簡か竹簡)に筆で「崔杼弑其君光」と記入したところ、崔杼は権力に物言わせ圧力をかけ、後世に自分の名が逆臣として残ることを恐れ、斉国の太史(記録係)に「荘公は病死した」と国史に記録するよう命じ、その史官を斬り殺して記録を抹消しようとした。そして史官を継いだ、殺された史官の弟が同様に「崔杼弑其君光」と記録したため、崔杼はその弟をも殺して歴史の改竄を謀ろうとした。しかし、またその史官の弟が継いで同様に記録するに及び、ついに歴史の改竄を諦めたのであった。
崔杼「死ぬのが怖くないのか?」
史官「あったことをあったと記すことが歴史です。もしも歴史を偽ったとしても必ず事実を記す人が誰か居る筈です。そうなれば貴方の歴史改竄による偽りの歴史は貴方に対し永遠に悪評を立てる恥の源となることでしょう。」
…筆は剣よりも強い…
(情報の出所が不明ではあるが…一体、どこから聞いたのか…)
史官の兄弟が悉く殺されことを聞いた史官・南史氏は「崔杼が君主を弑殺した」と記した簡策を持参して斉の役所に馬で駆けつけ赴いたのだが、既に「記録された」ということを知って引き返したともいう。(『春秋左氏伝』襄公二十五年)
荘公は決して立派な君主とは言えず、崔杼の方に同情する余地も十分ある。ましてや荘公が自分で転落死した訳であるから、崔杼にすれば君主殺しの犯人として歴史に残ることは、承服しかねるといえばそうであろう。
歴史を記録する側から言えば、理由はともかく荘公は崔杼の配下の者に矢を射られて追いかけられ、その難を逃れようとして死んだのであるから、崔杼が荘公の死に関与した事実を記録する必要があるのはいうまでもない。
崔杼はその後、荘公の弟を景公として擁立した。崔杼は慶封と共同して国内を掌握し、反対者が出ないように大夫・士(貴族階級)達を集め、「崔・慶に組しないものはこれを殺す」と恐怖政治宣言を行った。当時、斉の国民に絶大な人気があった晏嬰をもこれに従わせようとするも晏嬰はこれを断った。しかし、崔杼は晏嬰を殺すことはできなかった。その後、崔杼は景公を傀儡として政治を行ったが、前妻の子と後妻の連れ子とが対立し、それに慶封が介入して権力を独占しようとしたために一族は全滅してしまい、一人残された崔杼は自殺に追い込まれた。
その際、残された歴史は淡々とその事実をも伝えている。彼の苦悩や権勢がどうあろうと、連綿とした歴史・史料に対しては脆かったことを考えずにはいられない。歴史的事実とはそういうものなのである。
東大テストゼミ日本史解説動画
東大テストゼミに参加しよう!
東大PJゼミ生になろう!
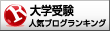
大学受験 ブログランキングへ
にほんブログ村 受験ブログ
歴史学上には「あった歴史」の探求以外に歴史は存在しない。ましてや「愛」や「魂」とやらの感情は「歴史」に含めることはない。ある意味、歴史学は冷徹な学問だ。近年、「歴史・歴史」とかまびすしい北東アジア情勢である。まあ「歴史」が政治利用される典型ではあるが、歴史学を志した者とすればスポットが当たっている感もあり、また学者の意見を超え、史料を捻じ曲げてまで歴史を利用し構築しようとする動きも垣間見え、複雑な感情を禁じ得ない。
無論、歴史「認識」や歴史「観」というものは、画一化するべき問題ではない。最初から観点が複雑多岐に相違する思想内容に勝敗、優劣を単純にしかも結果論的に叙述した「歴史」にはそれこそ未来も正義すらも存在しない。歴史哲学・歴史思想という学問分野であれば、それが「あってほしい歴史」を予定調和的存在に該当させるであろうが、あくまでも概念・思想であり、事実関係を史料によって探求した上での「歴史事実」ではない。
歴史事実についての「意義」は当事者間の事情やその影響も含めた考察を丁寧に行い、残された史料が何を語り、何を事実と断定できるのか、同時代史料や比較考察によって「事実」を掘り起こす作業が必要である。それらの調査・研究に関して様々な角度から取り組んだ結果、定説が覆ることもしばしばある。それが歴史学だ。むしろ「定本的、画一的歴史」もしくは最初から「動かし難いと規定する歴史」こそ、最も歴史学の発展に対する難敵・障害そのものなのである。
「日本史」でいえば、鎌倉幕府の成立を「1192年」ではなく「1185年」にするという変更が行われたのは記憶に新しい。また聖徳太子、源頼朝、足利尊氏、武田信玄だと思われて定着していた人物画像について全てに「?」が生じていることも、歴史学の未来的発展の結果である。
そうした歴史学調査や研究の成果を、まずは「結論ありきの思想」として政治利用することは戒められねばならない。
さて中国史は世界有数の史料が集積されている豊富な素材の宝庫である。
その史料に関する扱いについて、考えさせられる事例が2つあるので紹介したい。
『春秋』斉襄公二十五(前548)年、「夏五月乙亥、斉の崔杼、其の君、光を弑す」という記録が見える。斉国の崔杼が斉の荘公(名は光)を弑殺したという事実を記録したものである。そこには判断は存在しない。ただ故人の営みがあるというだけだ。
崔杼は荘公の時の大夫(貴族)であり、荘公を殺して荘公の異母弟である景公を立てて、自ら宰相の任に着いた。司馬遷は崔杼が荘公を殺した間の事情について詳細に記録している。荘公の父である霊公は、魯の公女との間に生まれた光を太子としたが、後に寵愛した宋の戎姫の子牙を太子に立て、光を僻地に追放した。一度立てた太子を正当な理由もなく廃嫡するのは理不尽であるのみならず、当時の嫡長子相続を元にした世襲制度に反することであった。そのため、霊公が病気になると、崔杼は光を迎え入れてこれを擁立した。これが荘公である。荘公は斉に戻るとすぐに戎姫を殺し、即位すると太子牙も殺し復讐したのである。荘公は崔杼の尽力により斉の君主に着くことができたのであったが、荘公は崔杼の妻が特に美人であったためにこれと密通し、屡々、崔家に通っては乱行の限りを尽くしていたのであった。(『史記』斉太公世家)
荘公の破廉恥で「恩知らず」な行為に激怒した崔杼は、遂に荘公を自宅の兵で追い詰め殺害するに至った。
その日、懲りもせず崔杼の妻を誘惑していた荘公は、崔杼の自宅を警備する兵に追いかけられたため、荘公は「ワシは君主だぞ!」と大声で喚いたが、兵らが答えた。「我々は命令により好色な賊を捕らえようとしているのだ。それが君主などとは知らぬ。」という。塀際に追われた荘公は「一族の墓所で自殺させてくれ」と懇願したところ、激昂する兵士は「恥を知るならばそこで自害するがよい」と騒ぐ。そこで荘公は垣根を乗り越えて逃げようとしたが、途中で兵の矢が股に当たり、垣根から転がり落ちて死んだのであって、崔杼が直接殺した訳ではない。実際に殺害したのは自宅警備の兵だが、彼らに「殺せ!」と命令したのは崔杼である。
当時の中国では、国の役所に歴史を記録する官人である「史官」が必ず存在していた。斉の史官は、理由はどうあれ荘公の死の責任を崔杼に負わせ、崔杼が荘公を弑殺したと見做したため、崔杼による荘公の弑殺であると記録した。
史官が簡(木簡か竹簡)に筆で「崔杼弑其君光」と記入したところ、崔杼は権力に物言わせ圧力をかけ、後世に自分の名が逆臣として残ることを恐れ、斉国の太史(記録係)に「荘公は病死した」と国史に記録するよう命じ、その史官を斬り殺して記録を抹消しようとした。そして史官を継いだ、殺された史官の弟が同様に「崔杼弑其君光」と記録したため、崔杼はその弟をも殺して歴史の改竄を謀ろうとした。しかし、またその史官の弟が継いで同様に記録するに及び、ついに歴史の改竄を諦めたのであった。
崔杼「死ぬのが怖くないのか?」
史官「あったことをあったと記すことが歴史です。もしも歴史を偽ったとしても必ず事実を記す人が誰か居る筈です。そうなれば貴方の歴史改竄による偽りの歴史は貴方に対し永遠に悪評を立てる恥の源となることでしょう。」
…筆は剣よりも強い…
(情報の出所が不明ではあるが…一体、どこから聞いたのか…)
史官の兄弟が悉く殺されことを聞いた史官・南史氏は「崔杼が君主を弑殺した」と記した簡策を持参して斉の役所に馬で駆けつけ赴いたのだが、既に「記録された」ということを知って引き返したともいう。(『春秋左氏伝』襄公二十五年)
荘公は決して立派な君主とは言えず、崔杼の方に同情する余地も十分ある。ましてや荘公が自分で転落死した訳であるから、崔杼にすれば君主殺しの犯人として歴史に残ることは、承服しかねるといえばそうであろう。
歴史を記録する側から言えば、理由はともかく荘公は崔杼の配下の者に矢を射られて追いかけられ、その難を逃れようとして死んだのであるから、崔杼が荘公の死に関与した事実を記録する必要があるのはいうまでもない。
崔杼はその後、荘公の弟を景公として擁立した。崔杼は慶封と共同して国内を掌握し、反対者が出ないように大夫・士(貴族階級)達を集め、「崔・慶に組しないものはこれを殺す」と恐怖政治宣言を行った。当時、斉の国民に絶大な人気があった晏嬰をもこれに従わせようとするも晏嬰はこれを断った。しかし、崔杼は晏嬰を殺すことはできなかった。その後、崔杼は景公を傀儡として政治を行ったが、前妻の子と後妻の連れ子とが対立し、それに慶封が介入して権力を独占しようとしたために一族は全滅してしまい、一人残された崔杼は自殺に追い込まれた。
その際、残された歴史は淡々とその事実をも伝えている。彼の苦悩や権勢がどうあろうと、連綿とした歴史・史料に対しては脆かったことを考えずにはいられない。歴史的事実とはそういうものなのである。
東大テストゼミ日本史解説動画
東大テストゼミに参加しよう!
東大PJゼミ生になろう!
大学受験 ブログランキングへ
にほんブログ村 受験ブログ