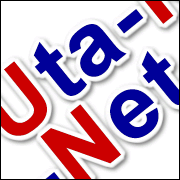こちらではご無沙汰しています![]()
せめて誕生日は祝おうと、妄想を奮い起こしました![]()
一月だというのに良く晴れた暖かい日だった。
幾何の授業中、窓際の席でキャンディは必死に眠気と戦っていた。午後の陽射しが彼女の頭と顔を直撃し、昼食後の満腹感とダブル効果で、幾度となく、ぐらぐらと首が折れかける。
(脳みそが溶けそうだわ……)
キャンディは真剣な表情で前方を直視しているクラスメイトたちを感心するように眺めた。
(みんな、よく平気ね)
少しでも気を紛らわせようと、欠伸を堪えながらキャンディが窓の外に目をやると、タイミングを合わせるように樹木の枝から雪の塊が落下した。
その塊の上の方で、はたはたと何かが動いているのが見える。
(え? ……鳥?)
一度、教壇へ視線を戻した。シスターが背中を向けて、黒板に訳の解らない数式を書いている。
再び、キャンディは外を見る。蠢く物体。
(やっぱり何かいる。ヒナが巣から落ちたのかしら?)
その時、エメラルドの瞳が、目線の端に小動物の姿を捉える。
──猫だ。
次の瞬間──彼女の体感では秒だった──キャンディは勢いよく窓を開くと、ひらりと外へ降り立っていた。
「きゃあっ! 寒い!」
窓から最も離れた席のイライザの大袈裟過ぎる金切り声と、
「キャンディスっ!!」
シスター・マーガレットの高い声を背に浴びて。
駆け寄ったのと同時に、猫は一目散に逃げていく。
「なぁんだぁ」
ヒナだと思い込んでいたものをキャンディは拾い上げる。
どんぐりだった。どんぐりについた葉っぱが風で揺れていたのだ。
「なぁんだぁ……」
キャンディは繰り返した。
「良かった」
「ちっとも良くありません」
……ビクンッ。
恐る恐る振り返ると、腕組みをしたシスター・マーガレットが怖い顔でキャンディを見下ろしていた。
窓際に群がる生徒たち。アニーとパティの心配そうな顔。
寒いと叫んだ筈のイライザが誰よりも身を乗り出して、意地悪そうな笑みを浮かべている。この上なく上機嫌そうだ。
(あぁ……、やってしまった)
その後は、お決まりの流れだった。
しんと静まり返ったシスターの部屋で、ペンが走る音だけが規則正しい時を刻んでいる。
ラテン語で聖書書き取り10回。反省室よりはマシだが、かなりきつい(右手が)。
「ふぅ……」
無意識に溜息。シスターが顔を上げ、キャンディを睨む。
「す、すみません」
「生き物の命を尊ぶのは大切なことですけれど、時と場合を考えなくてはいけませんよ、キャンディス」
「はい、でも、一刻を争うことだと思って……」
「手が止まっています」
「あ、すみません」
「まったく……」
今度はシスターが大きく溜息をつく。それから眉間を軽く押さえた後、机の上の書類の束を整えようと両手で摑んだ。
ところが、手元が狂い、数枚を床にばら撒いてしまう。
「あっ」
キャンディは瞬発的に席から立ち上がり、散らばった書類を搔き集めた。その時偶然、テリュースの名前が目に入り、心臓が飛び出しそうになる。
思わず、凝視した。
「キャンディス」
「はいっ!」
「プライベートなものですよ」
「は、はい……、申し訳ありません」
キャンディは書類をシスターへ差し出した。
「拾ってくれたことは感謝します。ありがとう」
「いいえ、当然のことです」
「では、書き取りを続けなさい」
「はい、シスター」
「はぁ……、手が痺れちゃった」
キャンディはじんじんする右手を振りながら、にせポニーの丘へ向かう。
「よく積もったわねぇ」
真っ新な雪の絨毯に足跡をつける時はいつも躊躇、ではなくわくわくする。
嬉々として丘の上まで登ったキャンディが雪の上にしゃがもうとした時だった。
「やめといたほうがいいんじゃないか」
どっきん……。
「いくら頑丈なモンキーの尻でも、凍傷は免れないと思うぜ」
いつもの揶揄うような低い声。
「失礼ね」
と余裕な素振りを装って、キャンディはゆっくりと振り向く。
「gentlemanなら、ハンカチくらい敷いてくれないの?」
「うーん、敷いてあげてもいいけど……」テリィはキャンディの躰の一点へ視線を走らせ、にやりと笑う。「たぶん収まりきらないと思うよ」
「なっ、何ですってぇ!?」
キャンディはテリィに正対し、指摘された部位を隠すように両手を後ろに回した。
「ほら、隠れてないじゃないか」
「テリュース! いい加減にしないと怒るわよ!」
栗色の髪の青年は遂に吹き出し、大笑いした。
「もういいわ!」ぶつぶつ呟きながら、金の髪を逆立てて少女は踵を返そうとする。
「まったくもう……レディに向かって……」
「おや、もう戻るのかい? 門限にはまだ早いぜ」
レディそばかす、どうぞと、テリィはハンカチではなく自分の着ていたコートを脱いで雪原に広げた。
「だ、駄目よ、濡れちゃうわ」
「平気さ。部屋に帰って暖炉の前に干しておけば一晩で乾くよ。それにこれなら、二人分余裕で収まるだろ?」
上手く丸め込まれている気がしないでもないけれど、断り切れず、キャンディはテリィのコートにおずおずと腰を下ろす。コートはほんのりと温かく、彼の体温に包まれているみたいだとキャンディは感じた。
「あのねテリィ、言っておきますけど……」
「分かってるよ、君の尻が見かけほどでかくないってことは」
と甘い掠れ声が桃色の耳朶に囁く。
「し」
キャンディはウサギのように跳び退いて、耳を押さえて叫んだ。
「だからっレディに向かって、尻、尻って何度も言わないでちょうだい!」
テリィは肩を震わせて笑っている。
「君といると本当に退屈しないよ、キャンディ」
やっと落ち着いた。
「今日は遅かったじゃないか。また何かやらかしたのかい?」
「え!?」
待っていてくれたの? という言葉をキャンディは飲み込んで、
「え、ええ……、ちょっと聖書書き取りを10回ばかし……」
「は?」
「お陰でペンだこができちゃった」
ほら、と痛々しく腫れた右手の中指を見せる。
「おやおや、でも反省室までいかないってことは、大した理由じゃなかったんだよな」君にとってはだけど──とわざわざ付け加えて彼は笑った。
「もう、これ以上説明する気が失せたわ」
いちいち厭味ったらしいんだから、と彼女は頬を膨らませる。
赤くなったり青くなったり飛び跳ねたり膨れたりと忙しかったので、目の前の青年に何か言うことがあったのを漸くキャンディは思い出した。
「ねぇテリィ」何の構えもなく、呼吸するように彼女は言う。「もうすぐ誕生日なのね」
刹那、テリュースの顔が強張った。
「──どうして知ってる?」
「えっと……あの、書き取り中に、シスターが落としたあなたの名簿を偶然……見てしまったの」
キャンディは狼狽える。テリィの声が明らかに不機嫌になったからだ。
「忘れてくれ」
「な、何故?」
「誕生日なんか、目出度くも何ともないからさ」
「そんな……、でも……」
「いいから忘れろ!」
「テリィ……」
テリィが急に立ち上がった。慌ててキャンディも立ち上がる。
彼は乱暴にコートを摑むと、キャンディと目も合わさずに歩き始めた。
「テリィ、待って!」
そして、少女の悲痛な声にも振り向かず、にせポニーの丘を駆け下りて行ってしまった。
数日後の放課後、にせポニーの丘を二つの影がゆっくりと登っていく。低い天辺に着くと、影と影は少し離れて立ち止まった。
この前と変わらぬ不機嫌な背中。前を歩いている間も、一度も振り向いてくれなかった。無理を言って連れ出したから当然かもしれない。
今の二人の心情のように、空は薄暗く重かった。
「テリィ……、私ね」
後ろを向いたままの青年の背中に、少女は、ぎこちなく言葉を紡ぐ。
「あなたが何故誕生日を嫌っているのか、私には解らない。解りたい……、解ってあげたいと思うけど、あなたが教えてくれない限り知ることはできないし、あなたの心を無理矢理こじ開ける権利は、私にはない。それに、知ったとしても理解できる自信はないわ。だって、私は、あなたじゃないから。あなたが長い間抱えてきたものを、一日やそこらで……、そんな簡単なことじゃないわよね。
だけど──」
テリィは振り向かない。
「偉そうに聞こえたならごめんなさい。私は……」
キャンディは息を吸う。
「私は、あなたがこの世に生まれてきてくれて嬉しいの。だって……、生まれてきてくれたから、私はあなたに出逢えたんだもの。もしもあなたがこの世に存在してなかったら、私たちは出逢うことはなかったのよ。──永遠に」
広い肩がぴくりと震え、テリィの顔が振り向きかけた。
「だから……」
一月の風に、滑らかな栗色の髪が靡く。
「テリィ、誕生日おめでとう。生まれてきてくれてありがとう」
キャンディは、宝物のような言葉を一つ一つ嚙み締める。
「今日という日を、この時間を、今この瞬間を、私と一緒にいてくれてありがとう」
青年は、ゆるゆると空を見上げた。今にも落ちてきそうな曇天の空を。
少女もつられて顔を上げる。
二人は暫くの間、その一点を見つめていた。
「あの時は──、空から宝石が降ってきたみたいに俺には思えた」
感慨深げな声が呟く。
「そう……かしら? なんだか私、傲慢じゃない?」
キャンディは居心地が悪そうに俯いた。
「今思うと恥ずかしい……。若かったのね」
「傲慢? どこがだい?」意外そうな顔でテリィが訊いた。
「だって、まるで貴方は私のものよ、って宣言しているみたい」
「は?」テリィは吹き出す。「それは、迂闊だったな。そこまで汲み取るには、あの日の俺は若造だった」
「今思えばよ。あの時は、無我夢中だったもの」
「すると俺は、世界一傲慢な妻をもらったわけだ」
「そうよ」キャンディはいつかの仕返しをする。「貴方にとってはね」
結婚して最初の夫の誕生日──
祝われるべき本人が薔薇の花束を抱えて帰宅したので、キャンディは驚いた。
「どうしたの? あ、今日の公演で貰ったのね」
「いや、劇場近くの花屋に注文した」そう言って、テリィは大輪の薔薇を妻へ差し出す。「キャンディ、君にだ」
エメラルドの虹彩が見開いた。
「テリィ! 今日は貴方の誕生日なのよ。ほら、こうやって貴方のために頑張って作ったんだから」
キャンディはダイニングテーブルに並べられた山盛りの料理を指し示した。
いったい何人分なんだい? とテリィは笑う。それから、
「違うよ」きっぱりとテリィは告げる。
「あの日、君からの言葉を聞いて、17年の人生で初めて俺の誕生日は意味を持った。分厚い雲の隙間から、星々が瞬き始めた。それを教えてくれたのは君だ。
君と出逢わなければ、俺は自分が生まれてきたことを憎んだままだったろう。恐らく一生……」
「そんなことない。私が言わなくても、いずれ貴方は気づいた筈だわ。この十年の間に……」
「いいや、君の夫は、君が思うよりかなり愚か者だよ」
違うわ……と言いかけた桜色の唇を、優しく指が塞ぐ。
「だから、これは君のものだ。あの学院の中で、俺に近づこうとする者は誰一人としていなかった。君を除いてはね。俺は君に……何度も酷いことをしたと思う。なのに、君だけは諦めなかった。──あんなしぶといやつは初めてだった」
「それ……褒めてるの?」
指の下で、キャンディは唇を尖らせた。
勿論さ、とテリィは微笑む。
「キャンディ、俺の誕生日に彩りを加えてくれてありがとう。それから」
テリィは跪き、もう一度、花束を差し出した。
「俺を諦めないでいてくれて、ありがとう」
キャンディは、込み上げてくるものを堪えようとしたが無理だった。
「狡いわ……、こんなの……、貴方の誕生日なのに……」
![]()
土曜の夜は──朝まで君を抱く。
真夜中の月をふたりで見上げ、
日付けが変わる瞬間にキスをして、
夜更けの海を浮流する。
愛してるよ……
君が想うよりもずっと。
君は認めないだろうけど……。
![]() 水仙の画像は、あすかさまのブログからお借りしました。あすかさま、快くご承諾いただきましてありがとうございました
水仙の画像は、あすかさまのブログからお借りしました。あすかさま、快くご承諾いただきましてありがとうございました![]()
タイトルはこちらから![]() 『LOVE SONG』/CHAGE and ASKA
『LOVE SONG』/CHAGE and ASKA
ピアノバージョンです🎹
ラスト近くのテリィの独白『土曜の夜は──朝まで君を抱く』はこちらから(たまたま今年の曜日が歌詞と重なったので引用させていただきました![]() )。
)。