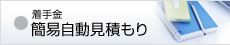判例時報2208号で紹介されていた事例です(大阪高裁平成25年7月26日決定)。
相続分野の規定というのは複雑で,法律解釈としても未解明の部分があったりして,弁護士でもなかなかよく分らなかったりするところがあったりします。
特別受益というのは相続処理に当たっての基本的な概念ですが,民法903条に規定があります。
例えば,相続発生時に存在する遺産が1000万円であったとして,法定相続人が子2人(AとB)であったとすると,法定相続分は2分の1づつとなり,AとBの取り分は500万円づつとなります。
しかし,被相続人が生前に1000万円をAに贈与していたとして,これが特別受益に当たるとされる場合は,生前贈与した1000万円を加えたものを遺産としてみなすこととされており(民法903条1項),2000万円が遺産とみなされます。
そして,2000万円の遺産を2分の1づつの法定相続分で分けると,AとBの取り分は1000万円づつとなり,Aはすでに1000万円を受け取っていることから,これを差し引くと,現存遺産1000万円については取り分はなくなることになり,Bが現存遺産1000万円を相続するということとなります。
持ち戻しの免除の意思表示というのは,上記の処理のうち,
①生前贈与した1000万円を遺産に組み込むこと
及び
②生前贈与分(又は遺贈を受けた分)を受取済みとして差し引く
という処理をしなくてもよいという意思表示を被相続人がすることです。
上記の例で持ち戻しの免除がされたとすると,Aは生前贈与された1000万円に加えて,現存遺産から500万円を受け取ることができ,合計1500万円を被相続人から相続出来るということとなります。Bは500万円しか受け取ることができません。
ただ,持ち戻しの免除の意思表示も,遺留分の規定に反することはできません(民法903条3項)。
遺留分の算定に当たっては,生前贈与された特別受益も遺産として合計することになるので,先ほどの例でいえば2000万円が遺留分算定の基礎となる遺産額となりますが,子2人が相続人の場合の遺留分はその2分の1(1000万円)がそれに当たりますので,AとBの遺留分はさらにその2分の1,金額にするとすなわち500万円ということになります。
そうすると,先ほどの例では,Bは500万円は相続できているので,Aに合計1500万円を相続させるという被相続人の持ち戻し免除の意思表示は有効ということになります。
説明が長くなりましたが,本件事案では,被相続人が遺言によって特定の不動産を相続人Aに遺贈することとして死亡しました。
他の相続人であるBらは,当該不動産についてAが相続したのだから,その分は相続済みとして差し引くべきだと主張したのに対し,Aは,当該不動産については被相続人から持ち戻し免除の意思表示がされており,前記でいえば②の処理はしなくて良いのだという反論をしました。
持ち戻しの免除の意思表示というのは,必ずしも遺言でしなくてもよいものとされていますが,そのように言われているのは主に生前贈与で特別受益が与えられた場合についてです。それは,生前贈与の場合には,何十年の前の生前贈与のことについて遺言によって持ち戻しの免除がされているとは限らないし,そもそも被相続人(遺言者)もそのようなことまで覚えていなかったり,特別受益に該当するかどうかについて正確に理解していないことも多いだろうからです。
しかし,本件のように遺言によって特別受益が与えられた場合には,わざわざ特定の相続人に対して多めに相続させるという効果をもたらす持ち戻しの免除をしたいのであれば,当該遺言によって意思表示がれているべきではないか(遺言必要説)も根強く唱えられており,判例時報の解説によるとこのような考え方が通説的立場であるとされています。
本件では,特に遺言必要説ということを明示しているわけではありませんが,本件の事情の下では持ち戻し免除の意思表示が遺言に記載されているのが通常であるところ,そのような記載がない以上,被相続人がAのみに多めに相続させようという意思,すなわち,持ち戻し免除の意思表示がされていたとはいえないと判断されています。
本件の事情というのは,本件では,Aの主張によると,相続人Bらは被相続人の預金通帳を持ち出すなどしたことから,Bらと被相続人の関係が悪化したために,被相続人としてはAのみに特別受益を与えて多めに相続させようとしていたのだということでしたが,そうであるならば,なおさら,そのことが遺言に記載されていて然るべきであっただろうということです。
本件は確定しているということです。
■ランキングに参加中です。
■着手金の簡易見積フォーム
(弁護士江木大輔の法務ページに移動します。)