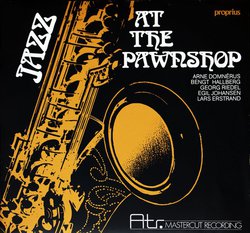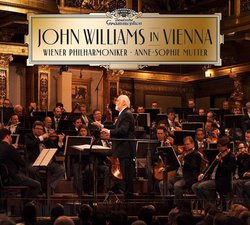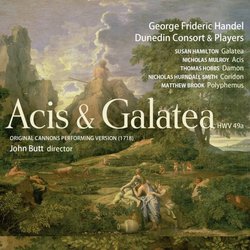====================================
LINN10年の進化を継承、さらに劇的変化を遂げた「MAJIK DSM/4」を徹底レビュ-
レビュー
“超軽量”のアンプ一体型プレーヤー
山之内 正
https://www.phileweb.com/review/article/202009/03/3943.html
■SELEKTの意匠を踏襲、フォノ入力も持つ新たなアンプ一体型ネットワークプレーヤー
リンのMAJIKがモデルチェンジしてMAJIK DSM/4に切り替わった。新しい製品名から、ネットワークプレーヤーとアンプを統合したDSM仕様を継承していること、そして初代機のMAJIK DSMから数えて5世代目を迎えたことがわかる。末尾の数字が変わっただけなので従来路線を受け継ぐ更新と考えがちだが、実は今回、内容・外装ともに劇的な変化を遂げている。変わらないのは名前だけと言っても大げさではない。

LINNのMAJIK DSM/4。SELEKT DSMの外観を踏襲しているが、トップのボリュームノブが省略されているほか、スリットの形状も異なる。フロント上部の6つのボタンにはそれぞれピンアサインが可能で、右は十字キーのような動きで操作が可能。
価格は550,000円(税抜)
photo by 田代法生
リンのネットワークオーディオ製品はKLIMAX、AKURATE、MAJIKの3シリーズ展開が長かったが、新コンセプトのSELEKTが2018年に加わり、4シリーズ構成に拡大した。そのなかでエントリーグレードを担うMAJIKが初代機登場以来の変貌を遂げた背景には、ひと足早く提案されたSELEKT DSMの存在がある。新しいDACアーキテクチャやクラスDアンプを大胆に投入し、大型ディスプレイや新機軸の操作ボタンで使い勝手を一新。ハンドリングしやすい小型ボディに豊富な機能を凝縮し、クオリティと使い勝手の両方でネットワークオーディオの新基準を作り上げた重要な製品だ。
SELEKT DSMは機能と性能の選択肢を複数用意したモジュール設計にこだわりがあるが、それを通常の設計に落とし込んで低コスト化を図ったのが、今回の新しいMAJIK DSMである。
デザインもダイヤル部以外はSELEKT DSMとそっくりだし、DSD対応の最新DAC、35bitデジタルボリューム、ビスポーク製クラスDアンプなど、音質を左右する基幹技術はSELEKT DSMの標準仕様とほぼ同等。フォノイコライザーアンプをURIKA II譲りのアナログ・デジタルハイブリッド回路に格上げするなど、最先端の技術も積極的に投入した。スピーカーを用意するだけでシステムが完成する1BOXのコンセプトを貫きながらも、クオリティ志向はMAJIKシリーズのなかで最も強い。
MAJIK DSM/4の内部。手前が電源部、一番左がクラスDアンプ部、そのすぐ右がDAC部となっている。右側は2段構成で、下段にデジメインFPGAを搭載、SpaceOptimisationやデジタルボリュームなど、DSMの核となる技術が搭載されている
モジュール設計ではないので当然だが、割り切った部分もある。DACのアップグレードやサラウンド仕様への拡張はできないし、アンプ増設に備えた電源回路(ダイナミックパワーサプライ)の強化が不要なので、必要な容量だけでまかなっている。350W×350D×100Hmmの筐体サイズはほぼ共通だが、MAJIK DSMの質量は4.1kg、アンプ内蔵のSELEKT DSMの約半分しかない。
そもそもモジュール設計に比べて機構部品が少ないし、ガラス製ダイヤルをカーソルボタンに変更したり、ケースのアルミ板厚を少し薄くするなど、音質への影響を抑えながらの軽量化と簡素化も進めている。スピーカー端子の間隔が狭いなど、小型ボディならではの短所もあるが、バナナプラグを使えば済むので実用上は問題なさそうだ。
入出力はデジタルの比重が高い。イーサネット/同軸/光/USB-Bに加えて4入力1出力のHDMI(ARC)端子を装備し、Wi-FiとBluetoothにも対応する。アナログ入力は1系統のみだが、メニューでフォノ(MM)入力にも切り替えられる。リンの現行製品の大半が装備するEXAKT LINK端子も省略された。パッシブ型の一般的なスピーカーとの組み合わせをメインに据えていることが理由だろう。
MAJIK DSM/4のリアパネル。ラインとフォノ(MM)共通のアナログ入力が1系統、デジタルはUSB typeB、Coaxial、Opticalに加えてHDMIを4系統搭載する
MAJIK DSMがカバーする音源は着実に増えている。オーディオ用NASからのストリーミング再生に加え、TIDAL、Qobuzなど複数の高音質ストリーミングがハイレゾ再生のメインになる(Amazon Music HDはアップデートで対応予定)。Roonも独自伝送規格で引き続き対応しているし、Airplay 2のサポートも予定。複数のデジタル入力をCDプレーヤーやポータブルオーディオ機器との接続に活用すれば、1系統のみのアナログ入力をフォノ専用に割り当てられる。
今年2月より新操作アプリ「LINN」もリリース。ローカルストリームはもちろん、TIDAL等のストリーミングサービスも直感的に操作・再生ができる
HDMI接続でテレビ(ARC)、BDプレーヤー、ゲーム機など多彩な映像機器がつながるのは、SELEKT DSMと同様、リンの製品ならではのアドバンテージで、リビングルームでの用途が一気に広がる。そのほか、パソコン用にUSB-B端子も付いているし、有線接続が難しい環境ではWi-Fiでネットにつなぐこともできる。スマホの音源を手軽に楽しみたいときはBluetooth(4.2)が使えるが、aptX HD、LDAC、AACには対応していない。
■MAJIK最新スピーカー140 SEと組み合わせ。ナチュラルで誇張のない音調
本体が小さいのでコンパクトなスピーカーと組み合わせたくなるが、今回はあえてフロア型のMAJIK 140 SEを用意した。スタガード接続されたツインウーファーが繰り出す低音はすこぶる反応が良く、俊敏な動きにクラスDアンプの長所を実感。ボリュームを上げてもベースがふくらまず、アタックがぶれないことにも感心した。スペースに余裕があれば、このサイズのスピーカーと組んでスケールの大きなサウンドを狙うのはありだと思う。
LINNのスピーカーMAJIK 140 SEと組み合わせ。アナログプレーヤーにはMAJIK LP12(カートリッジはADIKT)、NASにはfidataのHFAS1-S10を使用している
フル編成のオーケストラを聴けば、それが大げさでないことがわかる。下支えが厚く、トゥッティの音圧は部屋の空気を一瞬で動かすほど余裕がある。基板上でパワーアンプ回路が占める面積があまりに小さいので心配していたのだが、チャンネルあたり100Wという数字は伊達ではなかった。
MAJIK DSMは上位機種と同様にスペース・オプティマイゼーション機能を利用して定在波の補正ができる。試聴室の各種データとスピーカーの位置を入力してリンのサーバーに送信し、同機能をオンにして再生すると、特定の音域でわずかに残っていた低音のにじみが消え、動きの良さが目に見えて改善された。強めのピークが出やすい部屋では絶大な効果を発揮するので、セッティング位置が決まったらぜひ試してみるべきだ。
LINNのMAJIK 140 SEはペア350,000円(税抜)。
パッシブタイプのため、EXAKTには対応しないMAJIK DSM/4とベストマッチな組み合わせとも言える
このMAJIK 140 SE、実はリンのベストセラー機の140を金属製ベースで強化したバージョンで、低音がブレないのはそこにも理由があるのだ。2Kアレイが受け持つ高域と16cmウーファーの立ち上がりや音色がよく揃っていることもあって、ベース、ピアノ、ヴォーカルなど幅広い音域で発音が自然に揃う。中高域は力みや突っ張り感がなく、ジェーン・モンハイトの声は抜けの良さと包み込むような広がりが両立。高い音域も含めて神経質なところはないが、古楽器によるバロックアンサンブルは発音の速さにすぐ気付いた。
MAJIK 140 SEでは、MAJIK 140の足元を強化し、金属製スタンドが標準装備されている
2つのMAJIKの相性が良いことは、LPレコードで聴いたジェニファー・ウォーンズのヴォーカルでも明らかだ。声の質感が素直で、特に中音域から高音域にかけてのなめらかな感触が優れている。アコースティックギターは発音が速く鮮度が高いので、柔らかいヴォーカルとの対比がいっそう鮮やかに浮かび上がる。ベースの音色は緩めだが動きに余分な重さはなく、声やピアノにかぶらず、もたつきもない。今回組み合わせたターンテーブルもMAJIKグレードのLP12で、カートリッジはADIKT。いずれもリンとしてはエントリーグレードながら、ナチュラルで誇張のない音調にリンらしさが感じられた。
アナログ入力のライン/フォノの切り替えはPCのkonfigから行う
MAJIK DSMのフォノステージは前段がアナログ、後段がデジタルのハイブリッド構成で、フィルターの偏差や歪など、アナログ回路を上回る物理特性を実現している。URIKA IIとは異なるMM専用設計で、機能面でも簡略化しているようだが、ハイブリッド構成の利点はけっして小さくないと感じる。それは、『ジャズ・アット・ザ・ポーンショップ』のサックスの実在感、ノイズに埋もれず現場の空気を伝える臨場感など、この録音の聴きどころを漏らさず伝えてくることからも明らかだ。
アナログ盤「Jazz at the Pawnshop」(アルネ・ドムネルス)
■TVと組み合わせて密度の高いリビングシアターも実現可能!
次に55型のOLED TVとUltra HD Blu-rayプレーヤー、パナソニック「DP-UB9000」を用意し、映画やライブなど映像コンテンツを再生した。スピーカーはMAJIK 140 SEをそのまま組み合わせている。
ARC対応のHDMI入力を搭載しているため、リビングシアターユースとしても活用できる
HDMI入力を選び、ジョン・ウィリアムズ指揮ウィーン・フィルのライブを再生する。リニアPCMのステレオ音声(96kHz/24bit)ながら音場はスピーカーの外側まで広がり、カメラが捉えたムジークフェラインザールの豊かな余韻が部屋を満たす。もちろん音場の密度はサラウンド再生ほど高くないが、オーケストラが自然な大きさにまとまるのはステレオ再生ならでは。ステージとの距離の近さを実感できる良さもあり、演奏にすぐ入り込むことができた。ムターの独奏ヴァイオリンは楽器イメージがピンポイントに引き締まり、オーケストラとのバランスに違和感はない。55型の画面ではちょうどよいバランスで画と音の一体感が得られる。
『ジョン・ウィリアムズ ライヴ・イン・ウィーン』(ジョン・ウィリアムズ、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団)。Blu-rayも同梱される
MAJIK DSMとフロア型スピーカーの組み合わせは映画再生でも予想外の効果を発揮した。ステレオ再生なので音の移動感は限定されるとはいえ、特にMAJIK 140 SEはサブウーファー音域も含めてエネルギー密度が高く、効果音の重心が一気に下がるのだ。『バリー・シール アメリカをはめた男』の飛行シーンを再生すると、滑空時のエンジン音の変化を含め、サウンドエフェクトのリアリティが非常に高いことに気付く。付帯音が乗らないのでセリフに誇張がないし、効果音と音楽が重なっても両者が混濁しないなど、ハイファイシステムならではの長所も少なくない。
忠実度の高いステレオシステムを映像機器と組み合わせるのは、リビングルームをホームシアターに進化させる最短の手法の一つなのに、リン以外の多くのオーディオメーカーはHDMI対応に二の足を踏んでいる。AVアンプとの差別化など様々な理由がありそうだが、MAJIK DSMの登場をきっかけにして、今後は少しずつ状況が好転するかもしれない。
■ソナスのブックシェルフとの組み合わせではヴォーカルの表現力が際立つ
ここからはスピーカーをブックシェルフ型に切り替えてハイレゾ音源とLPを聴いていく。いずれも欧州を代表するブランドの人気モデルを3機種用意し、MAJIK DSM/4がそれぞれのスピーカーの個性をどこまで引き出すことができるのか、探ってみた。
MAJIK DSM/4のアンプ性能を試すため、3つの人気スピーカーを組み合わせてテストした
最初に聴いたソナス・ファベールの「Minima Amator II」は、
往年のベストセラーを最新技術でモディファイした話題の小型スピーカーである。
兄貴分のElecta Amator IIIに比べてひと回りコンパクトだが、音楽的な表現力の豊かさでは引けを取らない。今回はOlympica Novaシリーズ用のスタンドに載せて試聴した。
ソナス・ファベール「Minima Amator II」(550,000円/ペア税抜)
一般的なコンポーネントよりもひと回り小さいサイズ感がMAJIK DSM/4とよく似ていて、細部まで隙のないデザインのアプローチにも共通点を感じる。発売後半年ほどだが、筆者はこのスピーカーを何度か聴いていて、そのたびに新しい魅力に気づかされてきた。リンの製品との組み合わせは今回が初めてだが、まず引き込まれたのは
予想通り
ヴォーカルの表情の豊かさだった。
ジェーン・モンハイトとウィリアムス浩子は言葉の発音の素直さと声の感触の生々しさが際立ち、特に
高音部は温度感が高めで
密度の高い音色に魅了される。
声の密度の高さではダニーデン・コンソートのヘンデル『エイシスとガラテア』も双璧をなす。
この録音の特徴であるオーケストラの澄んだ響きはそのまま残しながら、独唱陣の高音の艷やかな輝きが際立ち、一歩前に出て力強い声を発する。
その浸透力の強さは小さめの音量で聴いても失われず、
二重唱ではハーモニーの密度の高さに感心させられた。
MAJIK DSM/4は再生音に余分な強調がないので、
重唱や合唱の和音を混濁なく再現し、
転調を重ねても声の厚みが不自然に変化しないのだ。
余韻の描写も実に繊細で、教会録音ならではの長めの滞空時間と自然な減衰を忠実に引き出すことができた。
ヘンデル『エイシスとガラテア』(ダニーデン・コンソート)88.2kHz/24bit
LP再生ではジェニファー・ウォーンズの
ヴォーカルからしっとりとした感触を引き出し、
歯切れのよいアコースティックギターや
パーカッションとのコントラストに抜群の説得力がある。
ウォームで深みのある声のタッチは、
LP12とMinima Amator IIの外観から受ける印象とも重なり、あえてレコードで聴く楽しみが倍加した
トゥイーターを一新したディナウディオ。リッチで陰影の深い表現を聴かせる
次に聴いたディナウディオのContour 20iは発表からまもない新製品で、筆者も今回初めて聴くスピーカーである。生まれ変わったContour i シリーズのなかで一番コンパクトな2ウェイブックシェルフ型スピーカーで、新開発のトゥイーターEsoter 2i を載せていることが目を引く。ダンパーを改良したウーファーも新開発で、Contour 20iは18cm口径のユニットを積む。
DYNAUDIO「Contour 20i」(700,000円/ペア税抜)
専用スタンドに載せたContour 20iはMinima Amator IIに比べるとふた回りくらい大きく感じるが、深みのあるグレーの仕上げがMAJIK DSM/4のブラック仕上げとよく調和し、落ち着いた雰囲気のインテリアに似合いそうだ。
伸びやかなベースを中心にサウンドの重心が一気に下がり、ソナス・ファベールからディナウディオに変えて音の印象はガラリと変わった。
艶や輝きよりも表情の深みや低音域のふくよかさで聴き手を引き込む力があり、
同じ歌声を聴いても表情に落ち着きが出てくる。
イアン・ボストリッジが歌うベートーヴェンの歌曲など、まさにこのスピーカーで聴きたいと思わせる録音がいくつも思い浮かんだ。ボストリッジの
高音の潤いとなめらかさは新世代トゥイーターの素性の良さを物語っている。
リッチで陰影の深いヴォーカルもいいが、このスピーカーで最も感心したのは
LPレコードで聴いたジャズのライブ音源だ。
サックスの旋律を太めの筆致で描きつつ、リズム楽器はベースを中心に過剰な重さがなく、速めのテンポ感で急き立てるように前に進む。
音の実体感が強いだけでなく、
プレーヤー同士がかわす息遣いやインプロヴィゼーションの気迫など、
形にならない音の描写にも説得力があること。
それがこのスピーカーの新たな魅力と言って良いだろう。
微妙とはいえ音楽表現のなかでは価値の高い情報で、そこが埋もれてしまうと臨場感が一気に後退してしまう。
MAJIK DSM/4のフォノステージはそうした重要なディテールを見事に引き出している。
■B&Wでは音の情報量が多く、細部までクリアに見通せる
最後に聴いたB&Wの805D3はあらためて紹介する必要のない銘機であり、今回用意したスピーカー群のなかでは最も高価格な製品である。MAJIK DSM/4と組み合わせるとスタンド込みで150万円を超え、クラスが一つ上がる。とはいえけっして鳴らしにくいスピーカーではないし、MAJIK DSM/4のアンプ性能を検証するには恰好のモデルと言っていいだろう。
B&W「805 D3」(920,000円/ピアノブラック/ペア税抜)
805D3に変えた途端に気付くのは
音の情報量が多いことだ。
編成が大きくなるほど、音が埋もれず細部までクリアに浮かび上がり、その結果として音楽のダイナミクスレンジが大きく感じられる。
今回聴いたなかではゲルギエフ指揮、マリインスキー劇場管弦楽団のショスタコーヴィチがその典型的な例だ。
第1楽章前半、楽器が次第に増えて和音とリズムが複雑さを増していくなか、
DSD音源に記録された響きを混濁なく緻密に再現し、
クレッシェンドの頂点でも全体の響きが飽和する気配を見せない。
LINNの操作アプリから楽曲名やアーティストも確認できる
MAJIK DSM/4のクラスDアンプは、力で低音を押し出すような方向ではなく、
低音から高音まで緻密に噛み合わせながら、縦を精密に揃えることで一気に
大音圧を引き出すような鳴らし方を得意とするように感じる。
アンプだけでなく、DACとその周辺回路のジッター低減策も功を奏しているはずだが、いずれにしても時間軸方向の情報を精度高く再現していることはたしかで、その点でも上位機種に迫る実力を秘めていると感じた。
レコード再生ではジェニファー・ウォーンズのヴォーカルから
ほどよい潤いを引き出し、
SACDやハイレゾ音源とも微妙に異なる柔らかい歌声をじっくり楽しむことができた。
LP12とADIKTの組み合わせはこれまで何度か聴いたことがあり、一つはそこに理由がありそうだが、MAJIK DSM/4と805D3の相性の良さを垣間見たようにも思える。歪の少ない信号を入力すると、
800シリーズのダイアモンドトゥイーターが本来のなめらかな音を奏でるのだ。
■LINN10年の進化が、エントリーグレードにも確実に受け継がれている
ベストセラーが揃うターンテーブルやスピーカーの例を上げるまでもなく、MAJIKはリンの屋台骨を支える主力の製品群だ。MAJIK DSMもその役割を担う重要な製品だが、発売から年数を経るなかで大きなモデルチェンジが少なく、上位機種に比べて相対的に存在感が薄くなり始めていたきらいがある。
今回のモデルチェンジはその懸念を吹き飛ばす大胆なアプローチであり、再びこのシリーズに注目を引き寄せる効果が期待できる。ほぼ一日かけてじっくり聴いたなかで一番強く印象に残ったのは、リンのハイファイ製品が経験してきたこの10年間の進化の成果が、エントリーグレードのMAJIKにも確実に受け継がれていることだ。特に、最前線に位置する複数のスピーカーと組み合わせたとき、それぞれの個性を正確に鳴らし分けていたことには大いに感心させられた
https://www.phileweb.com/review/article/202009/03/3943_3.html