Twitter、150文字で何ができるのかと思うと、ちゃんとしっかりした文章を読んだり描いたりすることのハードルが上がる気が。某ネット掲示板でも、きちんとまとめて書こうとすると「禿同」だけとかそんなレスが返ってきたりして、ああこれはこういうものに浸っていると、「それのどういうような部分にどう同感なのか」を描けなくなるんじゃないかと思える時がある。
まあ、それでも書ける人は書くんだとは思うけど。これはこれで便利な部分も多いし、面白いところも多々ある。150字の制限の中で速報情報共有が図れたり、今はないけど喫煙室での駄弁りのような楽しさとか(私は喫煙者ではないが)、そういう楽しさはある。
でも、某鉄道サイト(PCケータイ両対応)で若齢者の起こすトラブルを見ていると、Twitterというものは気をつけて使わないといけないし、気をつけることのできない人間はしばらく様子見する必要があるのではないかと一時思った。
もともとこういう家族や家庭や親族で交わされてきたコミュニュケーションが核家族化対策として「社会化」という概念で使われるようになっている歴史はあると思う。
しかし「社会人」という言葉に示されるように、社会人になっていないのに社会に飛び出るというのは、いろいろなリスクが生じる気がする。
そこはそこで頭のいい人たちが作っているのだから対策していると思うし、ここ数日のNHKニュースでの話題としてのTwitter話題のヘビーローテを考えると、なんとかTwitterを先行してきた掲示板やブログでの顛末を踏ませないようにという意識と、「そんなものでしかつながれないのは寂しい」という使いもせずに批評しちゃう意識がまだNHKの中でもぐちゃぐちゃなんだと思う。
事実社会の解体というか、心のスラム化は進行している。挨拶も無し、会釈も無し、何かあれば鬼の首を取ったように叩く。伝聞情報も「だとしたら問題と思われ」で叩く。
そういう揚げ足取り文化というのは掲示板で加速したし、その源流はTVについて大宅壮一が言ったことがまだ続いているのだと思う。
スルー力なんて言うけど、でもそれよりも、何にでもコメントするという切迫感があっては、やっぱりこれも「モモ」の時間銀行ができてからのファスト風土化(宗田好史)と同じ道をたどると思う。
- モモ (岩波少年文庫(127))/ミヒャエル・エンデ
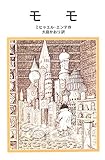
- ¥840
- Amazon.co.jp
- 中心市街地の創造力/宗田 好史

- ¥3,360
- Amazon.co.jp
幸いTwitterの場合はレスに必ず返事をしなければいけないという切迫感は今はないようだけど、でもいずれそういうものができてくるかもしれない。
私なんかは「スローライフ」なんて言葉は大嫌いだけど、でも、ちょっと考えておくことにする、ひとまず棚に上げておくというのも人間の脳の仕組みとして大事な機能だとおもうし、それのためにちょっと自分で調べごとをするとか、それぐらいはしてから返事を返すぐらいでいいんだと思う。
私は歴史家ではないし、小説家と言ってもまだ修業中の身だし、プロといえる専門的知識はない。でも、言いたいことはどうしてもある。そういうとき、ちょっと話したいこととしてこのブログも運用してきたし、自分にプロとしての資格があるかというと、結構忘れごとも多いし、最近は統合失調がひどいので、まだまだだなと思う。
でも、プロであるかないかはお金のことではなく、作品のクオリティなんだと思っているし、そこで審判されるのは当然だと思う。でも、歴史家ではないし、私の書いている歴史は真実ではないと思うけど、かといって歴史家がそんな真実を探り当てているかというと、それだって人間のやること、教科書は書き変わることはあると思うし、また歴史にはイデオロギーの入る余地が大きすぎる。
そう思いつつ、総コメンテーター化の動きはコミュニュケーションの社会化に付随してあるだろうし、その中で私の仕事としての地方再生、過疎化問題、限界集落問題を考えるとき、私の今の師匠の一人は地方議員の中に「ヤホーで調べました」みたいに町の風景を見ずにウェブ検索だけで地方議会の場で発言するものが多すぎると叱っている。
活字を捨てて、町へ出よう、という言葉があったような。若い頃の私はすごく嫌いだったけど、いま何かを書くとき、ウェブも活字も捨てて、とにかくその現場を見て、その時間、歴史の一部を全力で感じる大事さを思い知らされる。
そして、その全力で感じなければならない時は、私はメモも取らないし、ケータイもPCも使わない。実況なんてしない。まず感じて、そこからしばらくして、落ち着いてから時間があるときに浮かぶ感情や感覚を言語化し、統語して、それからメモる。そしてそれのなかからテキスト化して仕上げる。
本質に触れるときに、実はケータイとかPC、さらには極端な話、紙メモですらもかえって邪魔になることはけっこうある。そして、コメントをすぐ返すより、しっかり筋道を立てて考えることを留意する必要はあると思う。
何が本質かは議論はあるだろうけど、でも重度のTwitter中毒は、かつて実況までするウェブ日記中毒だった私としては、またそういうものにはまるといけないなと思えて、ちょっと慎重になってしまう。それだけTwitterそのものが面白いところがあるからなんだけど。
頭の切り替えができる人、技術は万能に近づいているけど21世紀初めではまだまだ途上にあることを痛感している人でないと、いろいろとリスクが大きくなると思う。まあリスク管理は今の世の中では各人が意識してやらないといけない常識だと思うので、悲観も楽観もしない。でももうちょっと日本語対応を詰めて欲しいと思ってしまうのも私である。
話題が分散した感じもあるけど、でもTwitterはデメリットよりメリットの方が私には多い気がします。いろいろとフォローしてくれたりフォローさせてもらったりでありがたいです。
嫁もTwitterを始めているけど、まだなにをどうしたらいいのかわからない状態の模様。まずフォローからすべてが始まるのがTwitterのおもしろさだと思うけど。
それと、Twitterもやっぱり使ってみながら検討するのも、またそれも「感じる」大事なことだと思う。頭ごなしの否定は、手放しの肯定と同じくリスキーだと思う。
結局は使う人によるところも大きいのだから。「まず使ってみましょう!」と思う。それで合わなかったらしばらくアカウントを休眠させてもいいんだし。
私の場合は特に通信とかも研究しているので、ちょっとやってみようと思った。シュミの段階だけど。でも結構こういう通信技術は大事だと思う。特にあれほど「私はケータイは持たない!」なんて言っているおじさんたちが結局持つことになり、その結果市場がふくらんで基地局が増え、登山時の緊急通報にケータイが使えるなんてのも技術の進歩なのは間違いないし。
案外、ユビキタスコミュニュケーションとかもこういう形で少しずつ実現しているんだろうな。これはこれで未来を考えるヒントになりそうなので、興味を持ったし、それはそれでいろいろ役に立っている。
ありがたいです。本当に。
クリックありがとうございます。いつも励みになります。