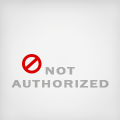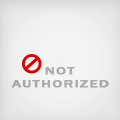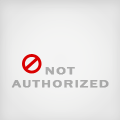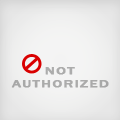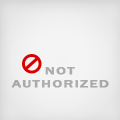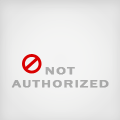小さな村イーボンソンに泊まる
カローから次の目的地ターズィの町までの数十キロは「ずっと下り」だと聞いた。
町で話す誰もが僕のこれから向かう道を「easy」だと言った。
そうしたこともあり、ちょうど出発のこの日が5日に1度市場が盛大になるファイブデイマーケットだと聞いていた僕は朝から午前中の時間を利用してカローの市場をゆっくりと散策し、遅めの時間に町を出た。
幹線道路に出て山々に囲まれた道を少し進むと、聞いていたとおりの「下り坂」が始まった。
「easy、easy♪」
僕は上機嫌でサドルから腰を上げ、立ちこぎの姿勢で余裕を見せて坂道を下っていた。
それがいつのまにか眉間に皺の寄った険しい表情に変わっていたことに、僕は自分自身しばらく気がつかなかった。
登り坂が登場したわけではない、下りだと聞いていた道は確かに下りだった。回転ペダルに力を注ぎこまなくても荷重と体重の付加によって自転車は自ずと坂道を下りながら、かつ目的地へと向けて進行していた。
しかし走り始めてから1時間、既にこの日2度目のパンクにみまわれた時、僕は夕刻までにターズィへ着くことが無理であることを悟った。
いかんせん、下り坂ではあれど、道路事情が悪いのだ。
舗装されている道路でも目は荒く穴だらけ、ゴツゴツとした石があちらこちらにとび出している。山間部の道は細く、にもかかわらず何台もの工事車両の大型トラックがほこりを巻き上げながら通過していく。穴ぼこだらけの道を避けて進むため、ブレーキをかけながら慎重に進み、トラックが通過するたびに道路脇ぎりぎりまで避けて待たなければならない。
ペダルをこがなくとも加速していくという本来最高の状況は、この日の僕のルートにとってむしろ邪魔になるものでしかなかった。「easy」なのは単に「下り」だという景観による判断と車両で通過したならば、という条件を伴った判定でしかなかったのだ。
下りにもかかわらず、フラットな道をのんびりと走っていくよりも遅いスピードで進んでいた僕は、午後4時を過ぎた時点で1日の半分程度までしか消化できていないことを知り、愕然として道路脇に座りこんでうなだれた。
連なる山々の途中には道が平坦に続くところもあり、そうしたところには小さな村が存在していたが、ゲストハウスやホテルというものは皆無だった。
余裕綽々でファイブデイマーケットを散策してから遅い時間に出てきたことを後悔しそうにさえなる。
「野宿をするか、真夜中までかけて自転車を走らせるか・・」
そんな覚悟の二択をせざるを得ないことに苦笑しながら、通りかかった小さな村の売店に食料と水の調達を兼ねて休憩しようと立ち寄った。
何か食べ物とペットボトルの水はないかと尋ねる僕に、店の奥にいたおばさんは申し訳なさそうに
「ないんだよぉ・・」
と答えた。
売店でありながら腹の足しになりそうなものは何一つ店頭に置いていない。せいぜいいくつかの飴玉を詰め込んだ袋が、陳列されているというよりは散らばっているといった状態で売られているだけだった。
これからの状況に加えて、この店の貧相な様子まで見てますます気が滅入ってきた。
店の前に置かれていた木の椅子に座り、仕方なく非常食のつもりでバッグにしまっておいたビスケットを取りだして一口かじり、残っていたペットボトルの水をがぶがぶと飲み干した。
「はぁぁぁ・・・」
大きく伸びをして背もたれにもたれかかると、なんだか何もかもがどうでもよくなってきた。
売店は、この村では珍しく大きな、レンガで作られた2階建ての家の一階に構えられていてそこに家族が住み、広い敷地内には他に藁ぶき屋根の高床式家屋が2,3軒あり、ここにも同じようにして人々が住んでいた。あちらこちらの家から子供たちが出てきたかと思うと、別の家に入っていき、きゃぁきゃぁ言いながら出てきたかと思うとまた別の家にかけこんでいく。
こうした自由に出入りしている姿からすると、これまでラオスや他の国の小さな村でも見られたように、集落そのものが一つの家族といった感じで共同生活を営んでいるようだった。
そんな様子をぼぉっと眺めていたところ、かわいらしい小さな女の子が目の前にやってきて、木の実とプラスティック容器に入った一杯の水を差し出してくれた。
疲れて遠い目をしていた僕はふと我に返ったように、
「あ・・、チェーズ―ベー(笑)」
ありがとう、と言ったのだが、僕の一言が終わるか終わらないかのうちに女の子は恥ずかしそうに照れ笑いしながら家の中へタタタッと走って逃げていってしまった。
さっきまでそこら辺をかけまわっていた子供たちがいつのまにか、家の中からドア越しにこちらをうかがってはサッと隠れたりして、どこからともなく自転車でやってきた僕のことを気にかけている様子だった。
僕は風船がバッグにしまってあったのを思いだして、一つ取りだして膨らませてみせた。
「なになに・・?」
という感じでちょっと近づいてきた子供たちは、持っていた風船の口を離してぴゅーっと飛ばすと、びっくりしてまた家の中へ慌てて逃げていった。
「おいでおいで!!(笑)」
僕は新たな風船を取りだすと、子供たちに手招きをして呼んだ。
昨日、カローの町で風船屋のおじさんと仲良くなっていた僕は、この先、どこかで出会った子供たちと遊ぶときに使おうと風船の入った大袋をまるごと買わせてもらったのだ。膨らませると2メートルにもなる特大の風船。その翌日に早速こんな形で使うことになるとは思ってもみなかったが、ちょうどいい場面でもある。
子供たちの中の1人に一つ膨らませて渡してあげると、「僕のも!!」「あたしのも!!」といった感じで飛びついてくるようになった。
次から次へと風船を渡しているうち、気がつくと家の広い庭が人で溢れ返るほどになっていた。大人たちまで集まってきて、あの子にもやってくれ、この子にもやってくれ、と。
気がつけばどこから話を聞きつけたのか、村中から子供たちがこの家に集まってきて、収拾がつかないほどの大風船大会になっていた。
あまりにも大勢やってくるのでたまりかねたお母さんたちが
「はいはい、もう風船は終わりだよ!!売りきれ売りきれ!!さぁ帰った帰った!!」
という感じで、大声を張り上げながら次から次へとやってくる子供たちを追い返すほどだ。
100個くらいあった風船はあっという間になくなってしまった。
しかしことのほか、この村の皆が喜んでくれたおかげで僕は楽しいひとときが過ごせたことに満足していた。
大風船大会が終わると、僕は家の中へ招かれた。
お茶をいただきながらさっき撮った写真を見せてあげていると、部屋の真ん中にどすんと腰を下ろしていたお父さんが僕にジェスチャー交じりで言った。
「今日は泊まっていきなさい」
野宿をするか、真夜中までかけて走るかの二択を迫られ、休憩がてら立ち寄ったこの村でもう開き直ったように遊んでいた僕にとってこの上なく最高の一言をいただき、そして僕はひょんなことからこの家族(トゥマナ一家)にお世話になることになった。
両手を合わせ、
「チェーズ―ティンバーデー。。」
ありがとうございます、と告げた直後には
「そうと決まったら遊ぼっ!!」
と言わんばかり、子供たちに手をぐいぐい引っ張られて外へ連れだされていた。
夕暮れ時、家では女性たちが夕食の準備にとりかかっていた。
庭でさんざん走りまわった後、今度は村の若い男衆と共に水浴びへ。
カローから山あいを抜けて行く途中にあるこの村はやはり標高も高く、大きな水がめに蓄えられた水を洗面器でジャバジャバとすくって体にかけるたびに悲鳴をあげるほどの寒さだった。しかし、ゲストハウスの水シャワーならものの3分で切り上げそうなその寒さも、毎日こうしてここで水浴びをすることが日課の村人たちと一緒になって頭や体を石鹸で泡立ててゴシゴシ洗っていると、寒さを通り越してこのわずかな時間がとても貴重なものに感じられた。
水浴びを終えて家の中へ戻ると、中央の丸テーブルに夕食が並べられていた。
「早く早く!!」
と手招きするお母さんや子供たちを前に、濡れた頭をタオルでゴシゴシ拭きながら僕は食卓を囲む席へ腰をおろした。
村での素朴な食事。
炊きたてのご飯に菜の花みたいなものの炒め物、煮物、暖かいスープ。
ラオスでの日々を思いだして、少し懐かしい気持ちがした。
ミャンマーを訪れて、今はまた新しい出会いの中でこうして素敵な人たちに囲まれて食事をさせてもらっていることが何よりも至福だった。
夜8時、近所の村人たちが次々と家に集まってきた。
何が始まるのかと不思議に思って見ていると、部屋の片隅に置かれていた一台のテレビが運び出されてきた。やってきた人々は皆、座敷の上に並んで座り、テレビの電源が入るのを待つ。
ざわざわとしていた家の中は、トゥマナ一家の長男ソードゥの「つけるよ!!」の一言で、まるで小さな映画館で上映開始のブザーが鳴らされた時のように、静かになった。
ここら周辺ではこの家にしかテレビというものがないのか、夜の決められた時間になると一斉に近所の人々が集まってきて皆でテレビ鑑賞会を開くことが日課のようだった。
テレビ画面には、大きな舞台が映し出され、そこで青い服を着た若い男と黄色い服を着た若い女性が少し早口の言葉で何やら掛けあいの漫才のようなことをしている。2人が何か言うたびに、それを見ている村人たちはゲラゲラ笑いながら楽しんでいる。日本でいうと「吉本新喜劇」でも見ているといった感じなのだろうか。
小さな子供から大人までその画面の中の舞台で展開される模様にかじりつきながら見入っている姿が、この村の日常風景をとてもよく表している気がしてなんだか嬉しくなった。
夜10時を過ぎた頃、テレビ鑑賞も終わって皆一斉にそれぞれの家へと帰っていく。
ようやく静かになったところで寝る準備を始めるのかと思っていると、今度はトゥマナ一家のお父さん以外全員が外へ出て庭の薪を囲んで座り始めた。
大きな鍋が運ばれてきて中央に置かれると、お母さんたちが夕食の残り物やさらに具材を加えて「おじや」のようなものを作り始めたのだ。
「まだ寝なくて大丈夫かい?疲れてるんだから無理して合わせなくていいよ」
というようなことを言って気遣ってくれたけれど、僕が
「みんなと一緒にいたいんだ」
と告げると、
「そうかい。。じゃぁ座りな」
と言って薪を囲む席を一つ空けてわけてくれた。
夜になり、外はだいぶ寒い。
それでも薪の火に手をかざし、皆が談笑しながらおじやの出来あがりを待っている時間、僕はずっと温かいものに包まれていた気がした。
出来あがったほくほくのおじやを一口、また一口と味わうたびに、幸せの香りが体中に広がっていく。
吐く息は白く、凍えそうな寒さのはずなのに、そんなことも忘れて僕は夜更けまでトゥマナ家の人々と語り合い、山あいの小さな村での一夜を過ごしたのだった。